授業についていけない ! 発達障害の特性と効果的なサポート方法

授業についていくのが難しいと感じることは、発達障害を抱える子どもたちにとって大きな悩みの一つです。
授業中に集中が途切れてしまったり、先生の説明が理解しきれなかったり、周りがどんどん進んでいく中で自分だけが遅れているような気がして、不安や焦りを抱えているかもしれません。
こうした授業についていけない状況が続くと、「自分はできない」と自己否定的な気持ちになってしまい、学びへの意欲が失われてしまうこともあります。
しかし、発達障害の特性に合わせた工夫やサポートがあれば、少しずつ授業に前向きに取り組むことが可能です。
この記事では、発達障害の特性に応じた授業の理解が難しい理由を解説し、効果的なサポート方法を紹介していきます。
また、授業中に学校でできる支援や家庭での工夫など、無理なく取り入れられるアイデアもお伝えします。
子ども自身だけでなく、保護者や先生が一緒にサポートをすることで、授業についていける可能性は広がります。
子ども達が抱える「どうしたら授業がわかるようになるのか?」という問いに対する具体的な対策が、この記事を通して見つかるでしょう。
今できる小さな工夫から始め、前向きな気持ちで授業に向き合えるヒントをぜひ見つけてくださいね。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
授業についていけないと感じる理由とは?発達障害の特性に注目しよう

発達障害のある子どもたちは、それぞれ異なる特性を持っており、それが授業についていく上でのハードルになることがあります。
自分が授業についていけないと感じる原因を理解することは、適切なサポートや工夫を見つけるための第一歩です。
ここでは、発達障害の特性に注目し、授業についていくのが難しいと感じる理由について具体的に解説します。
ADHD(注意欠如・多動症)の場合
ADHDの特性を持つ子どもたちは、集中力が持続しにくいことが原因で、授業についていくのが難しいと感じることがよくあります。
例えば、先生の話に集中していたのに、ちょっとした物音やクラスメートの動きに気を取られ、その瞬間に授業の内容が分からなくなってしまうことがあります。
また、課題や指示が複数あると混乱してしまい、どこから手をつければ良いか分からなくなってしまうこともあります。これにより、周りが理解を進めている中で、自分だけが取り残されているような感覚を抱きやすくなります。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合
ASDの特性を持つ子どもたちは、言葉の意味や状況の変化を理解するのに時間がかかることがあり、授業についていくのが難しいと感じることがあります。
例えば、先生が急に話題を変えたり、曖昧な表現を使ったりすると、その内容が理解できず、授業が進むたびに混乱してしまうことがあります。
また、感覚が過敏な場合、教室の照明や音が気になって集中しづらく、授業内容に意識を向けるのが難しいと感じることも少なくありません。
SLD(限局性学習症)の場合
SLD(限局性学習症)の特性がある子どもたちは、特定の学習分野において難しさを感じるため、授業についていくのが難しいと感じることがあります。
例えば、文字を読むことが苦手な場合、国語や英語の授業で教科書の内容が理解できなかったり、数学で数字や記号を正確に捉えられなかったりすることがあります。
このため、他の生徒と同じスピードで理解を進めるのが難しくなり、自分だけが授業から遅れてしまうように感じてしまうことがあるのです。
その他の授業の難しさ
また、発達障害の特性により、集団の中で発言することや、教室内で指示を素早く理解して行動することが苦手な場合もあります。
先生が複数の指示を出したり、授業中に取り組むべき内容が変更されたりすることで、ついていけなくなってしまうことがあり、授業そのものが「自分には難しい」と感じられる原因になっているのです。
このように、発達障害の特性によって、授業についていくのが難しいと感じる理由はさまざまです。
こうした特性を理解することで、授業中に必要なサポートや工夫を考えるヒントが見えてきます。
自分がなぜ授業についていけないと感じているのか、その理由を知ることが、勉強を前向きに進めるための第一歩です。
集中力が続かない……ADHDの特性と授業対応策
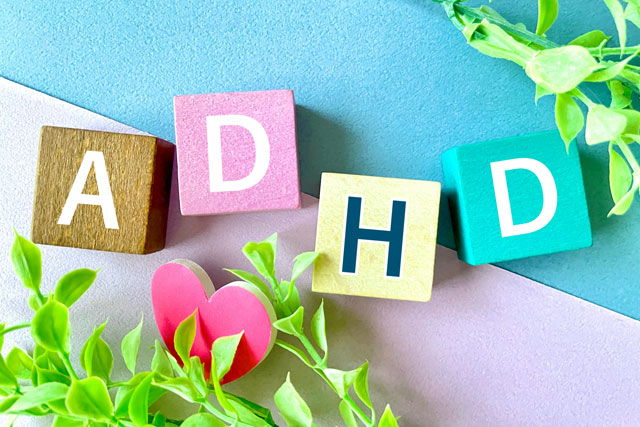
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ子どもたちは、集中力が続きにくい、気が散りやすいといった困難を抱えがちです。
このため、授業中に先生の話が頭に入ってこなかったり、授業の途中で他のことに意識が向いてしまい、内容についていけなくなることが多くあります。
ここでは、ADHDの特性による集中力の課題と、授業での具体的な対応策について解説します。
ADHDの特性による集中力の課題
ADHDの特性には、「注意散漫」「衝動的な行動」「多動性」などがあり、これが授業中の集中を妨げる原因になります。
例えば、周りの物音やクラスメートの動きに気を取られやすいため、授業に集中するのが難しいことがよくあります。
また、興味がある話題には集中できても、少しでも興味が薄れるとすぐに注意が散ってしまうこともあります。
このように、集中力が断続的になることで授業内容が途切れ途切れにしか理解できず、自分だけが置いていかれるような感覚を抱きやすいのです。
集中力を保つための具体的な授業対応策
集中力が途切れやすい場合でも、いくつかの工夫で授業への集中をサポートすることが可能です。
以下の対応策を試してみることで、少しずつ集中力を持続させやすくなります。
座席の配置を工夫する
ADHDの子どもには、窓際や教室の後方ではなく、前方で先生が見やすい位置に座ることが効果的です。
先生の話が聞こえやすくなるだけでなく、周囲の刺激を少なくできるため、集中力を高めやすくなります。
短い休憩を挟む
ADHDの子どもは長時間集中するのが難しいため、授業の中で5分程度の小休憩を取り入れると良いでしょう。
短いリフレッシュの時間を挟むことで、気持ちをリセットしやすく、次の内容に集中しやすくなります。
学校によってはこのような工夫が難しい場合もありますが、家庭学習においても同じ方法を試してみましょう。
具体的で短い指示を出す
授業中の指示をできるだけ短く、明確に伝えてもらうことも効果的です。
例えば、「この段落だけ読んでみよう」といったように小さな目標を設定すると、達成感を味わいやすく、次の指示に集中しやすくなります。
また、複数の指示が一度に出されると混乱しやすいため、一つずつ段階的に指示を出してもらうよう、先生にお願いすると良いでしょう。
視覚的なサポートを取り入れる
ADHDの子どもには、文字だけでなく図やイラストを使った説明が理解を助けます。
教科書に重要なポイントをマークしたり、授業内容を絵やチャートにして視覚的に整理したりすることで、集中して内容を理解しやすくなります。
家庭でできるサポート
学校での対応に加えて、家庭でも集中力をサポートする工夫を取り入れてみましょう。
例えば、宿題や家庭学習の際にも「15分集中したら5分休憩する」というリズムで取り組むと、無理なく勉強が続けやすくなります。
また、タイマーを使って勉強時間を視覚的に示すことで、集中しやすい環境が作れます。
ADHDの特性によって授業中の集中力に課題があっても、さまざまな工夫を取り入れることで少しずつ改善していくことができます。
自分に合った方法で、少しずつ集中力を高め、授業に前向きに取り組んでいきましょう。
理解に時間がかかる……ASDの特性と授業でのサポート方法

ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ子どもたちは、授業での内容理解に時間がかかることが多くあります。
特に、言葉の意味をすぐに把握するのが難しかったり、授業の進行が突然変わったときに混乱してしまったりすることがあり、周囲に遅れを感じやすくなります。
ここでは、ASDの特性による理解の難しさと、授業での具体的なサポート方法について紹介します。
ASDの特性による理解の難しさ
ASDの子どもたちは、抽象的な表現や比喩、突然の話題の変更に対する理解が難しい場合が多くあります。
例えば、先生が例え話を用いたり、曖昧な表現を使うと、その意味をすぐに理解できず、授業の流れについていけなくなることがあります。
また、順序立てて説明することを好む一方、予想外の出来事や話題の転換に弱く、急に違う話題になると混乱してしまうこともあります。
その結果、周りとペースが合わなくなり、「自分だけが分からない」と感じやすくなります。
理解を助けるための具体的なサポート方法
ASDの子どもが授業についていくためには、理解しやすい工夫や環境づくりが重要です。
以下は、授業での理解をサポートするための具体的な方法です。
視覚的な補助を活用する
ASDの特性を持つ子どもには、言葉だけでなく、図やイラスト、チャートなど視覚的なサポートを取り入れると理解が進みやすくなります。
例えば、重要なポイントを教科書に色分けして表示したり、手順を図にして示すと、流れを追いやすくなります。
先生が黒板やホワイトボードに図を描きながら説明することで、内容が頭に入りやすくなります。
予測できる流れを作る
ASDの特性として、授業の流れや話題が急に変わると混乱しやすいため、授業の前にその日の内容を簡単に予告してもらうと良いでしょう。
「今日は最初に数学の例題を解き、その後に応用問題に入る」というように、授業の流れがわかると安心感が生まれ、理解が進みやすくなります。
抽象的な言葉は具体的に説明する
比喩や抽象的な表現が多い場合、具体的な例を加えると、ASDの子どもが内容を理解しやすくなります。
例えば、「感情表現を豊かにしよう」という説明に対して、「喜んだときには笑顔を見せる」「悲しいときには肩を落とす」という具体的な行動で例示するとわかりやすくなります。
一度に多くの情報を伝えない
ASDの子どもは一度に大量の情報を処理するのが難しいため、授業中に新しい内容が次々と出てくると負担がかかります。
段階的に一つずつ説明し、「どこまでが理解できたか」を確認してから次に進むことで、授業内容がわかりやすくなります。
家庭でできる理解のサポート
学校でのサポートに加え、家庭でも授業内容の理解をサポートする方法があります。
例えば、授業の内容を一緒に復習し、特に難しかった部分をゆっくり説明し直すと、少しずつ内容を理解しやすくなります。
また、家庭で視覚的なツール(図表、単語カードなど)を使いながら勉強することで、情報が頭に入りやすくなり、授業に前向きに取り組みやすくなります。
ASDの特性による授業の理解の難しさも、視覚的なサポートや段階的な説明を活用することで解決の糸口が見つかります。
無理に急がず、少しずつ理解を深めていくことで、授業への不安が減り、安心して取り組むことができるでしょう。
読み書きが苦手……SLD(限局性学習症)に応じた学習支援

SLD(限局性学習症)の特性がある子どもたちは、読み書きの課題に対して特に困難を感じやすく、授業についていくのが難しいと感じることがよくあります。
文字を読むのに時間がかかる、板書を写すのが遅れる、正確に書き写すのが難しいといった特性があり、他の生徒と同じペースで授業を進めるのが難しいことが多くなりがちです。
ここでは、SLDの特性による読み書きの課題と、それに応じた学習支援方法について解説します。
SLDの特性による読み書きの課題
SLDの特性には、特定の分野における学習の苦手さがあり、特に「ディスレクシア(読みの困難)」や「ディスグラフィア(書字の困難)」などが影響して、文字や文章の処理が難しいことが挙げられます。
例えば、文章を読むときに文字が飛んで見えたり、文脈を理解するのに時間がかかったりするため、授業の板書や教科書の内容をすぐに理解するのが難しいことがあります。
また、黒板に書かれた内容をノートに正確に書き写すのが遅れ、授業の内容を十分に把握できなくなることもあります。
読み書きの負担を軽減する具体的な学習支援方法
SLDによる読み書きの苦手さをサポートするためには、理解しやすい環境や補助ツールの活用が役立ちます。
以下のような学習支援を取り入れることで、授業への取り組みやすさが向上します。
音声教材や読み上げソフトの活用
読むのが難しい場合、教科書やプリントを音声で聞くことができる「音声教材」や「読み上げソフト」を利用すると、内容の理解がしやすくなります。
特に長い文章を読むと疲れやすい場合、聞くことで理解がスムーズに進むため、授業中の負担が軽減されます。
ノート代わりにタブレットを使用する
手書きでノートを取るのが難しい場合、タブレットやパソコンで文字を入力してノート代わりにする方法も効果的です。
タイピングの方がスムーズに進む子どもには、デジタルノートを活用することで授業の内容を効率よく記録することができます。
また、授業内容をデジタルで整理しやすいため、復習の際にも便利です。
視覚補助を使った板書の記録
黒板の文字を書き写すのが苦手な場合、先生の許可を得て板書を写真に撮るなど、視覚的に内容を補助する方法もあります。
写真を撮った内容を後でじっくり見直すことで、理解を深めやすくなり、授業中の負担も減ります。
板書に集中しすぎて内容が頭に入らないときにも、この方法が役立ちます。
マークや色分けを使って情報を整理する
読み書きが苦手な場合、ノートや教科書に重要なポイントをマーカーで色分けしておくと、視覚的に整理しやすくなります。
例えば、赤はキーワード、青は重要な説明といった具合に色を使い分けることで、見直しが簡単になり、要点が理解しやすくなります。
家庭でできるサポート
学校での支援に加え、家庭でも読み書きのサポートができます。
例えば、家での学習においても、音読を取り入れることで文章への理解が深まることがあります。
また、テキストを大きな文字で印刷したり、教科書を音声で聞くことで、負担を軽減しながら理解を進められます。
家庭学習においても、スムーズに進められる方法を探りながらサポートしていきましょう。
SLDの特性による読み書きの困難さも、適切なサポートやツールを活用することで、授業に前向きに取り組めるようになります。無理せず、自分に合った方法で学びを進めることで、授業への不安が少しずつ軽減されるでしょう。
学校でできる支援とは?発達障害に対応した配慮と工夫

発達障害のある子どもたちにとって、学校での支援や配慮があることで、授業についていきやすくなり、安心して学べる環境が整います。
ここでは、発達障害に対応した学校での具体的な支援方法や配慮についてご紹介します。
個別に対応した学習計画の作成
発達障害の特性に応じて、個別の学習計画を立てることで、子どもが無理なく学べるように支援することが可能です。
例えば、特別支援学級や通級指導を活用し、理解が難しい部分を補う授業を設けることで、個々の学習ペースに合わせた指導ができます。
また、個別計画に基づいて、どのようなサポートが必要かを明確にし、授業内容のカスタマイズができると効果的です。
配慮した座席の配置
発達障害の子どもが授業に集中しやすくするために、座席の配置を工夫することが支援になります。
例えば、ADHDの特性がある場合は、窓やドアから離れた席にすることで、周りの刺激を減らし集中しやすくします。
ASDの特性がある場合、他の子どもたちと適度な距離をとることで、気が散りにくくなる効果もあります。
授業に集中しやすい環境づくりとして、座席の場所を検討することが有効です。
授業中の短い休憩を取り入れる
発達障害の特性があると、長時間集中するのが難しい場合があります。
授業の途中で数分間の短い休憩を取り入れることで、気持ちをリフレッシュしやすく、次の学習内容に集中しやすくなります。
特に、ADHDの子どもにとっては、体を少し動かすことで集中力が回復しやすくなるため、授業の中で小さな休憩を設けると良いでしょう。
補助ツールの活用
発達障害のある子どもたちが学習内容を理解しやすくするために、補助ツールの活用が役立ちます。
例えば、読み書きが苦手な子どもには、タブレットを使った音声読み上げソフトや、デジタルノートが便利です。
また、図やイラストを用いた教科書や、文字の色分けをして視覚的にわかりやすくする工夫も、理解を助ける支援として効果的です。
支援教室や特別支援学級の利用
学校によっては、発達障害の子どもたちの学びを支えるための支援教室や特別支援学級が設置されています。
これらのクラスでは、通常の授業よりもゆっくりと進めたり、理解しやすいように内容を工夫した授業が行われます。
必要に応じて支援教室を利用することで、子どもが安心して学べる環境が整い、苦手な分野もサポートしながら取り組むことができます。
コミュニケーションの取り方を工夫する
ASDの特性がある場合、曖昧な表現や暗黙の了解がわかりにくいことがあります。
授業中の説明や指示を具体的に伝えたり、少しずつ進行内容を確認しながら授業を進めると、子どもが内容を把握しやすくなります。
また、困っているときに自分から声をかけられない場合もあるため、先生が「大丈夫?」と確認することで、安心してサポートを受けやすくなります。
学校でできる支援や配慮を取り入れることで、発達障害の子どもたちも安心して授業に取り組めるようになります。
子どもの特性に合わせたサポートを提供し、無理なく学べる環境を整えることが、学習の充実につながるでしょう。
家庭でできる勉強サポート!授業の内容を補う工夫

発達障害のある子どもにとって、授業内容をすべてその場で理解するのは難しいことがあります。
家庭でのサポートによって、授業の内容を補い、学習への自信を育むことができます。
ここでは、家庭でできる具体的なサポート方法や工夫を紹介します。
授業内容の復習を習慣化する
授業で学んだ内容を家庭で復習することで、少しずつ理解が深まります。
特に発達障害がある場合、同じ内容を繰り返し確認することが理解の定着につながります。
例えば、教科書やノートを一緒に見返し、重要なポイントを簡単に復習するだけでも効果があります。
無理に詰め込まず、少しずつ復習を習慣化することで、理解度が高まります。
音声や映像教材を活用する
発達障害の特性により、文字だけでは理解が難しい場合、音声や映像を使った教材が役立ちます。
例えば、教科書の内容を音声で読み上げるアプリや、わかりやすい映像解説を視聴することで、視覚や聴覚から内容を理解しやすくなります。
また、アニメーションやビジュアルで説明している教材を使うと、興味を持ちやすく、内容が頭に入りやすくなります。
自宅学習の際に短い休憩を入れる
集中力が続かない場合、勉強を短時間に区切り、適度に休憩を取る方法が効果的です。
例えば、15分間勉強したら5分間休憩を入れるといったリズムを作ると、無理なく学習を続けやすくなります。
集中して取り組める時間を見つけ、短時間で区切りながら学習を進めることで、負担を軽減しながら理解が深まります。
ビジュアルな学習サポートを取り入れる
発達障害の特性として、視覚から情報を得る方がわかりやすいことが多いため、ビジュアル的なサポートを取り入れると効果的です。
例えば、図表やイラストを使ったノート作りや、単語カードを活用することで、学んだことを整理しやすくなります。
色分けや絵を使ってポイントを視覚化することで、見直す際にもわかりやすく、復習がスムーズになります。
ポイントをわかりやすくまとめる
授業の内容を一度にすべて理解するのが難しい場合、特に重要なポイントを短くまとめて復習する方法が有効です。
例えば、国語の内容なら「この物語のテーマは〇〇」、数学の内容なら「この公式を覚える」といった形で、理解すべきポイントを要約してあげると、無理なく取り組みやすくなります。ノートやカードにまとめることで、復習の際に役立ちます。
勉強に対するポジティブな声かけをする
家庭で勉強をサポートする際には、ポジティブな声かけも効果的です。
学習の進捗や小さな達成を認め、「今日はここまでできたね」「よく頑張ったね」といった声かけをすることで、勉強に対する自信が育まれます。
特に発達障害がある子どもは、学習に苦手意識を持ちやすいため、積極的に励まして自信を引き出してあげましょう。
家庭でのサポートを通して、少しずつ授業の内容が理解できるようになると、子ども自身も「できる」という感覚を得やすくなります。
無理をせず、楽しみながら学べる工夫を取り入れることで、学習に前向きに取り組めるようサポートしていきましょう。
できることから始めよう!無理なく授業についていくためのステップ

授業についていくのが難しいと感じると、勉強そのものが負担に感じられることがあります。
発達障害のある子どもにとって、無理なく授業に参加できるようにするには、少しずつできることから始め、小さな成功体験を重ねることが大切です。
ここでは、授業についていくための具体的なステップを紹介します。
授業前に「今日の目標」を決める
授業についていくためには、まず簡単な目標を持つことから始めると効果的です。
例えば、「今日は先生の話を5分間しっかり聞く」「授業の最初の部分に集中する」など、小さな目標を設定します。
目標を達成することで、「自分にもできる」という達成感が得られ、少しずつ自信がついていきます。
予習で授業内容を少しでも把握しておく
授業の内容に先に触れておくと、授業中の理解がスムーズになります。
例えば、教科書を軽く読むだけでも「この話は聞いたことがある」という感覚を持ちやすくなり、授業への安心感が増します。
予習の際には、教科書の見出しや太字の部分を読む程度でも十分です。
新しい内容を事前に知っておくことで、授業中の不安が減ります。
授業中に気になることをメモに残す
授業の内容をすべて理解するのが難しい場合、気になることやわからなかった点をメモしておくと、あとで復習しやすくなります。
例えば、板書を写すのが難しい場合でも、先生が強調したポイントや、後で確認したい部分だけでも書き留めると良いでしょう。
授業が終わった後に見直すことで、自分の疑問を解消しやすくなります。
一度にたくさんのことをしようとしない
授業についていこうと無理に頑張りすぎると、逆に疲れてしまいます。
一度にたくさんのことをしようとせず、授業の内容を少しずつ理解することを意識しましょう。
例えば、「今日は数学の授業に集中する」「英語の単語をいくつか覚える」といった具合に、科目ごとに取り組む範囲を絞ると負担が減ります。
家庭で復習する習慣をつける
授業内容を定着させるためには、家庭での復習が効果的です。
授業でわからなかった部分を家族と一緒に確認したり、教科書を見返したりすることで、理解が少しずつ深まります。
また、授業での疑問を解消するために、家でリラックスした状態で復習すると、理解が進みやすくなります。
小さな成功体験を大切にする
授業でできたことを記録し、小さな成功体験を積み重ねることも大切です。
例えば、「今日は先生の話を最後まで聞けた」「板書を全部写せた」など、小さな達成をメモしておくと、自分の成長を実感できます。
成功体験が積み重なると、「授業も少しずつわかるようになってきた」と前向きな気持ちが育まれます。
無理なく授業についていくためには、まず小さなステップを少しずつ積み重ねていくことが重要です。
自分に合った目標を立てて、無理のないペースで授業に取り組んでいくことで、少しずつ自信を持って学べるようになります。
まとめ
授業についていくのが難しいと感じる発達障害のある子どもたちにとって、学びに向き合うことは大きな挑戦かもしれません。
しかし、無理をせず、自分のペースに合わせて少しずつ進めていくことが大切です。
授業の内容をすべて一度に理解するのではなく、できることから始めて、小さな成功体験を積み重ねることで自信を育んでいきましょう。
また、サポートツールや家庭での工夫を活用することで、授業が少しずつ理解できるようになります。
自分に合った学び方を見つけ、授業内容に触れる時間を増やすことで、「少しわかってきた」という達成感が得られるはずです。
こうした取り組みが授業への前向きな気持ちにつながり、授業についていくための大きな一歩となります。
自分に合った方法で学びを続けていけば、授業も少しずつ楽しめるようになるでしょう。
周りのサポートを上手に活用しながら、自分なりのペースで進んでいくことが、学びの成果につながります。
授業に対して前向きな姿勢を持ち、できることから一歩一歩進めていくことで、充実した学習が期待できます。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。






