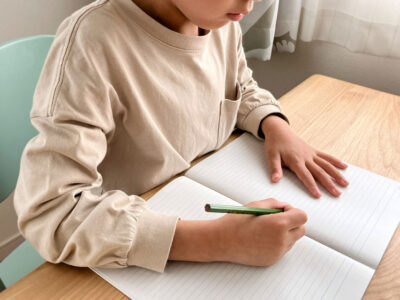感覚過敏・感覚鈍麻のある発達障害の子どもへの対策と効果的な学習法

発達障害を持つ子ども達は、日常生活や学習の際に、さまざまな困難を抱えることが数多くあります。
特に、感覚過敏や感覚鈍麻といった感覚に対する問題を抱える子ども達は、普通の子どもが気にもしないような音や光、触覚の刺激に対して過敏に反応してしまったり、逆に全く反応しなかったりすることがあります。
例えば、教室の蛍光灯の光がまぶしすぎて集中できない、友達との触れ合いが不快であるとか、あるいは逆に周囲の音や触覚刺激に対して反応が鈍く、危険を感じにくいということがあります。
これらの感覚の特性は、学習や社会的な交流に大きな影響を与えてしまいがちです。
感覚過敏の子どもは、些細な刺激に気を取られて集中力を欠いてしまい、学習の進行が妨げられることがあります。
一方、感覚鈍麻の子どもは、刺激に対して適切に反応できず、学習内容の理解や記憶に困難を感じることが少なくありません。
今回の記事では、感覚過敏・感覚鈍麻を持つ発達障害の子ども達が抱える具体的な困難についての理解を深め、それぞれの特性に応じた対策と効果的な学習法について解説していきます。
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達が安心して学び、成長していける環境を整えるためには、どんなことをしていけばいいのか、ぜひ参考にしてくださいね。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
感覚過敏・感覚鈍麻とは?その特徴と発達障害との関係

感覚過敏・感覚鈍麻の定義
感覚過敏とは?
感覚過敏とは、外部からの刺激に対して通常よりも過度に反応してしまう状態を指します。
感覚過敏の子どもは、日常生活で触れる音や光、匂い、触覚などに対して非常に敏感であり、その結果として強い不快感やストレスを感じることがあります。
具体的な例としては、次のような状況が挙げられます。
- 聴覚に対する過敏:
教室内での話し声や廊下を歩く音が非常にうるさく感じられ、集中が妨げられる - 光に対する過敏:
蛍光灯の明かりや太陽光がまぶしすぎて目を開けていられない - 触覚に対する過敏:
特定の衣服の素材やタグが肌に触れるだけで強い不快感を覚える - 匂いに対する過敏:
給食の匂いや他の生徒の体臭が気になり、食事や授業に集中できない
感覚鈍麻とは?
感覚鈍麻とは、外部からの刺激に対して通常よりも反応が鈍く、感覚情報を十分に感じ取れない状態を指します。
そのため、感覚鈍麻の子どもは、重要な感覚情報を見逃したり、危険を察知するのが遅れることがあります。
具体的な例としては、次のような状況が挙げられます。
- 痛みに対する鈍麻:
怪我をしても痛みを感じにくく、怪我の重大さに気づかないことがある - 温度に対する鈍麻:
熱いものや冷たいものに触れても反応が鈍く、やけどや凍傷のリスクがある - 触覚に対する鈍麻:
強い圧力をかけられても気づかず、他人との触れ合いに対する反応が乏しい - 味覚や嗅覚に対する鈍麻:
食べ物の味や匂いに対して反応が薄く、食欲が低下することがある
発達障害との関連性
感覚過敏や感覚鈍麻は、発達障害の一部として時々見られる特徴です。
発達障害には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、限局性学習症(SLD)などがあります。
これらの障害を持つ子ども達は、感覚処理の特性として感覚過敏や感覚鈍麻を示すことが多くあります。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD):
ASDの子ども達は、感覚過敏や感覚鈍麻の症状を示すことが多く、これが日常生活や学習に大きな影響を与えます。
例えば、特定の音や光が強い状態に不安を感じたり、パニックを起こしたりする場合があります。 - 注意欠陥・多動性障害(ADHD):
ADHDの子ども達も、感覚過敏や感覚鈍麻の症状を示すことがあります。
これが集中力や注意力に影響を与え、学習の妨げとなることがあります。 - 限局性学習症(SLD):
SLDの子ども達も、感覚過敏や感覚鈍麻の特徴を持つことがあり、学習の効率や理解度に影響を与えることがあります。
これらの感覚に対する問題は、発達障害を持つ子ども達の学習や社会的な交流に大きな影響を与えるため、適切な理解と支援が必要です。
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達が安心して学び、成長できる環境を整えるためには、これらの特性を理解し、個々の子どもに合わせた対策を講じることが重要です。
感覚過敏・感覚鈍麻を持つ子どもが抱える学習の困難とは?

日常生活と学習環境で起こる問題
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達は、日常生活や学習環境においてさまざまな困難を抱えています。これらの問題は学習効率や社会的な交流に大きな影響を与える恐れがあります。
- 聴覚に対する過敏
教室の雑音や廊下の足音、鉛筆で書く音などが過度にうるさく感じられるため、集中力が途切れやすくなります。
また、他の生徒が話す声が気になり、授業に集中できないことがあります。
- 光に対する過敏
蛍光灯の光がまぶしすぎて、目を開けているのが苦痛だと感じる場合があります。
また、教室内の自然光が強すぎる場合、視覚的な刺激が多すぎて集中力が低下することもあります。
- 触覚に対する過敏
制服や衣服の素材、タグなどが肌に触れると不快で、授業中も気になってしまうことがあります。
また、教室の椅子や机の触感が気になり、座っているのが苦痛に感じる子もいます。
- 匂いに対する過敏
教室内の給食の匂いや他の生徒の体臭が気になり、集中できないことがあります。
さらに、特定の匂いが強い場合、気分が悪くなり授業に参加できないこともあります。
- 温度に対する鈍麻
教室の温度変化に気づきにくく、適切な服装の調整ができないため、快適に過ごせないことがあります。
暑さや寒さに対する感覚が鈍いと、自分が快適な状態でないことに気づきにくくなるため、長時間不快な状態が続くことになります。
例えば、暑い教室で過ごしているときに汗をかいても暑さを感じにくい場合、体が過熱し続けますが、それに適応するための行動(服を脱ぐ、窓を開ける、水分を取るなど)を取らないため、身体的なストレスが蓄積します。
- 痛みに対する鈍麻
転んだり怪我をしたりしても痛みを感じにくく、適切な対応が遅れることがあります。
また、痛みに対する反応が鈍いため、健康管理が難しい状態になります。
感覚過敏・感覚鈍麻を持たない子どもとの違い
感覚過敏・感覚鈍麻を持つ子ども達は、これらの問題により、感覚過敏・感覚鈍麻を持たない子ども達とは異なる学習体験を持つことになります。
下記では、具体的なその違いを紹介していきます。
- 集中力の維持が難しい
感覚過敏の子どもは、常に環境からの刺激に気を取られてしまい、授業内容に集中できない状態になります。
感覚鈍麻の子どもの場合は、授業中の重要な指示や情報を見逃すことがあります。
- 社会的な交流に影響
感覚過敏の症状があると、他の子どもとの触れ合いを苦手とする傾向があり、友達作りが難しい場合があります。
感覚鈍麻の症状の場合は、他の子ども達との遊びや活動に適切に反応できず、コミュニケーションが円滑に進まないことがあります。
- 学習方法の違い
感覚過敏を持つ子ども達は、静かな環境や特定の照明、感覚刺激を減らす工夫が必要なため、個別指導が要求されることがあります。
また、感覚鈍麻を持つ子ども達には、視覚や触覚を使った具体的な学習法が効果的なため、積極的なフィードバックやリマインダーが必要です。
これらの違いを理解し、個々の子どもに合わせた学習環境を整えることが、感覚過敏・感覚鈍麻を持つ子ども達の学習を支援するために重要です。
適切なサポートがあれば、こういった子ども達も他の子ども達と同様に学び、成長していくことができるでしょう。
感覚過敏・感覚鈍麻に対応するための学習環境の整え方
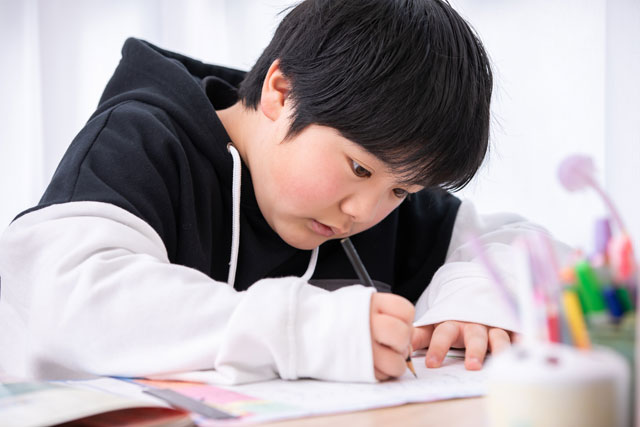
安心できる学習スペースの作り方
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達が安心して学習できる環境を整えることは、学習効率を向上させるために非常に重要です。
下記では、具体的な学習スペースの作り方のポイントを紹介していきます。
- 静かな場所の確保
学習スペースはできるだけ静かな場所に設け、外部の音が入りにくいようにしましょう。
聴覚過敏があれば、耳に耳栓やイヤーマフを使用しても良いでしょう。
- 個別の学習スペース
共有スペースよりも個別の学習スペースを確保することで、他の人の動きや音に気を取られることなく集中できます。
パーティションや間仕切りを使って、視覚的な刺激を減らすことも効果的です。
- 快適な座席と家具
座席や机は、子どもが快適に長時間座っていられるように調整しましょう。
座り心地の良い椅子や適切な高さの机を選び、身体に無理のない姿勢を保てるようにするといいでしょう。
- 温度と換気の管理
学習スペースの温度は適切に調整し、換気を良くすることで、快適な環境を保ちます。
特に感覚鈍麻の子どもに対しては、こまめな温度調整が必要です。
- 感覚刺激を最小限にする工夫
匂いや触覚に対する過敏がある場合は、学習スペースの清潔さを保ち、強い匂いのする物(香水、洗剤など)を避けるようにしましょう。
触覚に対する配慮としては、柔らかい素材のカバーやクッションを使用することも有効です。
照明や音などの環境調整のポイント
感覚過敏や感覚鈍麻に対応するためには、照明や音などの環境調整が重要です。
下記では、具体的な調整ポイントを紹介していきます。
- 照明の調整
照明は自然光に近い柔らかい光を使用し、蛍光灯のようなまぶしい光を避けましょう。
調光可能なライトを使用して、光の強さを調整できるようにするといいでしょう。
また、デスクランプを使用し、必要な場所だけを照らすことで、全体の明るさを抑えることもできます。
- 音の管理
外部からの音を遮断するために、窓やドアに防音材を使用するのも効果的です。
カーペットやカーテンも音を吸収するため、静かな環境を作るのに役立ちます。
また、ホワイトノイズ(テレビの砂嵐の音、ラジオの無信号時の音など)や自然の音(波の音、雨音など)を流すことで、雑音を遮る効果があります。
- 視覚的な刺激の減少
学習スペースの壁には、派手な色や過度な装飾を避け、シンプルで落ち着いたデザインにしましょう。
視覚的な刺激を減らすことで、集中力を高めることができます。
- 触覚への配慮
座席や机の素材が肌に合わない場合は、クッションやカバーを使って快適に過ごせるようにしましょう。
例えば、柔らかい布製のカバーを使うことで、不快感を軽減できる場合があります。
- 匂いの管理
学習スペースには、無香料の洗剤や清掃用具を使用し、強い匂いを避けましょう。
また、空気清浄機を使用して、空気を清潔に保つことも効果的です。これらの工夫を取り入れることで、感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達が安心して集中できる学習環境を作ることができます。
個々の子どもの特性に合わせて調整を行い、最適な学習スペースを作り上げましょう。
感覚過敏・感覚鈍麻の子どもへの効果的な学習法
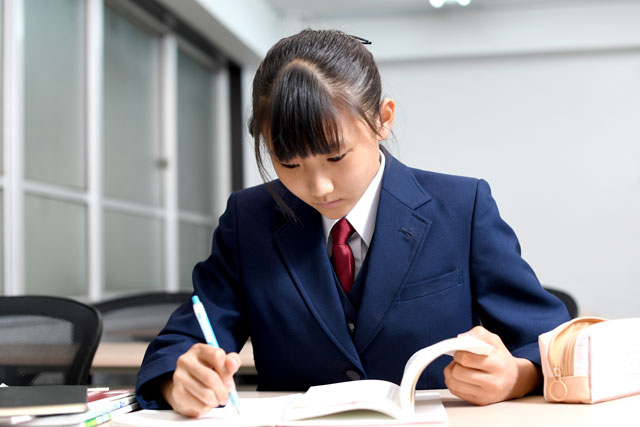
個別指導の重要性
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達は、一般的な学習環境や方法では集中力や学習効率が低下することがあります。
こういった子ども達のための個別指導は、子ども一人ひとりの感覚特性や学習スタイルに合わせた指導が可能であり、下記のようなメリットがあります。
- 個別対応
子どもの特性やニーズに応じた指導ができるため、感覚過敏や感覚鈍麻に対する適切な対応が可能です。
これは、子どもが感じる不快感や困難に対して迅速に対応できるため、学習効率が向上していきます。
- 柔軟な学習のペース
子どもの理解度や集中力に応じて、学習のスピードを調整しましょう。
これにより、無理なく学習を進められるため、感覚過敏や感覚鈍麻に対するストレスを軽減し、学習に対する意欲を保つことができます。
- 安心できる環境
個別指導では、子どもが安心して学習できる環境を整えることが簡単になります。
静かで落ち着いた環境を提供することで、集中力を高めることができます。
また、イヤーマフや調光可能な照明など、感覚特性に合わせたツールの使用がしやすくなります。
視覚・聴覚・触覚を活かした学習方法
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達に対して、視覚・聴覚・触覚を活かした学習方法を取り入れることで、学習の効果を高めることができます。
- 視覚を活かした学習方法
図表、イラスト、動画などの視覚教材を用いることで、視覚的に情報を理解しやすくします。
また、重要なポイントを色分けしたり、ハイライトをつけることで、情報の整理がしやすくなります。
また、単語や概念を単語帳に書いて視覚的に学ぶことで、記憶の定着を図ることができます。
- 聴覚を活かした学習方法
録音された教材やオーディオブックを利用して、聴覚から情報を取り入れてみましょう。
感覚過敏がある場合は、イヤーマフやイヤホンを使用して音量を調整するといいでしょう。
また、音楽やリズムを取り入れた学習法(例:掛け声に合わせて単語を覚える)を活用し、聴覚的に刺激を与えたり、聞いた内容を書き取る練習を行い、聴覚と書く動作を連携させたりして学習するのも効果的です。
- 触覚を活かした学習方法
実際に手を使って学ぶ活動(例:実験、模型作り、ブロックを使った数学学習)を取り入れてみましょう。
また、感覚過敏や感覚鈍麻の調整を目的とした遊び(例:粘土遊び、砂遊び)を通じて、触覚を刺激しながら学んだり、異なる触感の素材を使用した本を用いて、触覚的な刺激を取り入れた読書を行ったりしてもいいでしょう。
これらの学習方法を取り入れることで、感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達がより効果的に学ぶことができ、学習に対する意欲や集中力が向上していきます。
子ども一人ひとりの感覚特性に合わせた工夫を取り入れ、楽しく学べる環境を整えていきましょう。
感覚過敏・感覚鈍麻のある子どもが持つ強みを引き出す方法

強みのある側面を活かす
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達は、その特性に起因する特別な強みを持っていることがあります。
これらの強みを理解し、積極的に活かすことで、子ども達の自己肯定感を高め、学習や生活における成功体験を増やすことができるでしょう。
- 感受性の高さ
感覚過敏の子どもは、細かな違いに気づくことができる場合が多いため、芸術や音楽、クリエイティブな活動で優れた能力を発揮することがあります。
美術や音楽の授業での活動を通じて、その感受性を伸ばす機会を探ってみましょう。
- 集中力と深い洞察力
特定の分野において非常に集中力が高く、深い洞察力を発揮することがあります。
興味のあるテーマについて深く掘り下げる学習活動をサポートするといいでしょう。
また、プロジェクト型学習や調査活動を通じて、自分の興味を追求し、専門性を高める経験をしていくのも効果的です。
- 独創的な思考
感覚鈍麻の子どもは、独自の視点や発想を持っていることが多く、問題解決や創造的な活動で優れたアイデアを出すことがあります。
自由な発想を奨励し、アイデアを形にするプロジェクトや活動をしていくといいでしょう。
- 細部へのこだわり
細かい部分にこだわる性質があるため、精密さが求められる作業や活動で高いパフォーマンスを発揮することがあります。
手作業や工芸、研究活動など、細部に注意を払うことが求められる活動に参加することで、その強みを活かしてみましょう。
特技や興味を伸ばす支援
子ども達の特技や興味を見つけ、それを伸ばすための具体的な支援方法を見つけることで、自己肯定感を高め、子ども達の成長をサポートしていきましょう。
- 特技を見つける機会を与える
多様な活動や経験を通じて、子ども達が自分の特技や興味を発見できるようにしましょう。アート、スポーツ、科学、技術など、様々な分野に触れる機会に触れると才能が開花されるかもしれません。
そのため、クラブ活動や課外活動への参加を促し、興味を持った分野での経験を積むのがおすすめです。
- 興味を深める学習環境を整える
子どもの興味に応じた教材などを提供するようにしましょう。
図書館の利用、インターネットでの調査、専門家との交流などを図っていくといいでしょう。
そのため、自主的な学習プロジェクトをするようにし、興味を持ったテーマについての探究活動をしていくのがおすすめです。
- 専門家との連携
必要に応じて、特定の分野での専門家やメンターと連携し、子どもの成長をサポートしましょう。
例えば、音楽の才能がある子どもは、音楽教師との個別レッスンを受けるといいでしょう。
また、地域のコミュニティやオンラインでの指導を活用して、子どもの興味を深める支援を行いましょう。
- 社会的スキルの育成
感覚過敏や感覚鈍麻がある子ども達にとって、社会的なスキルの育成も重要です。
グループ活動やチームプロジェクトを通じて、コミュニケーション能力や協働スキルを育むといいでしょう。
これらの方法を取り入れることで、感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達が持つ強みを引き出し、自己肯定感を高めながら成長をサポートすることができます。
個々の特性に応じた支援を行い、積極的な学習体験を与えていくことが大切です。
まとめ
感覚過敏や感覚鈍麻を持つ発達障害の子ども達は、学習や日常生活において特有の困難を抱えることが多くあります。
しかし、これらの特性を理解し、適切な環境を整えることで、子ども達の学習効率や生活の質を大幅に向上させることが可能となります。
個別指導や環境調整を通じて、安心して学べるスペースを与えていくことが重要です。
また、視覚、聴覚、触覚を活かした学習方法を取り入れることで、子ども達の強みを引き出し、学習意欲を高めることができます。
特技や興味を伸ばす支援を行うことで、自己肯定感を高め、成功体験を増やすことができます。これにより、子ども達が持つ潜在能力を最大限に引き出すことができます。
適切なサポートを提供することで、感覚過敏や感覚鈍麻を持つ子ども達も、他の子ども達と同様に学び、成長することができます。
私たちの理解と支援が、子ども達の未来を明るくするための鍵となるでしょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。