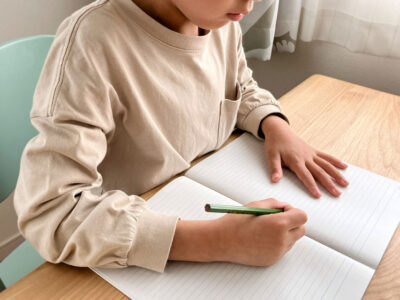場面緘黙症の子どもをサポート!発達障害を持つ子どもの学習法ガイド

「初めて会う人と話をしたり、大勢の人たちの前で話をしたりすると、緊張をしてうまく話ができなくなる」
皆さんもそんな経験があるかもしれませんね。
特に小さな子どもでは、人見知りをしたり、恥ずかしがり屋で人前では話をしたりするのが苦手だという子は大勢います。
小学校に入学したり、公園で初めて会う子どもたちと話をしたりなどの状況で、最初はうまく打ち解けられずにいても、慣れてくると多くの場合はその時のことが噓のように一変して、仲良くおしゃべりをしたり、一緒に遊んだりするようになります。
一方、今回のテーマの「場面緘黙(ばめんかんもく)症」の子どもは、こういった人見知りや恥ずかしがり屋の状況とは違い、家庭では普通に話せるにもかかわらず、1ヶ月以上経っても幼稚園や学校等の特定の場所や状況では全く言葉を発することができくなる症状を持っています。
こうした症状は、日常生活や学習面でも大きな影響を及ぼすことがあります。
今回の記事では、場面緘黙症の理解を深め、発達障害を持つ子どもの学習をサポートするための具体的な方法について解説します。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
場面緘黙症とは?その症状と原因

場面緘黙症は、特定の場面や状況で話すことができなくなる状態を指します。
「緘黙」という言葉は、「緘」(かん)=口を閉ざす、「黙」(もく)=沈黙するという意味があり、まさに特定の状況で言葉を発しない状態を表しています。
この症状を持つ子どもは、家庭や親しい友人の前では普通に話すことができる一方で、学校や公共の場では何をどうしたらいいのか分からないなどして、全く話せなくなります。
場面緘黙症の詳細な症状と原因については、下記の通りです。
症状の特徴
場面緘黙症の主な特徴は、以下の通りです。
特定の場所で話せない
- 家庭や安心できる環境では話せるが、学校や公共の場など特定の場所では沈黙して、その環境に慣れるのに、非常に長い時間がかかる
- 1ヶ月以上にわたって特定の状況で話せない状態が続く
社会的な不安
- 話すことに対する不安から、体が硬直する、視線を合わせない、表情が乏しくなるといった身体的な反応が現れることがある
原因
場面緘黙症は家庭環境に要因があると言われることがありますが、そう考えるのは誤解であると言われています。
場面緘黙症の原因や発症のメカニズムについては、まだ研究の段階で、はっきりとわかってはいませんが、下記の複数の要因が絡み合って発症することが多いようです。
遺伝的要因
家族に不安障害や精神的な問題を抱えている人がいる場合、場面緘黙症の発症リスクが高まることがあります。
環境的要因
環境の変化やストレスの多い状況(例えば、学校への入学や引っ越し)が引き金となることがあります。
心理的要因
社会的な不安や自己評価の低さが影響することも多くあります。
また、過去のトラウマやネガティブな経験も、その一因となりうる場合があります。
発達的要因
子どもによっては、発達障害や言語発達の遅れが関係している場合もあります。
専門家による治療とサポート
場面緘黙症の治療には、専門家による早期発見と適切な支援が重要です。
専門家による治療とサポートには、以下のような方法が効果的です。
心理療法
認知行動療法(CBT)や遊び療法を通じて、不安を軽減し、自己表現を促すようにしましょう。
| ※認知行動療法(CBT)とは 認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)とは、ストレスなどで固くなった考えや行動を柔軟にし、自由に考えたり行動したりするのをサポートする心理療法です。 物事の捉え方(認知)は人によって異なり、この認知の偏りがストレスを引き起こし、行動にも影響を与えます。 例えば、人前で話すときに「みんなが応援してくれている」と思うのと「みんなが私を批判している」と思うのでは、感じるストレスとその後の話し方に違いが生じます。 認知行動療法は、この認知と行動に働きかけて思考のバランスを整え、ストレスを減らすことを目的とし、うつ病、統合失調症、パニック障害、PTSDなど、さまざまな疾患や障害の治療に用いられています。 |
環境の調整
学校や家庭でのサポート体制を整え、子どもが安心して過ごせる環境を作るようにしましょう。
家族のサポート
親や兄弟が理解し、温かく見守ることで、子どもの不安が軽減するようにサポートしていきましょう。
場面緘黙症は子どもの性格や意思に関係なく発症するとされています。
日本場面緘黙研究会は、場面緘黙症の治療について下記のように記しています。
| 場面緘黙は、脳の損傷や先天的異常などの不可逆的・恒久的な器質障害ではなく、社交不安症 (social anxiety disorder) の一つとして考えられる症状である。したがって適切な治療的介入を行えば症状の改善が可能である。逆に、積極的な介入が行われなければ、症状が改善されずに固定化し、成人後に社会的機能に重篤な悪影響を及ぼしかねない。 (場面緘黙の)背景にある「不安」にうまく対応できるスキルを身につけさせることが、場面緘黙の改善に有効であると考えられている。 |
引用: 日本場面緘黙研究会 https://mutism.jp/
治療には、専門家による早期発見と適切な支援が重要となります。
心理療法(CBT)や環境調整、家族のサポートを通じて、子どもが安心して過ごせる環境を整え、周囲の理解と適切なサポートで、大人になる前に症状の改善を目指していくと良いでしょう。
場面緘黙症と発達障害との関係

場面緘黙症の症状がある子どもの中には、発達障害の傾向をあわせもっている子どもがいます。
発達障害には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、限局性学習症(SLD)などが含まれます。これらの障害を持つ子どもは、社会的な不安やコミュニケーションの困難さから、場面緘黙症を併発することがあります。
ただし、話をあまりしないため、発達障害の診断をすることが難しい場合が多くあります。
発達障害の影響
社会的スキルの欠如
発達障害を持つ子どもは、社会的なスキルの発達が遅れることが多く、これが場面緘黙症の発症に影響することがあります。
コミュニケーションの困難さ
言語発達の遅れや言葉の理解に困難があるため、特定の場面で話すことができない場合があります。
支援の一貫性
包括的な支援
発達障害と場面緘黙症の両方に対する包括的な支援が必要です。
専門家、家庭、学校が一体となってサポートすることが重要です。
発達障害を持つ子どもは、社会的な不安やコミュニケーションの困難さから、場面緘黙症を併発することがあるため、専門家、家庭、学校が一体となり、包括的な支援を提供することが不可欠です。
適切なサポートを通じて、子どもたちが安心して学び、成長できる環境を整えていきましょう。
学習面で生じる不都合
場面緘黙症を持つ子どもは、以下のような学習面での不都合に直面することがあります。
口頭発表やクラスディスカッションへの参加
他の子どもたちと同じように口頭での発表やクラスディスカッションに参加できず、授業内容を共有する機会が制限される場合があります。
教師とのコミュニケーション
質問や意見を口頭で表現できないため、教師との直接的なコミュニケーションが困難になることがあります。
グループ活動や協働学習
グループ活動や協働学習の際に、他の子どもたちとのコミュニケーションが取りにくく、協力が必要な場面で孤立することがあります。
友達とのコミュニケーション
友達との日常的な会話や遊びに参加することが難しく、社会的なつながりを築くのが困難になることがあります。
評価やフィードバックの受け取り
教師からの口頭での評価を受け取ることが難しく、自分の学習状況を把握するのが難しくなる場合があります。
学習環境の整え方
場面緘黙症を持つ子どもが安心して学習に取り組める環境を整えるためには、以下のポイントが重要となります。
安全で安心できる学習スペースの提供する
静かで落ち着いた場所を用意し、子どもが安心して集中できる環境を整えるようにしましょう。教室内でも、子どもがリラックスできる席を確保することが大切です。
視覚的支援の活用
視覚的なサポート(図、イラスト、絵カード、スケジュール表など)を活用し、口頭でのコミュニケーションが難しい子どもに対して、理解を助ける手段を提供するようにすると良いでしょう。
書くことやジェスチャーなどを使ったコミュニケーション手段の導入
書くことやジェスチャーなど、話さなくても意見や質問を表現できる方法を積極的に取り入れると良いでしょう。
例えば、ノートやホワイトボードを使って質問や意見を伝える方法などが、その例です。
ただし、子どもたちは学校で特別な支援があることで、他の子どもたちと違う扱いを受けていると感じ、恥ずかしいと感じることがあります。
これが不登校を引き起こす場合もあるため、支援の方法については慎重に配慮することが重要です。
一貫性のあるルーティンの確立
毎日の学習スケジュールを一貫して行い、子どもが安心して学習に取り組めるようにします。予測が可能なスケジュールを立てることは、子どもの不安を軽減するのに役立ちます。
段階的な口頭表現の練習
小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけるようにします。
最初は家庭や個別指導の場で徐々に話す機会を増やし、次第に教室内でも話せるよう支援しましょう。
教員の理解と協力
教師や学校の関係者などと情報の交換を行って場面緘黙症について知識を深めてもらい、適切な対応を取るための指導を行ってもらえるようにすると良いでしょう。
教師は子どもにプレッシャーをかけず、温かく見守る姿勢を持つことが大切になります。
専門家の協力を得る
心理士や言語療法士などの専門家に相談し、個別の支援計画を立てても良いでしょう。
専門家のアドバイスを受けながら、最適なサポートを提供するようにしていきます。
場面緘黙症を持つ子どもに適した学習環境を整えることで、子どもが安心して学習に取り組み、自信を持って成長できるようになります。
学校と家庭が協力して、子どものニーズに応じた支援を行うことが重要です。
場面緘黙症の子どもに適した効果的な学習法

場面緘黙症を持つ子どもは、特定の状況で話すことができないため、学習面でのサポートが重要です。
場面緘黙症の子どもに適した効果的な学習法については、下記の通りです。
小さな成功体験を積み重ねる
目標設定
子どもが達成できる小さな目標を設定しましょう。
例えば、「授業中に一言話す」「一人の友達に質問する」などの具体的な目標を立てると良いでしょう。
段階的な訓練
初めは家庭や個別指導の場で練習し、徐々に学校での実践に移行していきましょう。
成功体験を積み重ねることで自信をつけるように段階的に訓練していきます。
視覚と触覚を使った学習法
図やイラストの活用
絵カード、図表、マインドマップなど、視覚的な教材を使用して学習内容を理解しやすくします。
ハンドサインやジェスチャーの導入
言葉以外のコミュニケーション手段を活用し、子どもが意思を表現できるようにするのも効果的です。
リラックス法の導入
呼吸法
深呼吸やリラックス呼吸を教え、不安を軽減する方法を身につけるようにします。
リラクゼーションテクニック
瞑想や筋弛緩法(きんしかんほう : 筋肉の緊張と緩和を繰り返す方法)を導入し、心身のリラックスを促すと良いでしょう。
多様なコミュニケーション手段の活用
筆談やデジタルツールの活用
ノート、ホワイトボード、タブレットなどを使用して、質問や意見を文字で表現する方法を身につけても良いでしょう。
ジェスチャーや絵を使った表現
ジェスチャーや簡単な絵を使って、言葉以外で意思を伝える方法を身につけるのも、コミュニケーション手段の一つとなります。
学習の一貫性とルーティンの確立
予測可能なスケジュール
毎日の学習スケジュールを一定に保ち、子どもが安心して学習に取り組めるようにしましょう。
また、1日のスケジュールを一定にすることで、不安を軽減し、集中力を高めることができるようになります。
保護者と教師の協力
保護者のサポート
家庭での学習サポートを強化し、学校での学習と連携させます。家庭での学習環境を整え、子どもが安心して学習できるようにします。
教師の理解と協力
担任の先生には、子どもの状況を理解して、適切な対応を取ってもらえるよう協力を依頼しましょう。
例えば「授業中に直接質問するのを避け、代わりに筆談を許可してもらう」などの配慮を求めても良いでしょう。
個別指導や少人数指導の導入
個別指導
家庭教師などを活用して、子どもがリラックスして学習できるようにします。
個別指導では、子どものペースに合わせた指導が可能となります。
少人数クラス
少人数クラスでの学習を推奨し、子どもが安心して参加できる学習環境を作ると良いでしょう。
場面緘黙症の子どもに適した学習法を導入することで、子どもが安心して学び、自信を持って成長できるようになります。
学校と家庭が協力して、子どものニーズに応じた支援を行っていきましょう。
場面緘黙症を持つ子どものためのオンライン家庭教師活用法

個別指導の利点を最大限に活用
個別のペースでの学習
オンライン家庭教師との学習は、子どもの学習ペースや理解度に合わせたカリキュラムを作成し、無理のない範囲で進めることが可能となります。これにより、子どもが安心して学習に取り組むことができるようになることでしょう。
カスタマイズされた指導
オンライン家庭教師の授業では、子どもの興味や関心に基づいて、家庭教師が作成した個別の教材や方法を取り入れ、学習を楽しいものにしていくことが可能です。
安全で安心できる環境の提供
リラックスした学習スペースの確保
自宅での学習という利点を活かし、オンライン環境でも子どもが安心して集中できるように、静かで落ち着いた学習環境を整えられるようにすることが可能です。
家庭教師が、自宅の学習スペースを最適化するアドバイスをすることもできるようになります。
多様なコミュニケーション手段の導入
デジタルツールの活用
デジタルホワイトボードなどを使って、子どもが言葉を使わずに質問や意見を表現できる方法を提供することが可能となります。
これにより、子どもの自己表現の機会が増えることでしょう。
ジェスチャーや絵を使った表現
オンラインツールを活用して、子どもが言葉以外で意思を伝える方法を使用することが可能です。
例えば、デジタルペンを使って絵を描いたり、ジェスチャーをカメラ越しに示したりができるようになります。
同一教師による一貫したサポートとフィードバック
継続的なフィードバック
学習の進捗や達成度について、学年が変わったとしても、同一の家庭教師から子どもと保護者に対して継続的にフィードバックを行うことが可能です。
これにより、子どもの努力が認められ、自信を育てるようになります。
柔軟な対応
家庭教師は、子どもの状態に応じて学習計画や指導方法を柔軟に調整することが可能です。
段階的な口頭表現の練習
段階的な成功体験の提供
初めは家庭教師とのオンライン個別指導で、少しずつ話す練習を始めると良いでしょう。
成功体験を積み重ねることで、自信を持って教室内でも話せるようにサポートしていきます。
社会的スキルの向上
友達とのコミュニケーション練習
オンラインツールを活用して、家庭教師と一緒に友達とのコミュニケーションの取り方を練習することも可能です。
例えば、ロールプレイングを通じて、実際の会話のシチュエーションを練習していくと良いでしょう。
オンライン家庭教師のサポートを得ることは、場面緘黙症を持つ子どもが安心して学習し、成長するための環境の提供に繋がっていきます。
家庭教師が家庭と連携し、子どものニーズに応じたきめ細やかな支援を行うことで、子どもが健やかに成長することをサポートできるようになるでしょう。
まとめ
場面緘黙症の子どもたちに対するサポートは、多方面からの一貫したアプローチが必要です。
この記事では、場面緘黙症の基本的な理解から、発達障害との関係、効果的な学習法、そして具体的な支援方法について詳しく解説しました。
場面緘黙症は、特定の場面や状況で話すことができなくなる状態を指し、子どもの性格や意思とは無関係に発症します。
家庭や親しい友人の前では普通に話すことができても、学校や公共の場では全く話せなくなり、日常生活や学習面に大きな影響を及ぼします。
早期発見と適切な支援が重要であり、認知行動療法(CBT)や環境調整、家族のサポートを通じて、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが求められます。
また、場面緘黙症と発達障害は関連することがあり、発達障害を持つ子どもは、社会的な不安やコミュニケーションの困難さから場面緘黙症を併発することがあります。
そのため、専門家、家庭、学校が一体となった包括的な支援が不可欠です。
学習環境の整え方としては、安全で安心できる学習スペースの提供、視覚的支援の活用、書くことやジェスチャーを使ったコミュニケーション手段の導入、一貫性のあるルーティンの確立、段階的な口頭表現の練習、教員の理解と協力、専門家の協力を得ることが挙げられます。ただし、特別な支援が恥ずかしいと感じる子どもたちへの配慮も重要であり、不登校を引き起こさないよう慎重に進める必要があります。
さらに、オンライン家庭教師の活用も効果的です。
個別指導の利点を最大限に活用し、リラックスした学習スペースの提供、多様なコミュニケーション手段の導入、継続的なフィードバックと柔軟な対応、段階的な口頭表現の練習、社会的スキルの向上などがオンラインでも実現可能です。
家庭教師が家庭と連携し、子どものニーズに応じたきめ細やかな支援を行うことで、子どもが健やかに成長する環境を提供することができます。
これらのサポートを通じて、場面緘黙症を持つ子どもたちが安心して学び、自信を持って成長できるよう、学校と家庭が協力して支援していくことが重要となるでしょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。