家庭教師による発達障害のある子どもへの学習支援:実践的サポートとテクニック

不登校を経験している発達障害の生徒や、グレーゾーンと呼ばれる発達障害の症状の傾向はあるものの診断の基準は満たさず確定診断にはいたっていないような生徒たちへの学習支援には、その生徒たちの個性や特性を活かしながら、小学生、中学生、高校生など幅広い子どもたちの学習経験を豊かにするような取り組みが重要です。
発達障害には「ASD(自閉症スペクトラム障害)」「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」「LD(学習障害)」などの種類がありますが、そういった子どもたちが学習にスムーズに取り組むためには、子どもたちが直面する学習上の困難を理解し、それらに対応するための実践的なサポートが必要です。
こういった子どもたちのサポートには「視覚支援ツールの使用」「日常ルーティンの確立」「注意力を向上させるための環境の調整」「学習内容を細分化してスモールステップで学習をする取り組み」などが有効とされています。
この記事では、それぞれの発達障害の特徴を理解し、個々の特性に応じた具体的な学習方法、そして、家庭教師を利用した場合の最適なサポート方法やそのテクニックなどを解説します。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
発達障害の各特性とは?
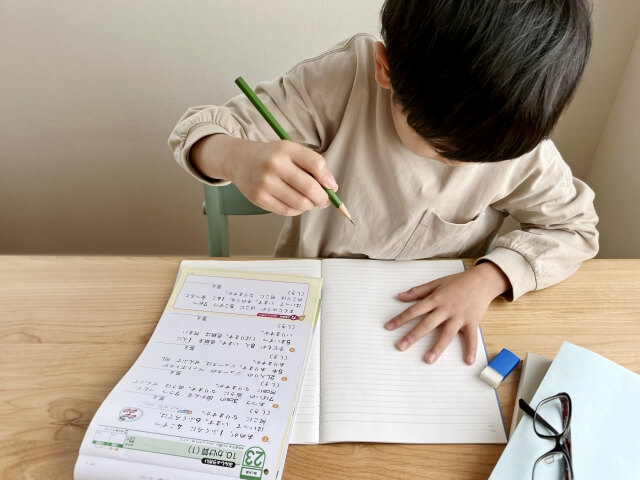
発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
引用 : 文部科学省 5.発達障害について https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu.htm
発達障害は大きく分けて「ASD(自閉症スペクトラム障害)」「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」「LD(学習障害)」などの種類があります。
発達障害にはそれぞれに固有の特徴があり、これらの特徴が原因で子どもたちの学習や日常生活にさまざまな影響を及ぼします。
発達障害の種類とそれぞれの特徴
| 障害の種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| ASD (自閉症スペクトラム障害) | ・社会的コミュニケーションが困難 ・特定の物事に強いこだわりを持っている ・常同行動(同じことを繰り返す行動)をとる ・感覚過敏や知覚過敏などがある子もいる |
| ADHD (注意欠陥・多動性障害) | ・注意力の不足 ・衝動的な行動をとる ・過度な活動(多動性)をする |
| LD (学習障害) | ・読み書きが苦手(ディスレクシア) ・計算が苦手(ディスカルキュリア) ・言語の理解が困難(ディスグラフィア) |
ASD(自閉症スペクトラム障害)の特徴
ASD(自閉症スペクトラム障害)の子どもたちには、下記の特徴があります。
【社会的コミュニケーションが困難】
自閉症スペクトラム障害を持つ子どもたちは、しばしば社会的なやり取りを理解したり、それに対して適切に反応したりすることが困難だと感じています。
こういった困難さの中には、他人の感情を読み取る能力が不足したり、言葉以外でのコミュニケーション(目の接触、身振り手振りなど)の解釈が難しかったり、社会的な状況での適切な振る舞いができなかったりすることが含まれます。
<具体的な行動例>
- 他の子どもたちと目を合わせることを避ける
- 他人の感情や表情を読み取るのが難しいため、相手の感情に対する反応が不適切になることがある
- 会話に参加するのが難しく、一方的に会話をする傾向がある
【特定の物事に強いこだわりを持っている】
自閉症スペクトラム障害を持つ子どもたちは、特定の事に関する興味や活動に対して極端なこだわりを示すことがあります。
これらのこだわりの範囲は極端に集中しているものの、その集中した範囲は狭く、何か変化があるとそれに対して顕著な抵抗を伴う子が多くいます。
<具体的な行動例>
- 「毎日同じ服を着たがる」「同じ食べ物しか食べない」「同じ道順で学校に行く」など、これらを強く要求する
- 特定の内容や趣味に異常なほどの関心を示し、それ以外の話題には興味を示さない
例 : 電車に関して非常に強い関心を持つ子が、電車の種類、時刻表、路線図など、電車に関するあらゆる詳細を深く掘り下げて学びたがるが、こういった関心は他のことにいくことはなく、電車以外には興味を示さない
【常同行動(同じことを繰り返す行動)をとる】
自閉症スペクトラム障害のある子どもたちは、同じ言葉やフレーズを繰り返したり、特定の動作を繰り返したりなど、反復的な行動やルーティンを持つことが多くあります。
これらの行動をとることで、子どもたちは安心感を感じるようになります。
<具体的な行動例>
- 手を振る、体を揺らす、物を回転させるといった動作を繰り返し行う
- 他人が話した特定の言葉やフレーズ、音を繰り返し発する(エコラリア)
【感覚過敏や知覚過敏などがある】
自閉症スペクトラム障害のある子どもたちは、感覚情報(音、光、触覚、味、におい)に敏感に反応し、通常とは異なる方法で対処することがあります。
これには、一般的な環境の刺激に対する過敏反応が含まれ、中には感覚過敏とは逆に感覚情報に対する鈍感さ(感覚鈍麻)を持つ子もいます。
<具体的な行動例>
- 服のタグや粗い布地に対して極端な不快感を示す
- 予期せぬ音(掃除機の音、電話のベルなど)に強く反応し、耳を塞ぐなどして反応する
- 光が強い場所や人が多い環境を避ける、あるいは逆に特定の光や物に特有の興味を示す
以上が、自閉症スペクトラム障害のある子どもたちによく見られる特徴と具体的な行動例です。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の特徴
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもたちには、下記の特徴があります。
【注意力の不足】
注意欠陥・多動性障害を持つ子どもたちは、長時間にわたって集中力を持続させ、常に物事に注意をはらうことに苦労します。
これは学校の授業や宿題、日常生活でやるべきことなど、さまざまな状況で見られます。
<具体的な行動例>
- 授業中に簡単に気が散り、先生の説明を聞き逃すことが多い
- 宿題ややるべきことに対して始めるのが難しく、一度始めてもすぐに別のことに注意が移る
- 指示を聞いているように見えても、何をすべきかを忘れることがしばしばある
【衝動的な行動をとる】
衝動的な行動を抑えるのが難しいために、注意欠陥・多動性障害の子どもたちは考える前に行動することがあります。
これにより、危険な状況に身を置いたり、社会的に不適切な振る舞いをしたりすることがあります。
<具体的な行動例>
- 順番を待つことができず、授業中や遊びの中で割り込みをすることがある
- 考える前に答えを叫んだり、物事を始めたりする
- 危険なことに気づかず、安全に対する配慮が欠けた行動をとることがある
【過度な活動(多動性)をする】
注意欠陥・多動性障害を持つ子どもたちは、通常、周囲が抑えるのが困難なほど通常よりも高いエネルギーレベルを持っており、じっとしていることが難しい状態です。
子どもたちは常に動いている必要があると感じ、座っている時でも足を動かしたり、手をいじったりすることが多くなります。
<具体的な行動例>
- 座っている時も足を動かし続ける
- いすを揺らすなどじっとしていられない
- クラスや家で走り回る
- 授業中や集会など、予期しないタイミングで立ち上がる
- 遊びや活動が一つに定まらず、すぐに他の活動へと移る
以上が、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもたちによく見られる特徴と具体的な行動例です。
LD(学習障害)の特徴
LD(学習障害)を持つ子どもたちには、下記の特徴があります。
【読み書きが苦手(ディスレクシア)】
ディスレクシアを持つ子どもたちは、文字を見てその音を想像すること、または単語が何を意味しているのかを理解することが難しい状態です。
このため、読む速度が遅れたり、読んだ内容を理解したりすることが難しくなってしまいます。
書く際にも、文字の並びや文法の誤りが頻繁に発生し、文章構成が苦手であることが一般的です。
<具体的な行動例>
- 簡単な単語の文字の並び方を繰り返し間違える
- 読む速度が同年齢の子どもたちに比べて顕著に遅い
- 文章を読んだ後の理解が低く、要約や質問への答えが難しい
- 文章や単語の順番を頻繁に間違える
- 他の子どもたちが簡単に読める文を何度も読み直す必要がある
- 書く際に単語を正しく組み立てることができず、文中で単語を省略してしまう
- テキストに「猫」と書かれている場合でも「犬」と読んでしまうなど、文章を読み上げる際に単語を置き換えたりする
【計算が苦手(ディスカルキュリア)】
ディスカルキュリアを持つ子どもたちは、算数の基本的な概念や手順を理解するのが難しい状態です。
これは、より複雑な算数の問題だけでなく、単純な足し算や引き算を解くことにも影響します。
そのため、ディスカルキュリアの子どもたちは、数字や計算式の記憶、数学的な言語の理解に困難が生じてしまいます。
<具体的な行動例>
- 基本的な算数の問題を解くのに通常よりも長い時間がかかる
- 数字や算数で使用する記号を頻繁に間違える
- 日常生活での時間管理やお金の計算が難しい
- 年齢に適した数学的な概念を理解するのに苦労する
- 単純な算数の問題でも、指を使って数を数え直す
- 年齢に合った算数のゲームや活動についていけない
- 図表やグラフを読み解くのが特に難しく、場所や形、方向といった空間に関する理解が苦手
【言語の理解が困難(ディスグラフィア)】
ディスグラフィアの子どもたちは、口頭での指示の理解や複雑な言葉で構成された会話の解釈に苦労をします。
書くことが困難で、特にアイデアを論理的に表現することや、字を書くスキルが一般の子どもたちより低下しています。
<具体的な行動例>
- 口頭での指示を理解し実行するのが難しい
- 長い文を書くときに、文法の誤りが多く、思考を論理的に整理するのが困難
- 口頭での表現がぎこちなく、適切な単語を見つけるのに苦労する
- 学校でのレポートや作文が他の子どもたちよりもはるかに短い、または文章の構成が乏しい
- 文章や単語の間隔が不規則で、一行に収めて文を書くのが難しい
- 話すときにも適切な単語を見つけるのが難しく、話が飛躍してつながりにくい
- 口頭での説明は理解できるが、それを書き留めることが非常に難しい
以上が、LD(学習障害)の子どもたちによく見られる特徴と具体的な行動例です。
ここまで、さまざまな発達障害の特性や具体的な行動例を紹介してきましたが、重要なことは、これらの特性がすべての子どもたちに等しく当てはまるわけではないという点です。
発達障害は個人によって影響の程度や症状のあらわれ方が異なります。
一人ひとりが独自の強みを持っており、同じ診断名であっても、個々の行動や必要とするサポートはそれぞれ違います。
そのため、発達障害のある子ども一人ひとりのニーズを理解し、個々の状況に応じた支援をすることが大切です。
発達障害の各特性に応じた勉強方法とは?

発達障害を持つ子どもたちがぶつかる「学習の壁」になるものは、一人ひとり異なります。そのため、効果的な学習方法も個々のニーズに合わせてカスタマイズする必要があります。
ここでは、ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)の特徴を持つ子どもたちには、オンライン教材の利用を含め、どんな勉強法が合っているのかを紹介します。
ASD(自閉症スペクトラム障害)
自閉症スペクトラム障害のある子どもたちには、視覚的なサポートと形式化された内容で学習する環境を作って学習をすることが有効です。
具体的に書かれた図表やイラストを使って教材を説明したり、日々のルーティンや、やるべき内容が書かれた明確なスケジュールを提供したりすることで学習効果を高めます。
また、子どもたちが持つ特定の興味を学習活動に取り入れることで、モチベーションを高めることができます。
<具体的な勉強法の例>
視覚で理解できるような工夫
- 教材や指示を視覚的に分かるように提示する
例 : 図や写真、色分けされたスケジュールやチェックリストを活用する - 視覚的に識別しやすい色付き付箋を活用して、次に何をすべきかを示す
子どもの興味に基づいた学習
- 子どもの興味や好みを学習に取り入れる
例 : 恐竜が好きな子には、恐竜をテーマにした教材や問題集を使用する
ルーティン化された学習環境の整備
- 学習スペースを整理し、必要な学習教材や文具を手の届く場所に置く
- 日々の学習活動のルーティンを確立し、次に何をすべきかがすぐに分かるような環境を作る
ADHD(注意欠陥・多動性障害)
ADHDの子どもたちには、短い学習時間の設定と体の動きを伴うような活動的な学習が適しています。
例えば、授業の中で頻繁に休憩をするようにしたり、歩いたり運動をしたりなど、物理的な活動を組み合わせることで、学習効果が最大限に引き出されます。
また、はっきりとわかるような明確な指示や目標を設けることで、集中力を維持し、学習の目標に向かって前向きになることができます。
<具体的な勉強法の例>
短い学習時間の設定
- 学習時間を短く区切り、5分間集中して学習した後に短い休憩を設ける
- タイマーを使い、勉強と休憩の時間を明確にする。
身体活動を取り入れた学習
- ジャンプをしながら算数の問題を解いて答える
- 歩きながら暗記をする
- ジョギングやスクワットなど、体力を使うような活動を行って注意力を高める
- 学習の内容をリズムよく読み上げ、手拍子や足踏みをしながら拍子を取る
- 物語を読むときは、そこで出てくる行動や動物などの真似をしながら読み進める
目標の設定
- 完了した項目ごとにポイントやスタンプを与えるなど、一定数たまったら何かの報酬が提供されるような仕組みを作る
- 小さな目標を達成するごとに、すぐに肯定的なフィードバックを行う
読み書きが苦手(ディスレクシア)
ディスレクシアは、文字や単語の認識、読み書きのプロセスに困難が生じる学習障害です。
ディスレクシアは、文字を音に変換する能力や、その逆のプロセスが脳内でスムーズに行われないため、読む速度が遅くなったり、正確な読み書きが困難になったりすることがあります。
こういった読み書きが苦手な子どもたちへの効果的な学習支援は、文字や単語を視覚的に識別するための方法や、スマホやタブレットなどの音節や音声の識別を強化できるような手段を用いるといいでしょう。
<具体的な勉強法の例>
音節分け練習
- 単語を音節ごとに分けて読む練習をする
例 : 「さくらんぼ」を「さ・く・ら・ん・ぼ」と区切って読む - カードやビジュアル素材を使って、音節を分けて学ぶ
ひらがなやカタカナなどの文字練習
- ひらがなやカタカナなどの文字を大きく書く練習をし、文字の形を体で覚える
- ひらがなやカタカナの文字を使ったカードゲームやビンゴゲームを行う
計算が苦手(ディスカルキュリア)
ディスカルキュリアは、数学的概念や計算に関する学習障害です。
この障害を持つ子どもたちは、お金の管理や時間の把握が難しいなど、日常生活での基本的な数の概念、計算スキル、数学的な言語の理解に困難が生じています。
ディスカルキュリアの子どもたちへの学習支援方法には、具体的な教材を用いた数学の概念の教育や、問題解決のステップを視覚的に示すことで効果があらわれるでしょう。
<具体的な勉強法の例>
身近な物を使った算数の練習
- 算数の問題を解く際に、硬貨、ブロック、カードなど、物を使って数を数える
- 日常生活の中で算数に繋がることを見つけ、実用的な問題を解いて練習する
例 : 買い物をしてお釣りを計算する
ビジュアルサポートの活用
- 図や表を使って、算数の概念を視覚的に理解する
- 算数の問題を解くステップを図示化し、それに従って問題を解いていく
言語の理解が困難(ディスグラフィア)
ディスグラフィアは、書く能力に困難が生じる学習障害です。
ディスグラフィアの症状には、手で文字を書く、文法や文章の構成、意思疎通が可能なコミュニケーション能力などの問題が含まれています。
ディスグラフィアの子どもたちは、書くことの物理的な行動だけでなく、自分が考えたアイデアを明確に伝えるのに苦労することがあります。
適切な学習支援には、書くスキルを上げるための練習、自分の考えをあらわすことができるようなサポート、特性に合わせた筆記のための道具の準備が必要です。
<具体的な勉強法の例>
書く練習のための工夫
- 書く時の姿勢やペンの持ち方を確認し、正しい方法で書けるよう指導する
- 短い文を書いてはその都度どのように改善すればいいかフィードバックをし、徐々に文を長くする練習をする
図や絵を使った表現
- 話したい内容を図や絵で表現するように促し、言葉にするのが苦手な子どもでも自分の考えが伝えやすくなるような環境を作る
- ストーリーを絵や写真で順番に並べ、それを基に文章を作る練習をする
以上が、ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)の特徴を持つ子どもたちの、各特性に応じた勉強方法の紹介です。
以上のとおり、各特性を持つ子どもたちに効果的な勉強方法はそれぞれ違います。
視覚的なサポートで学習効果が高まる子もいれば、体を動かすことで勉強がはかどる子もいます。
各特性の症状に合わせながら柔軟に勉強方法を変更することで、子どもたちが自分の強みを活かすことができ、学習の壁を乗り越える手段となることでしょう。
家庭教師ができる発達障害のある子どもへのサポート方法

集団で授業を行う学校や塾とは違い、家庭教師は発達障害を持つ子どもたちの特性をより深く理解することができます。
それにより、発達障害のある子どもの家庭学習で効果的な学習方法が実践され、それを中心に学習を進めることが可能です。
ここでは、家庭教師がどのようにして子どもたち一人ひとりに対応するのか、その具体的な個別指導の方法を紹介します。
個々の子どものニーズを理解する
発達障害のある子どもたちは、その特性や必要とするサポートが大きく異なります。
そのため家庭教師は、まずは子どもの状況を正確に把握し、その子に合った学習スタイルや興味のある関心事、強みや弱みを理解することから始めます。
家庭教師は、親や学校の教師、必要であれば専門家との連携を図り、一貫したサポート体制を築くことも大切にします。
子どもの行動や反応を観察する
家庭教師は日々の指導を通じて、子どもの行動や反応を注意深く観察していきます。
これにより、子どもがどのような時に困難を感じ、どのようなサポートが効果的かを理解することができます。
家庭教師と子どもとの信頼関係の構築
家庭教師と子どもとの間に信頼関係を築くことは、効果的な学習の基盤となります。
子どもが安心して自分の考えや困りごとを話せるように、家庭教師は積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築く環境を整えていきます。
効果的な学習環境の整備
学習環境は、子どもたちの学習効率に大きく影響します。
特に発達障害のある子どもたちにとって、適切な学習環境はとても重要です。
家庭教師は、子どもの特性に合った学習環境を整備し、必要に応じて視覚支援ツールや学習補助道具を使用して学習効果を高めるようにします。
学習のルーティンを確立する
家庭教師は、定期的に次に何をすればいいのかが分かるようなスケジュールを作成し、子どもの次の行動を明確にします。
これにより、子どもは安心感を持ち、学習に集中しやすくなります。
学習ツールの活用
視覚的なツールや具体的な教材を使用することで、抽象的な概念を理解しやすくします。
また、視覚効果が得られるようなデジタルツールやアプリを利用して、子どもたちが楽しいと感じるような学習方法を提供します。
個別化された学習方法の適用
一人ひとりの子どもに合わせた学習方法の提供は、家庭教師ができる最も重要な支援の一つです。
家庭教師は、それぞれの子どもの発達障害の種類、興味、学習スタイルに基づいて、個別の指導計画を立てていきます。
これにより、適切な学習内容の提供、指導方法の柔軟な変更、使用する教材の選定など、それぞれの子どもたちに合った学習方法が確立できるようになります。
学習内容の分割とスモールステップ
複雑な項目をより小さなステップに分けることで、子どもたちは一つ一つの目標を明確にし、達成感を感じやすくなります。
これは、特にADHD(注意欠陥・多動性障害)やLD(学習障害)などの子どもたちに効果的です。
学習スタイルに合わせた指導
家庭教師は、視覚的な教材での効果を期待する子どもたちには図表やイラストを、聴覚的な教材での効果を期待する子どもたちには音声資料や話し合いを取り入れるなど、それぞれの子どもの学習スタイルに適した指導方法で学習を進めていきます。
ポジティブなフィードバックの強化
子どもが小さな目標でもそれが達成できた場合には、積極的に褒めて前向きなフィードバックをするようにします。
これにより、子どもが自分の力を信じる感覚が高まり、モチベーションの向上に繋がります。
これは特に、自信を失いがちな高校生や、学校の授業についていけない子どもたちに有効な方法です。
家庭との連携強化
家庭教師は、子どもの学習を家庭内で支援するために、時には無料の相談なども引き受けながら、親御さんとの密接な連携を保つようにしていきます。
それにより、子どもたちの親に対して家庭でできるサポートの方法を提案し、子どもの学習や行動に関する情報を定期的に共有することが可能です。
定期的な進捗報告とコミュニケーション
家庭教師は、子どもの学習進捗や行動の変化について、定期的に親御さんに報告し、家庭での支援が学習成果にどう反映されているかを報告するようにします。
親への具体的なアドバイス提供
子どもの特性やニーズに合わせて、家庭での適切なサポート方法や、日常生活での対応策を親御さんにアドバイスします。
これには、例えば、家庭でのルーティンの作り方、視覚支援ツールの利用方法、目標達成後の報酬の設定の仕方などがあり、親の役割としてできるサポートの方法をアドバイスしてくれます。
以上が、家庭教師ができる発達障害のある子どもへのサポート方法です。
このように、家庭教師は発達障害のある子どもたちへ、それぞれの特性に合わせた教育支援を実施し、子どもたちが学習において最大限の成果を上げられるようにサポートすることが可能です。
まとめ
この記事では、 発達障害の各特性を理解し、それぞれの特性にあった勉強法や家庭教師を依頼した場合の具体的なサポート方法を解説しました。
家庭教師は子どもたちの特性を深く理解し、効果的な学習環境の整備と、個々の特性に応じた指導を通じて、子どもたちの能力と可能性を最大限に引き出すことができます。
また、家庭教師と保護者との密接な連携とコミュニケーションは、子どもの学習過程において極めて重要です。
家庭教師はまた、それぞれの子どもの個性を尊重し、学習の遅れをカバーするための具体的な対策を講じることが求められます。
多くの保護者は、このようなサポートに関する情報を探しており、その悩みに対応するための家庭教師からの具体的な資料や体験談が非常に役立ちます。
最終的には、発達障害がある子どもたちやグレーゾーンと呼ばれる子どもたちが、家庭教師と共に自分に合った勉強法で学習することにより、学習の壁を克服し、より積極的に学習に取り組めるようになることが目指されます。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。




