発達障害とワーキングメモリの関係性とは? 学習への影響と改善方法を解説

発達障害を持つ子ども達にとって、学習面での課題の一つが「ワーキングメモリ」の問題です。
ワーキングメモリとは、情報を一時的に保持し、必要に応じて操作する能力のことであり、学習や日常生活において重要な役割を果たします。
しかし、このワーキングメモリが十分に機能しない場合、学習効率が低下したり、記憶や理解に困難を伴ったりすることがあります。
この記事では、発達障害とワーキングメモリの関係性を詳しく解説し、学習に与える影響や改善方法について探っていきます。
また、家庭教師を活用した効果的なサポート方法や家庭でできる工夫についてもご紹介しますので、お子さんの学習支援にぜひお役立てください。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
ワーキングメモリとは?その役割と重要性
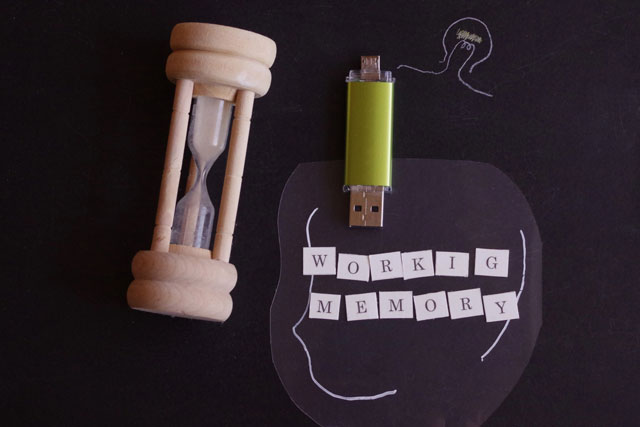
ワーキングメモリは、短期間に情報を保持しながら、それを操作・処理する能力を指します。
これは、私達が日常生活や学習活動をスムーズに行うために不可欠な機能です。
例えば、電話番号を一時的に覚えておく際に、ワーキングメモリが働いています。
また、複雑な計算問題を解くときにも、途中の計算結果を記憶しつつ次の計算を進めるために、ワーキングメモリが必要です。
こういったワーキングメモリは、学習面でも重要な役割を果たします。
例えば、授業中に先生が説明する内容を理解し、ノートに書き取る際に、この機能が働いています。
もしワーキングメモリが十分に機能しないと、新しい情報を短時間で処理し、記憶することが難しくなり、結果的に学習内容の理解や記憶に支障をきたします。
<具体例> 文章題を解くときのワーキングメモリ
具体的な例として、小学生が文章題を解く場面を考えてみましょう。
文章題では、問題文を読み、その内容を頭の中で整理し、必要な情報を保持しつつ計算や解答を導き出すことが求められます。
この一連のプロセスには、ワーキングメモリが欠かせません。
もしワーキングメモリが弱いと、問題文を読み進めるうちに前半の内容を忘れてしまったり、計算の途中で何を求めているのかを忘れてしまったりすることがあります。
ワーキングメモリが十分に機能することで、情報の保持と処理がスムーズに行われ、学習効果が高まります。
そのため、ワーキングメモリの役割を理解し、その能力をサポートすることは、特に発達障害を持つ子ども達の学習支援において重要です。
発達障害とワーキングメモリの関係性
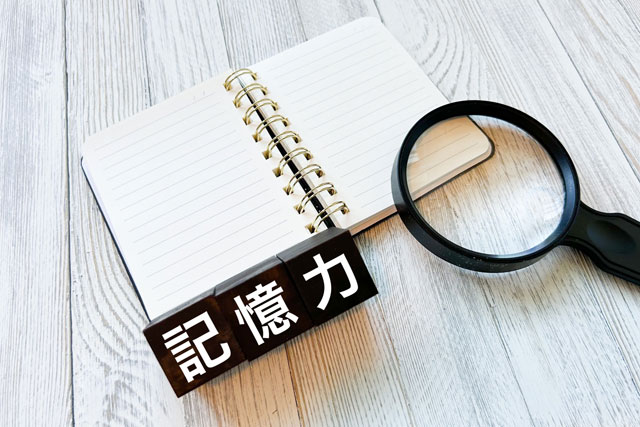
発達障害を持つ子ども達は、ワーキングメモリに困難を抱えることがあります。
これにより、学習や日常生活にさまざまな形で影響が及びます。
ここでは、注意欠如・多動性障害(ADHD)と学習障害(LD)の2つの発達障害がワーキングメモリにどのような影響を与えるのかを見ていきます。
| ※学習障害は、現在、「SLD(限局性学習症)」という名称に変更されていますが、この記事では、一般的に広く使われる「学習障害 (LD) 」という名称で記載しています。 |
発達障害の種類とワーキングメモリの関係
注意欠如・多動性障害(ADHD)
ADHDを持つ子ども達は、ワーキングメモリに課題を抱えることが多く、情報を一時的に保持し、注意を維持することが難しい傾向があります。
これにより、複雑な指示を理解したり、複数のことを同時に処理することが困難になったりする場合があります。
学習障害(LD)
学習障害には、読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカルキュリア)などが含まれます。
これらの障害を持つ子ども達は、特性の影響から特定の学習領域でワーキングメモリが十分に機能しないことがあります。
- 読字障害(ディスレクシア)
読字障害を持つ子ども達は、文字や単語を正確に読み取ることが難しく、これに関連してワーキングメモリが十分に機能しない場合があります。
例えば、文章を読む際に、前に読んだ部分の内容を覚えておくのが難しくなるため、全体の意味を理解するのに苦労することがあります。
- 書字障害(ディスグラフィア)
書字障害を持つ子ども達は、書くこと自体が困難であり、文字や単語を書き出す際に、ワーキングメモリを使って言葉を思い出すことが困難になることがあります。
これにより、正確に書くための手順を保持しつつ、文章を構成することが難しくなることがあります。
- 算数障害(ディスカルキュリア)
算数障害を持つ子ども達は、数や計算に関連する情報を保持して操作することが難しい場合があります。
例えば、数字を覚えながら計算を進める際に、途中のステップを忘れてしまうことがあり、これが算数の課題を解く際の大きな障害となります。
ワーキングメモリと短期記憶・長期記憶の関係
ワーキングメモリは、短期記憶と長期記憶をつなぐ重要な役割を果たします。
短期記憶は、情報を一時的に保持する能力であり、ワーキングメモリはその短期記憶に保存された情報を操作・処理します。
適切に処理された情報は、最終的に長期記憶へと移行し、より長期間にわたって保持されることになります。
しかし、ワーキングメモリがうまく機能しない場合、短期記憶から長期記憶への移行がスムーズに行われず、学習した内容を長期的に記憶することが難しくなります。
学習と日常生活への影響
| 発達障害の種類 | ワーキングメモリへの影響 | 学習への影響 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|---|
| 注意欠如・多動性障害 (ADHD) | 短期的な情報保持が難しく、注意の持続が困難 | 授業中の指示理解や複雑な課題の処理が難しい | 複数の指示を覚えて実行することが困難、計画を立てて行動することが難しい |
| 読字障害 (ディスレクシア) | 文章の内容を保持しながら読むことが難しい | 読解力が低下し、文全体の意味を把握するのが難しい | 文章を理解する際に時間がかかり、日常生活での情報処理が遅れる |
| 書字障害 (ディスグラフィア) | 書く際に言葉や文法の保持が難しい | 正確に文章を書くのが困難で、書くことに対する苦手意識が強まる | メモを取ることや記録を残すことが難しくなる |
| 算数障害 (ディスカルキュリア) | 計算過程を保持しながら進めることが難しい | 複雑な計算を解くのが困難で、数学に対する苦手意識が強まる | お金の計算や時間の管理が難しくなる |
ワーキングメモリがうまく機能しないと、学習や日常生活で以下のような具体的な課題が生じることがあります。
記憶の保持が難しい
例えば、授業中に先生が複数の指示を与える場面を考えてみましょう。
先生が「教科書を開いて、ページを確認し、その後ノートに例題を書いて解いてください」と指示した場合、ワーキングメモリが弱い子どもは、最初の指示を実行している間に次の指示を忘れてしまうことがあります。
これにより、指示に従って行動することが難しくなり、授業についていけないことがあります。
忘れ物が多くなる
ワーキングメモリが低下していると、学校や日常生活で必要なものを覚えておくことが難しくなり、忘れ物が増える傾向があります。
例えば、学校に必要な教科書やノート、筆記用具を家に置き忘れたり、逆に学校に置きっぱなしにしてしまったりすることが多くなります。
このような忘れ物は、学習の進行や日常生活のリズムに影響を与えることがあり、子ども自身も不安やストレスを感じる原因になります。
複雑な課題の処理が困難
書字障害のある子どもが、文章を書く際に、正しい綴りや文法を思い出しながら書くことが難しく、文章全体を構成するのが困難になることがあります。
また、算数障害のある子どもは、複数の計算ステップを要する問題を解く際に、途中で何をするべきかを忘れてしまうことがあり、問題を正しく解くことが難しくなります。
注意力の持続が難しい
家庭で宿題をしている際、書字障害を持つ子どもは書くことに集中するのが難しく、他の刺激に気を取られてしまうことがあります。
これにより、宿題に長時間かかってしまうことがあります。
発達障害を持つ子どものサポート
発達障害を持つ子ども達のワーキングメモリをサポートするためには、環境調整や具体的な支援が重要です。
個別のサポート計画を立て、ワーキングメモリの負担を軽減するための方法を取り入れることで、子ども達の学習や生活の質を向上させることができます。
ワーキングメモリの低下が学習に及ぼす影響とは?

ワーキングメモリは、情報を一時的に保持しながら、それを操作・処理する能力であることを説明しましたが、この機能が低下すると、学習にさまざまな影響を及ぼすことがあります。
ここでは、ワーキングメモリの低下が具体的にどのように学習に影響を与えるのかを見ていきます。
1. 授業内容の理解が難しくなる
ワーキングメモリが低下すると、授業中に先生が説明する内容を保持しながら理解することが難しくなります。
例えば、先生が「まずこの公式を覚えて、それを使って問題を解いてみましょう」と指示した場合、ワーキングメモリが弱い子どもは、公式を覚える段階でつまずき、その後の問題解決にうまくつなげることができません。
結果として、授業内容を十分に理解できず、学習の遅れを感じることがあります。
2. 課題の遂行に時間がかかる
複数のステップを要する課題を解く際に、ワーキングメモリが弱いと、途中で何をするべきかを忘れてしまいがちです。
例えば、数学の問題で「まずこの数字を掛け算して、その結果に10を足し、最後に2で割る」という手順が必要な場合、ワーキングメモリが低下していると、途中で次の手順を忘れてしまい、時間がかかるだけでなく、誤った答えを出してしまうこともあります。
3. 記憶の保持が困難になる
ワーキングメモリが低下すると、新しく学んだ情報を短期間で記憶することが難しくなります。
例えば、英単語や漢字を覚える際、ワーキングメモリが十分に機能していないと、繰り返し練習してもすぐに忘れてしまうことが多くなります。
そのため、復習や再学習が必要になり、学習効率が低下します。
4. 読解力が低下する
ワーキングメモリが弱いと、文章を読みながらその内容を理解することが難しくなります。
例えば、長い文章を読む際に、前半部分の内容を覚えておくことができず、後半の内容と結びつけて理解するのが難しくなります。
その結果、文章全体の意味を正確に把握できず、読解力が低下します。
5. 集中力が続かない
ワーキングメモリの低下は、集中力の持続にも影響を与えます。
例えば、子どもが宿題をしている途中で他のことに気を取られると、再び元の作業に戻って集中するのが難しくなります。
これにより、学習に必要な時間が長くなり、学習そのものに対するモチベーションが低下することもあります。
6. マルチタスクが困難になる
ワーキングメモリが低下していると、同時に複数の作業をこなすのが難しくなります。
例えば、板書を写しながら先生の説明を聞くという場面で、片方に集中するともう片方がおろそかになってしまうことがあります。
これにより、学習の効率が悪くなり、成績にも影響が出る可能性があります。
このように、ワーキングメモリの低下は学習のさまざまな側面に影響を及ぼし、特に記憶力や集中力、課題の遂行能力に問題を引き起こします。
これらの影響を理解し、適切な支援や環境の整備を行うことが、学習をスムーズに進めるために重要です。
発達障害のある子どものワーキングメモリをサポートする効果的な方法
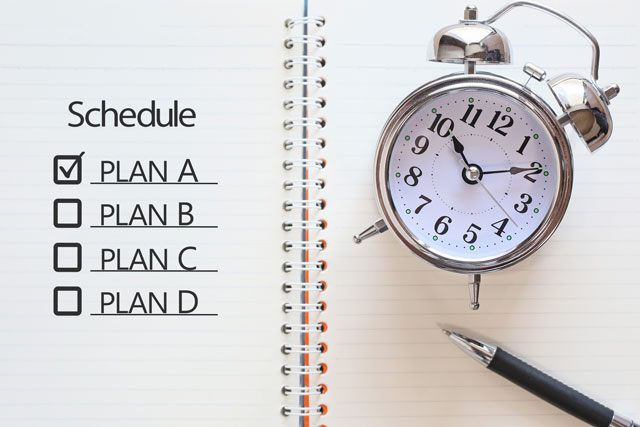
発達障害を持つ子ども達が、学習や日常生活でワーキングメモリに困難を感じる場合、適切な支援を提供することが重要です。
ここでは、発達障害のある子どものワーキングメモリを支えるための具体的な方法をご紹介します。
1. 簡単で具体的な指示を心がける
指示は短く、わかりやすくすることが大切です。
複数の指示を一度に出すのではなく、必要なことを一つ一つ順番に伝えるようにします。
例えば、「教科書を開いて」「次に、ページを確認して」「そして、そのページの問題を解いてみましょう」といった具合に、段階的に説明することで子どもが混乱しにくくなります。
2. メモやチェックリストを活用する
視覚的に確認できるメモやチェックリストを使うことで、子どもが何をすべきかを自分で確認できるようになります。
これにより、ワーキングメモリの負担が軽減され、次にするべきことを忘れにくくなります。例えば、宿題の手順をリストにしておき、終わったらチェックを入れるといった方法が有効です。
3. 繰り返しと反復を行う
新しい情報や技能は、繰り返し学ぶことで定着しやすくなります。
ワーキングメモリが弱い子どもにとって、同じ内容を何度も繰り返すことで、短期記憶が長期記憶に移行しやすくなります。
例えば、毎日少しずつ漢字や計算の練習を行うことで、覚えたことを忘れにくくする効果があります。
4. 視覚や聴覚を活用する
ワーキングメモリを補うために、視覚や聴覚を活用する方法も効果的です。
例えば、重要な情報を図やイラストで示したり、繰り返し音声で聞かせたりすることで、子どもが理解しやすくなります。
また、色分けやマーカーを使って大事な部分を強調するのも有効です。
5. こまめに休憩を取る
長時間集中することが難しい場合、こまめに休憩を取ることで集中力を維持しやすくなります。
「15分勉強したら5分休憩する」といったリズムを作ることで、ワーキングメモリの負担を軽減し、学習効率を高めることができます。
6. 子どもが前向きになれるような感想を伝える
子どもが頑張ったときには、その努力を認めて褒めることが大切です。
子どもを褒めることは、子どもの自己肯定感を高め、やる気を引き出す効果があります。
例えば、「今日はよく集中できたね」「この問題をしっかり解けてすごいね」といった声かけが効果的です。
これらの方法を実践することで、発達障害を持つ子ども達のワーキングメモリをサポートし、学習や日常生活での困難を少しでも軽減できるようになるでしょう。
子ども達が自分のペースで学びやすい環境を整えることが、子ども達の成長につながります。
ワーキングメモリを強化するための家庭でできる工夫

ワーキングメモリを強化することは、学習や日常生活の質を向上させるために非常に重要です。
家庭でできる簡単な工夫を取り入れることで、子ども達のワーキングメモリをサポートし、その機能を向上させることができます。
下記では、家庭で取り組める具体的な方法をいくつか紹介します。
1. 記憶ゲームを取り入れる
家族で一緒に楽しめる記憶ゲームは、ワーキングメモリを鍛えるのに効果的です。
例えば、トランプの神経衰弱や、数秒間絵を見せてからその内容を思い出すゲームなどを行うことで、楽しみながら記憶力を強化できます。
これらのゲームは、記憶する内容を保持し、再現する力を高めるのに役立ちます。
2. 短い指示を繰り返す
日常生活の中で、短い指示を出し、それを子どもに繰り返させることで、ワーキングメモリを鍛えることができます。
例えば、「冷蔵庫から牛乳を取ってきて、それからコップに注いでね」といった簡単な指示を出し、子どもがその内容を覚えて実行できるようにする練習を重ねます。
これにより、情報を保持しながら行動に移す力が養われます。
3. ストーリーを作る
子どもと一緒に、順番に話を考えていく遊びも、ワーキングメモリを強化するのに効果的です。
例えば、親が「ある日、森の中で……」と始めたら、子どもが次に話を続け、再び親がその続きを考えるといった形で、物語を作っていきます。
この遊びは、情報を頭の中で整理し、つなげる力を高める助けとなります。
4. 視覚的な補助を活用する
子どもが何かを覚えるときに、視覚的な補助を取り入れることで、記憶の定着を助けることができます。
例えば、予定表を作って一日のスケジュールを絵や色で表現したり、覚えるべき内容をイラストや図にして見える場所に貼っておいたりすると、視覚的に記憶に残りやすくなります。
5. こまめに復習を行う
一度覚えたことを忘れないようにするためには、こまめに復習を行うことが重要です。
例えば、学校で習った内容を家に帰ってから簡単に復習する習慣をつけることで、学んだことが長期記憶に移行しやすくなります。
毎日少しずつ復習することで、情報を長く保持する力が養われます。
6. 短い休憩を取り入れる
集中しているときでも、適度に休憩を入れることでワーキングメモリの負担を軽減し、効率的に学習を進めることができます。
例えば、15分間勉強したら5分間休憩を取るといったサイクルを取り入れることで、集中力を維持しやすくなります。
これらの家庭での工夫を通じて、子ども達のワーキングメモリを強化し、学習や日常生活でのパフォーマンスを向上させることが可能です。
親子で楽しく取り組みながら、少しずつ記憶力や集中力を高めていきましょう。
家庭教師を活用したワーキングメモリサポート:効果的なアプローチとは?

家庭教師を活用することで、発達障害を持つ子ども達のワーキングメモリを効果的にサポートすることが可能です。
個別に対応できる家庭教師の利点を生かし、子ども一人ひとりのニーズに合わせたアプローチを取ることが大切です。
ここでは、家庭教師が行える効果的なサポート方法について紹介します。
1. 個別の学習計画を立てる
家庭教師は、子どもの学習状況やワーキングメモリの状態を把握し、個別にカスタマイズされた学習計画を立てることができます。
例えば、覚えるべき内容を少しずつ分けて学習し、定期的に復習を取り入れることで、無理なく情報を長期記憶に定着させる手助けができます。
2. ゆっくりとしたペースでの学習
ワーキングメモリに課題がある子どもには、ゆっくりとしたペースでの学習が有効です。
家庭教師が付き添いながら、子どもの理解度に応じて、無理のないペースで授業を進めることで、焦りを感じることなく、じっくりと学習に取り組むことができます。
こうすることで、子どもがリラックスしながら学習できる環境を整えることができます。
3. 視覚的・聴覚的な補助を活用する
家庭教師は、子どもの理解を深めるために、視覚的・聴覚的な補助を取り入れることができます。
例えば、図や表、イラストを用いて説明することで、子どもが情報を視覚的に整理しやすくなります。
また、繰り返し声に出して復唱することで、聴覚を通じて記憶を強化することも効果的です。
4. 具体的なフィードバックを与える
学習の過程で、家庭教師が子どもに対して具体的なフィードバックを与えることは重要です。「この部分はよくできたね」「ここはもう少しゆっくり考えよう」といった具体的なアドバイスを通じて、子どもは自分の強みと弱みを理解し、どこを改善すべきかを明確にできます。
これにより、学習に対する自信を持たせることができます。
5. 記憶を助ける工夫を取り入れる
家庭教師は、子どもが情報を覚えやすくするための工夫を取り入れることができます。
例えば、リズムや語呂合わせを使って暗記をサポートしたり、覚えたことを繰り返し確認するためのゲームを取り入れたりすることが考えられます。
これにより、楽しく学びながら記憶を強化できます。
6. ワーキングメモリを鍛えるトレーニング
家庭教師は、学習の一環としてワーキングメモリを鍛えるトレーニングを組み込むことも可能です。
例えば、短い間に多くの情報を記憶して、その後にそれを再現する練習を行うことで、ワーキングメモリを強化することができます。
これにより、学習だけでなく日常生活においても役立つスキルを身につけることができます。
家庭教師を活用することで、ワーキングメモリに課題を持つ子ども達が、個別に最適化されたサポートを受けながら、安心して学習に取り組むことができます。
これらのアプローチを取り入れることで、子ども達の学習効果を高め、成長を促す環境を整えることができるでしょう。
まとめ
ワーキングメモリは、発達障害を持つ子ども達にとって、学習や日常生活における大きな課題となることがあります。
しかし、適切なサポートや環境の整備を通じて、子ども達のワーキングメモリを効果的に支援することが可能です。
家庭や学校、そして家庭教師を活用した個別のアプローチを組み合わせることで、子ども達が自分のペースで学びを深め、自信を持って成長していけるようサポートすることが重要です。
例えば、短く具体的な指示を与えたり、視覚や聴覚を活用した学習方法を取り入れたりすることで、子ども達の理解を促進し、学習効率を向上させることができます。
また、繰り返し学習や休憩を適切に取り入れることで、ワーキングメモリの負担を軽減し、長期的な記憶定着を助けることも大切です。
こうした日々の工夫が、子ども達の学習能力の向上に繋がります。
そして、最も重要なのは、子ども達が安心して学習に取り組める環境を整えることです。
専門家のアドバイスを受けながら、保護者や先生、家庭教師などが一丸となって子どもを支え、自信を持たせることで、子ども達は自分の力を信じ、成長していくことができるでしょう。
今後の可能性を広げるために、日常生活でできる小さなサポートを続けていくことが、発達障害のある子ども達の大きな成長に繋がっていきます。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。






