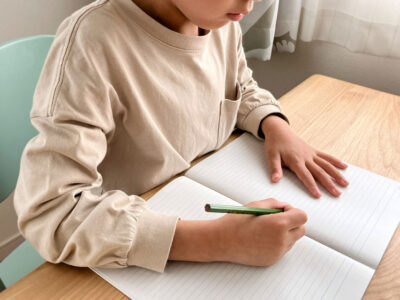春休みにやるべき勉強とは?発達障害のある子どもたちが学習を楽しむためのヒント

春休みは、学年の区切りとなる大切な時期です。
特に発達障害のある子どもにとって、新しい学年をスムーズにスタートするためには、焦って予習をするよりも、これまで学んだ内容をしっかり振り返ることが大切です。
なぜなら、学習の積み重ねが苦手だったり、一度理解したはずの内容を忘れやすかったりする特性があるからです。
「新学期に向けて少しでも先の内容を勉強したほうがいいのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、復習をおろそかにしたまま次の単元に進んでしまうと、授業についていけなくなり、学習の負担が増えてしまうこともあります。
春休みは長すぎず短すぎない、ちょうどいい期間だからこそ、「できることを増やす」時間にするのがポイントです。
この記事では、発達障害のある子どもたちが春休みの勉強を楽しく進めるためのヒントを紹介します。
どんな内容を復習すればよいのか、どんな学習方法が向いているのかを具体的に解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
目次
春休みの勉強はどう進めるべき?発達障害のある子どもたちに合った学習の考え方

春休みは学年の総復習をする絶好の機会ですが、発達障害のある子どもにとっては、どのように進めるかが重要です。
無計画に取り組むと学習意欲が下がってしまうこともあるため、無理なく継続できる方法を考えましょう。
ここでは、春休みの勉強を効果的に進めるためのポイントを紹介します。
春休みの学習計画は柔軟に!短期間の目標を立てるメリット
春休みの勉強計画は、厳密なスケジュールを作るよりも、柔軟に調整できるようにすることが大切です。
発達障害のある子どもは、気分やコンディションによって集中力に波があるため、毎日の勉強量を決めすぎると負担になりやすくなります。
短期間の目標を設定するメリット
短期間の目標を立てることで、学習へのハードルを下げ、達成感を得やすくなります。
例えば、以下のような形で区切ると、取り組みやすくなります。
| 期間 | 目標の立て方の例 |
|---|---|
| 1週間 | 計算ミスを減らすために、一日3問ずつ計算問題に取り組む |
| 3日 | 苦手な漢字を10個ずつ書き取り、3日で30個覚える |
| 1日 | 昨日間違えた問題を解き直して理解する |
また、勉強をする時は「◯ページ終わらせる」よりも「◯個の問題を解く」「◯分だけやる」という設定の方が、取り組みやすくなります。
ポイント
- 1週間単位での目標を考える(例:「算数の文章題を3日間で5問解く」)
- 1日の学習量を固定せず、その日の状況に応じて調整する
- 「できた!」と実感できる目標を設定することで学習意欲を維持する
勉強時間は「短く・集中」を意識!無理なく続けるコツ
春休みは、学校がないため自由な時間が多く、だらだらと過ごしてしまうこともあります。
しかし、発達障害のある子どもたちにとって、長時間の学習は集中力が続かず、逆に勉強嫌いにつながることがあります。
そのため、「短時間で集中する」学習方法を意識しましょう。
短時間学習の進め方
- 1回の学習時間は10〜20分を目安にする
・「長く勉強する」よりも「短時間で集中する」ほうが効率的
・集中できる時間は子どもによって異なるので、無理のない範囲で設定する - タイマーを使って区切る
・「15分だけやってみよう」と決めてタイマーをセットすると、だらけずに取り組める - 学習の合間にリフレッシュタイムを入れる
・5分間の休憩を挟むことで、次の学習に集中しやすくなる
おすすめの時間配分例
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10分 | 計算問題を解く |
| 5分 | 休憩(軽いストレッチや水分補給) |
| 10分 | 国語の文章読解に取り組む |
| 5分 | 休憩(好きな音楽を聴く、気分転換) |
「短く集中して終わる」ことを習慣化することで、勉強への抵抗感を減らし、春休みの間も学習リズムを維持しやすくなります。
「できた!」を増やす学習法とは?自己肯定感を高める工夫
発達障害のある子どもたちは、学習の成功体験が少ないと「どうせできない」と思い込んでしまいがちです。
そのため、春休みの勉強では「できた!」を増やし、自己肯定感を高めることが重要です。
自己肯定感を高める学習の工夫
- 簡単な問題から始める
最初に成功体験を積むことで、学習への抵抗を減らす 例:「簡単な計算問題→少し難しい文章題へ進む」 - 「解けた問題の数をカレンダーに書く」「できたらシールを貼る」など、視覚的に達成感を得られるようにする
- 間違えてもOKな環境を作る
・「間違える=学ぶチャンス」と伝え、正解することだけを重視しない
・先生や家庭での支援がある場合、「ここはよくできたね!」と具体的に褒める
春休みの勉強は、厳密なスケジュールを作るよりも、「短期間の目標を設定しながら、柔軟に調整する」ことが大切です。
また、短時間集中型の学習スタイルを取り入れることで、無理なく続けられます。
そして何より、「できた!」という成功体験を積み重ねることで、学習に対する自信を育てることができます。
春休みにおすすめの勉強内容!発達障害のある子どもたちが楽しく学べる工夫

春休みの勉強は、新学年に向けた準備期間として重要ですが、すべての範囲を一律に復習しようとすると負担が大きくなってしまいます。
特に発達障害のある子どもたちは、得意・不得意の差が大きいため、必要なポイントに絞って復習を進めることが大切です。
さらに、楽しく取り組める工夫を取り入れることで、学習の定着率を高めることができます。
ここでは、小学生・中学生それぞれの春休みにおすすめの学習内容と、無理なく続けるための工夫を紹介します。
学年の復習はどこまで必要?優先すべきポイントとは
新学年の学習をスムーズに進めるためには、これまでに学んだ基礎をしっかり固めておくことが重要です。
特に算数(数学)や国語のように積み重ねが必要な科目は、基礎があいまいなままだと、新しい単元が理解しにくくなってしまいます。
新学年に向けて復習すべきポイント
学年ごとに特に重点的に復習しておきたい内容を整理すると、以下のようになります。
【小学生】
- 新小学2年生:ひらがなの書き方、簡単な文章の読み書き、10までの足し算・引き算
- 新小学3年生:漢字の基礎(部首や書き順)、繰り上がり・繰り下がりの計算、かけ算九九
- 新小学4年生:文章問題の読み取り、長文の音読、分数と小数の基礎
- 新小学5年生:図形や面積の考え方、割り算の筆算、主語・述語を意識した作文
- 新小学6年生:速さ・割合・比の基礎、読解力を鍛える問題、敬語の使い方
【中学生】
- 新中学1年生:小学校の算数の総復習(特に分数・小数の計算)、基本的な英単語の読み書き
- 新中学2年生:一次方程式の解き方、比例・反比例のグラフ、英語の文法(現在形・過去形)
- 新中学3年生:連立方程式と関数の基礎、英語の長文読解の練習、理科・社会の用語整理
春休みは、新学期に向けた「準備期間」として、完璧に理解しようとするのではなく、つまずきやすい部分を重点的に復習するのがポイントです。
好きなことを活かした学習!興味を勉強につなげる方法
発達障害のある子どもたちは、興味のあることには驚くほどの集中力を発揮する一方で、関心が薄いことには手をつけにくいという特性があります。
この特性を活かし、春休みの勉強も「好きなことを学習につなげる工夫」をすることで、学習へのハードルを下げることができます。
好きなことを勉強に取り入れるアイデア
【小学生向け】
- 電車が好き
路線図を見ながら地名を覚える(社会)、乗車時間を計算する(算数) - 動物が好き
好きな動物の特徴を調べてレポートを書く(国語)、分類を学ぶ(理科) - ゲームが好き
ゲームのスコア計算で四則演算を練習(算数)、ゲームのストーリーを要約する(国語) - 図工が好き
立体図形を作って体積を考える(算数)、好きなものの説明文を書く(国語)
【中学生向け】
- 音楽が好き
歌詞の英訳をしてみる(英語)、音の振動を調べる(理科) - スポーツが好き
記録データを使って平均値や割合を計算する(数学)、競技の歴史を調べる(社会) - 歴史が好き
歴史上の出来事を年表にまとめる(社会)、時代背景をもとに作文を書く(国語) - アニメや映画が好き
セリフを英語で書き出してみる(英語)、物語の構造を分析する(国語)
このように、好きなことを学習に結びつけると、勉強への抵抗感が減り、楽しく学ぶことができるでしょう。
視覚や体験を活用!五感を使って理解を深める勉強法
発達障害のある子どもたちの中には、文字だけの学習よりも、視覚的に整理された情報のほうが理解しやすかったり、実際に体験しながら学ぶほうが記憶に残りやすかったりすることがあります。
視覚的に学ぶ工夫
- 色分けノートを作る:「算数の式は青」「答えは赤」「注意点は黄色」など、色を決めて整理する
- マンガや動画を活用する:文字だけで理解しにくい内容も、映像を見ながら学ぶことでイメージがつかみやすくなる
- イラストを描いて覚える:漢字の成り立ちを絵で表したり、歴史の流れを図にすることで、記憶に残りやすくなる
体験を通じて学ぶ工夫
- 料理を通して算数を学ぶ:「材料の分量を半分にする」「レシピの分量を3倍にする」といった割合の学習をする
- 公園や街の中で学ぶ機会を作る:「公園の距離を測る」「街の標識を読み取る」ことで、実際の生活と学習を結びつける
このように、春休みは時間に余裕があるからこそ、普段の学校生活ではできない学習方法を試してみるのもよいでしょう。
春休みの学習では、すべての範囲を網羅しようとするのではなく、「復習すべきポイントを見極め、子どもに合った学習方法を取り入れること」が大切です。
好きなことを学習に結びつけると、勉強への抵抗感が減り、楽しく学ぶことができます。
また、視覚的・体験的な学習方法を活用することで、より深く理解し、知識を定着させることができるようになるでしょう。
春休みだからこそ試せる!発達障害のある子どもたちが学習を楽しむ方法

春休みは、学校の授業がないため、自分のペースで学習に取り組める貴重な期間です。
しかし、自由な時間が増えることで、勉強のリズムが崩れてしまうこともあります。
特に発達障害のある子どもたちは、決められたスケジュールの中で動くほうが集中しやすい場合もあるため、学習の習慣が途切れないような工夫が必要です。
また、せっかくの春休みだからこそ、普段の学校の授業ではできない学習方法を取り入れ、楽しみながら知識を深める機会にすることも大切です。
ここでは、春休みを活用して学習を楽しむための具体的な方法を紹介します。
学習をゲームにする工夫
- 計算問題を時間を計って解くチャレンジにする:時間を計りながら問題を解くことで、達成感を味わえる
- すごろくやカードゲームを活用する:国語や算数の問題を取り入れたオリジナルゲームを作る
- ポイント制にして目標を設定する:「正解したらポイント獲得」「〇ポイントたまったらご褒美」といった仕組みを作る
例えば、「算数の計算問題を10問解いたら、1ポイント獲得。5ポイントたまったら好きな本を読める時間をプレゼント」といったように、学習を続ける楽しみを作ることで、自発的に取り組みやすくなります。
また、クイズ形式にして親や先生と一緒に楽しむのも効果的です。
例えば、「都道府県の形を見てどこか当てるクイズ」や、「英単語の神経衰弱」など、遊びの要素を取り入れることで、自然に知識が身につきます。
学習ツールを上手に活用!使いやすい教材やアプリの選び方
春休みの学習では、普段の教科書や問題集だけでなく、タブレットやアプリ、映像を使った教材なども取り入れることで、より楽しく学ぶことができます。
ただし、発達障害のある子どもたちは、複雑な操作や長時間の視聴が負担になることがあるため、使いやすいものを選ぶことが大切です。
おすすめの学習ツールの特徴
- 直感的に操作できるもの(難しいメニュー操作がない)
- 短時間で学べるもの(10〜15分程度で完結する内容)
- 視覚的にわかりやすいもの(イラストや動画があると理解しやすい)
例えば、算数の計算アプリでは、計算の正解・不正解をアニメーションで教えてくれるものや、英語の発音を聞いて真似するアプリなど、視覚・聴覚を活用できるものが効果的です。
また、紙の教材では、シールを貼って学習の進捗を見える化できるものや、カラフルなイラスト入りのドリルなどがモチベーションを維持しやすくなります。
学習ツールを選ぶ際は、実際に子どもと一緒に試しながら、「使いやすい」「楽しい」と感じるものを取り入れることが大切です。
先生や支援の力を借りる!苦手を克服するための環境づくり
春休みの勉強は、自分で進めることも大切ですが、わからないことが出てきたときに適切なサポートを受けられる環境を整えることも重要です。
特に、苦手な科目がある場合、一人で学習することがストレスになってしまうこともあります。
学習をサポートしてくれる環境を活用する方法
- 先生に質問できる機会を作る:塾や家庭教師を利用して、ピンポイントで苦手を克服する
- 学習支援の場を活用する:発達障害のある子どもたち向けの学習支援を行っている施設やプログラムを活用する
- 家庭での学習環境を工夫する:静かな場所で学べるようにする、集中しやすい教材を選ぶ
また、春休みは普段の学校の授業と違って、リラックスした状態で学習に取り組める時期でもあります。
そのため、「新しいことを学ぶ」のではなく、「苦手な部分をじっくり復習する時間」として使うと、余裕をもって取り組めます。
特に、家庭での学習では、親が過度に指導しようとするよりも、「一緒に考える」「やる気を引き出す声かけをする」ことが大切です。
例えば、「今日はどこまでできた?」と成果を確認したり、「昨日よりスムーズに解けたね!」と小さな成長を認めることで、自信につながります。
春休みの学習を楽しく進めるためには、「ゲーム感覚で取り組む」「学習ツールを活用する」「適切なサポートを受けられる環境を作る」などを取り入れるとよいでしょう。
勉強を「やらなければならないもの」ではなく、「楽しんで続けられるもの」に変えることで、学習意欲を維持しやすくなります。
また、苦手な分野に関しては、一人で悩まず、先生や学習支援の場を活用することで、スムーズに克服できることもあります。
春休みは、学校の授業に縛られず、自分に合った方法で学べる貴重な期間です。
ぜひ、楽しみながら学習を進められる方法を見つけてみてくださいね。
生活リズムと学習習慣を整える!春休み中の過ごし方のポイント

春休みは、学校の授業がないため生活リズムが乱れやすくなります。
特に発達障害のある子どもたちは、日々のルーティンが変わることで、学習のペースが崩れやすいことがあります。
しかし、生活リズムを整えることで、学習習慣も安定し、新学期をスムーズに迎える準備ができます。
ここでは、春休み中の生活リズムを整えながら、無理なく勉強を続けるためのポイントを紹介します。
朝の過ごし方がカギ!学習のリズムを崩さない工夫
春休みは自由な時間が増える分、夜更かしをして朝起きる時間が遅くなりがちです。
しかし、朝のリズムが乱れると、一日の流れが崩れ、勉強をするタイミングを見失いやすくなります。
そのため、なるべく学校があるときと同じような時間に起きて、午前中のうちに学習に取り組むことが大切です。
朝の生活リズムを整えるポイント
- 毎日同じ時間に起きる:目覚ましをセットして、一定の時間に起床する習慣をつける
- 朝のルーティンを決める:顔を洗う・朝ごはんを食べる・軽く体を動かすなど、決まった行動を続ける
- 午前中に軽めの学習を入れる:一日をスムーズに始めるために、10~15分程度の簡単な勉強を行う
例えば、朝食の後に「計算問題を3問だけ解く」や、「好きな本を1ページだけ読む」など、負担の少ない学習を習慣にすると、勉強のリズムを維持しやすくなります。
休憩の取り方も大切!集中力を維持するスケジュールの作り方
発達障害のある子どもたちは、長時間の学習を続けることが難しいことがあります。
そのため、「勉強をする時間」と「休憩を取る時間」のバランスを考えたスケジュールを作ることが重要です。
効果的な学習と休憩のバランス
- 1回の学習時間は短めに設定する(目安:10~20分)
- 勉強の合間に5分程度の休憩を取る(ストレッチや軽い運動がおすすめ)
- 長時間の学習は避け、午前と午後に分ける(例:午前に算数、午後に読解問題)
例えば「15分勉強したら、5分休憩」を繰り返すことで、集中力を維持しやすくなります。
休憩時間には、立ち上がって体を動かしたり、水分を取ったりすると、気分転換にもなります。
また、学習の合間に「好きなことをする時間」を組み込むのも有効です。
例えば、「30分勉強したら、お気に入りのアニメを10分だけ見る」「宿題を終えたら、外で遊ぶ」といったように、学習と楽しみの時間を組み合わせることで、無理なく続けられる環境を作ることができます。
家庭でできるサポート!リラックスと学習のバランスを取るコツ
春休み中は、勉強だけでなく、リラックスする時間も大切です。
発達障害のある子どもたちは、環境の変化に敏感な場合があるため、リラックスしながら学習に取り組める環境を作ることが重要です。
リラックスと学習を両立させる工夫
- 学習スペースを整える:静かな場所に机を用意し、余計なものを減らす
- プレッシャーをかけすぎない:「勉強しなさい!」ではなく、「今日はどんなことをやってみる?」と声をかける
- 楽しみの時間も大切にする:勉強の後に好きなことができるようにスケジュールを調整する
また、「春休み中に○○を頑張る!」と目標を決めることで、モチベーションを保ちやすくなります。
例えば、「春休み中に本を3冊読む」「漢字を50個覚える」といった具体的な目標を立て、それを達成できたらシールを貼るなど、進捗が目に見えるようにすると、やる気が続きやすくなります。
春休み中の生活リズムが乱れると、学習習慣も崩れやすくなります。
そのため、「朝の時間を有効に使う」「勉強と休憩のバランスをとる」「リラックスしながら学習できる環境を作る」などを取り入れるとよいでしょう。
また、毎日の学習は短時間でも良いので、「無理のない範囲でコツコツ続ける」ことを意識すると、新学期をスムーズに迎える準備ができます。
まとめ
春休みは、新学期に向けて学習の土台を固める大切な期間です。
しかし、発達障害のある子どもたちにとっては、学習への苦手意識や集中の難しさがハードルとなることもあります。
そのため、単に勉強量を増やすのではなく、「自分に合った方法で学ぶ」「興味を持てる形で取り組む」「生活リズムを整えながら学習を習慣化する」といった工夫が必要になります。
大切なのは、「勉強しなければならない」という義務感ではなく、「学ぶことが楽しい」と感じられる環境を作ることです。
好きなことを学習に取り入れたり、ゲーム感覚で楽しめる工夫を加えたりすることで、学習そのものへの抵抗を減らすことができます。
また、学習時間を短く区切ったり、休憩を適度に取り入れたりすることで、集中力を持続させることも可能です。
春休みの過ごし方次第で、新学期のスタートが大きく変わります。
焦らず、無理をせず、自分に合った学習方法を見つけることが、学習の継続につながります。
この期間を有効に活用し、小さな成功体験を積み重ねることで、新しい学年を自信をもって迎えられるようにしましょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。