授業についていけないのは発達障害のせい?原因と学習の遅れを取り戻す方法を徹底解説!
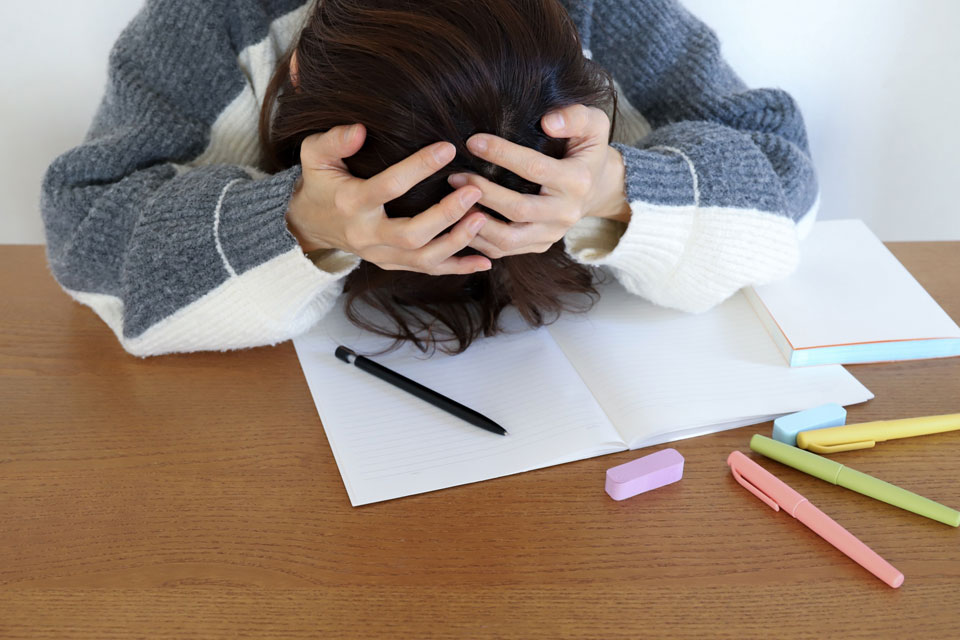
「先生の説明が早すぎて理解できない」
「勉強のやり方がわからない」
「どんなに頑張っても成績が上がらない」
皆さんは、そんな悩みを抱えていませんか?
教室で先生の話を聞いていても、いつの間にか思考が飛んでしまう。
黒板の文字を写すのに精一杯で内容が頭に入ってこない。
友達はすらすら問題を解いているのに、自分だけ取り残された気持ちになる。
小学生や中学生の中には、同じような悩みを抱え、どうすればいいのかと不安な気持ちになっている子も多くいるのではないかと思います。
授業についていけない理由はさまざまで、それは単に「勉強が苦手」というだけでなく、発達障害や学習スタイルの不一致など、さまざまな要因が影響していることが考えられます。
この記事では、授業についていけないと感じる原因を詳しく解説し、発達障害との関連性や学習の遅れを取り戻すための具体的な方法を詳しく紹介します。
自分に合った学習法を見つけて、少しずつでも成長を感じられるようになることが目標です。
勉強は決してスピードや他の人との比較ではありません。
自分のペースで、自分に合ったやり方で進めていくことが大切です。
この記事を読み終わる頃には、「私にもできる」という自信と具体的な行動プランが見つかるでしょう。
一緒に、可能性を広げていきましょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
目次
授業についていけない原因とは?
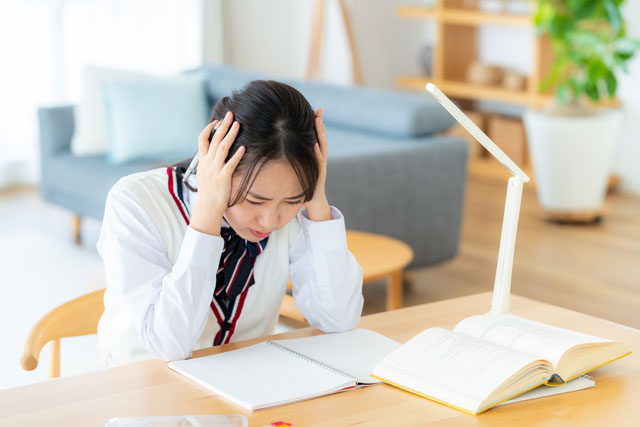
授業についていけない理由は一人ひとり異なります。
まずは、どのような原因が考えられるのかを理解しましょう。
発達障害の可能性について
発達障害とは、脳の発達の仕方が通常とは異なることで、学習や行動、コミュニケーションなどに影響が出る状態を指します。
発達障害がある場合、次のような症状が見られることがあります。
- 文字を読むことや書くことが難しい
- 計算が苦手
- 指示を理解するのに時間がかかる
- 集中力が続かない
- じっと座っていることが難しい
発達障害は生まれつきの脳機能の特性によるもので、適切な支援や環境の調整によって困難さを軽減することができます。
学習スタイルの不一致
人にはそれぞれ得意な学習スタイルがあります。
学校の授業スタイルと自分の学習スタイルが合っていないと、授業についていくのが難しくなることがあります。
主な学習スタイルには以下のようなものがあります。
- 視覚型:見て理解するタイプ。図や表、イラストがあると理解しやすい
- 聴覚型:聞いて理解するタイプ。説明を聞くことで記憶に残りやすい
- 運動型:体を動かしながら学ぶタイプ。実際に手を動かしたり、体験したりすることで理解が深まる
多くの授業は視覚型と聴覚型の学習者に合わせた形で進められます。
もし自分が運動型だったり、複数の感覚を使って学ぶ必要がある場合は、授業だけでは十分な理解が得られないかもしれません。
基礎学力の不足
学習内容はそれぞれ積み重ねの上に成り立っています。
例えば、かけ算ができないとわり算が難しく、分数の理解が不十分だと方程式が解けない、という具合です。
何らかの理由で基礎的な内容が理解できていないと、その上に積み重なる内容についていくのが難しくなり、これは「学習の穴」と呼ばれることもあります。
特に小学校低学年や中学校の入学時など、学習内容が大きく変わる時期に体調不良や転校などがあると、重要な基礎知識を逃してしまうことがあります。
集中力や注意力の問題
授業に集中できないのは、必ずしも「やる気がない」ということではありません。
集中力や注意力に関する問題は、次のような原因が考えられます。
- 睡眠不足:十分な睡眠が取れていないと集中力が低下します
- 栄養バランス:脳を働かせるためには適切な栄養が必要です
- ストレス:家庭や友人関係などのストレスがあると、勉強に集中するのが難しくなります
- 視力や聴力の問題:黒板が見えにくい、先生の声が聞こえにくいといった問題があるかもしれません
- 発達特性:ADHDなどの発達障害があると、注意力を持続させることが難しい場合があります
モチベーションや心理的要因
「どうせ自分にはできない」「努力しても無駄だ」というネガティブな思い込みがあると、学習への意欲が低下してしまいます。
また、以下のような心理的要因も学習に影響を与えることがあります。
- 過去の失敗体験:テストで低い点数を取ったことがトラウマになっている
- 過度なプレッシャー:親や先生からの期待が大きすぎる
- 学習への興味の欠如:なぜ勉強する必要があるのかが理解できていない
- 自己肯定感の低さ:自分の能力を信じられない
- 不安や恐怖:間違えることや失敗することへの恐れ
これらの心理的要因は、学習の大きな障壁となることがあります。
自分の気持ちに向き合い、必要なら周囲の大人に相談することが大切です。
発達障害と学習の関係を理解する
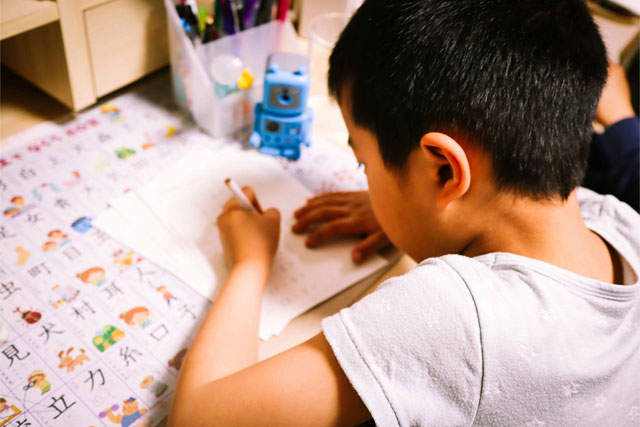
発達障害と学習の関係について、もう少し詳しく見ていきましょう。
発達障害の種類と特徴
発達障害には主に以下の種類があります。
- 限局性学習症/限局性学習障害(SLD:Specific Learning Disorder)
学習に必要な特定の能力(読む、書く、計算するなど)に困難がある状態 - 注意欠如・多動症(ADHD:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
注意力の持続や行動のコントロールが難しい状態 - 自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)
社会的コミュニケーションや対人関係の構築に困難がある状態
これらは明確に分かれているわけではなく、重なり合う部分もあります。
また、一人ひとり現れ方も異なるため、「スペクトラム(連続体)」という考え方が用いられています。
限局性学習症/限局性学習障害(SLD)について
限局性学習症(SLD)は、全般的な知的能力に問題がなくても、特定の学習領域に困難がある状態を指します。
以前は学習障害(LD)と呼ばれていましたが、現在の医学的診断名はSLDとなっています。
主な種類には以下のようなものがあります。
【読み書きの困難(ディスレクシアなど)】
文字を読むことに困難がある状態です。
文字が踊って見える、似た文字を混同する、文章を読むのに時間がかかるなどの特徴があります。
【書字表出の困難(ディスグラフィアなど)】
文字を書くことに困難がある状態です。
字の形が整わない、文字のバランスが取れない、書く速度が遅いなどの特徴があります。
【算数の困難(ディスカリキュリアなど)】
数の概念や計算に困難がある状態です。
数字の大小関係が分かりにくい、計算のプロセスを記憶できない、図形の認識が難しいなどの特徴があります。
限局性学習症があると、特定の科目だけ極端に苦手だったり、理解に時間がかかったりすることがあります。
例えば、国語の読解は苦手だけれど理科は得意、といった不均衡が見られることがあります。
注意欠如・多動症(ADHD)の特徴と学習への影響
ADHDには主に以下の特徴があります。
【不注意】
- 細かいミスが多い
- 注意を持続することが難しい
- 話を聞いていないように見える
- 指示に従うことが難しい
- 物をなくしやすい
- 忘れっぽい
【多動性】
- じっとしていられない
- 授業中に席を離れてしまう
- 過度にしゃべる
- 静かに遊べない
【衝動性】
- 質問が終わる前に答えてしまう
- 順番を待つことが難しい
- 他人の会話に割り込む
ADHDがある場合、授業に集中し続けることが難しく、重要な情報を聞き逃してしまうことがあります。
また、衝動的に行動してしまうことで、じっくり考えるべき問題でも早とちりしてしまうことがあります。
一方で、興味のあることには非常に集中できる「ハイパーフォーカス」という特性もあります。
この特性をうまく活かせると、学習効果が高まることもあります。
自閉スペクトラム症(ASD)と学習スタイル
ASDには主に以下の特徴があります。
【社会的コミュニケーションの困難】
- 視線を合わせることが難しい
- 相手の気持ちを読み取ることが難しい
- 冗談や比喩を字義通りに解釈してしまう
【こだわりや興味の偏り】
- 特定の分野に強い興味を持つ
- 予定や予測の変更に不安を感じる
- 同じ行動を繰り返す
【感覚過敏または鈍麻】
- 音や光、触感などに過敏に反応する
- 特定の音や匂いが苦手
ASDがある場合、言葉の意味を文字通りに解釈してしまうことがあるため、比喩や抽象的な説明が多い国語や社会などの科目で困難を感じることがあります。
また、感覚過敏があると、教室の雑音や明るさなどに気を取られて、授業に集中できないこともあります。
一方で、パターン認識や視覚的な情報処理が得意な場合も多いため、数学や理科などの論理的な科目が得意なことがあります。
また、特定の分野に関する知識が豊富で、その分野については驚くほど詳しいこともあります。
発達障害がある場合、学び方が異なるため従来の教育方法では十分に力を発揮できないことがありますが、その特性に合った支援や学習方法を取り入れることで、学習の困難さを軽減し、それぞれの強みを活かすことができます。
発達障害かどうかを知るための手がかり

授業についていけない原因が発達障害の可能性があるとわかったら、どうすればいいのでしょうか。
ここでは、自分自身や子どもの特性を理解するための手がかりを紹介します。
自己チェックリスト
以下のチェックリストは、発達障害の可能性を知るための参考にしていただくものです。
これらの項目に多く当てはまる場合は、発達障害の可能性があるかもしれません。
ただし、これはあくまで参考であり、正確な判断は専門家にご相談ください。
読み書きの困難に関する項目
- 字や行を飛ばして読んでしまうことがよくある
- 似た形の文字(「め」と「ぬ」など)を混同することがある
- 文章を音読するのに時間がかかる
- 黒板の文字を写すのに時間がかかる
- 漢字を覚えるのが難しい
- 文字のバランスが取れず、きれいに書けない
計算・数学の困難に関する項目
- 数字の大小関係を理解するのが難しい
- 計算の手順を覚えるのが難しい
- 暗算が苦手で、指を使って数える
- 時計の読み方が難しい
- お金の計算や時間の感覚がつかみにくい
注意力・集中力に関する項目
- 指示を最後まで聞かずに行動してしまう
- 物をよくなくす
- 宿題や持ち物を忘れることが多い
- 整理整頓が苦手
- 集中力が続かず、すぐに気が散る
- じっと座っていられない
コミュニケーションに関する項目
- 相手の表情や気持ちを読み取るのが難しい
- 冗談や皮肉を文字通りに受け取ってしまう
- 友達の輪に入るのが難しい
- 場の空気を読むのが苦手と言われる
- 一度に複数の指示を理解するのが難しい
感覚・運動に関する項目
- 特定の音や光、触感に過敏に反応する
- 体育の授業で球技や縄跳びなどが苦手
- はさみや定規などの道具を使うのが難しい
- 左右の区別がつきにくい
これらの特徴は、発達障害だけでなくさまざまな原因で現れることがあります。
一部の項目に当てはまるだけで発達障害と断定するのではなく、日常生活や学習において困っていることがあれば、専門家に相談してみましょう。
専門家への相談方法
発達障害かもしれないと感じたら、以下のような専門家や相談窓口を利用することができます。
学校の先生や養護教諭
まずは学校の担任の先生や養護教諭に相談してみましょう。
学校での様子を見ている先生方は、子どもの特性について気づいていることがあるかもしれません。
また、学校によっては特別支援教育コーディネーターという専門の先生がいる場合もあります。
スクールカウンセラー
多くの学校にはスクールカウンセラーが配置されています。
子どもの心理面や学習面での悩みを相談することができます。
発達支援センター
市区町村によって名称は異なりますが、発達に関する相談ができる公的な機関があります。
専門のスタッフが相談に応じてくれます。
小児科医・専門医
発達障害の診断を受けたい場合は、小児科医や発達障害を専門とする医師に相談しましょう。
かかりつけ医に相談するか、発達障害の専門医を紹介してもらえるよう依頼することもできます。
教育センター・教育相談窓口
各自治体の教育委員会などが運営する教育センターや教育相談窓口でも、学習面での悩みを相談することができます。
相談する際のポイント
- 困っていることを具体的に伝える
- 学校や家庭でどのような場面で困難が生じているかを説明する
- これまでに試してきた対応方法とその結果を伝える
- 子どもの得意なことや好きなことも伝える
診断の意味と向き合い方
発達障害の診断を受けることには、いくつかの意味があります。
診断を受けることのメリット
- 自分や子どもの特性を理解するための手がかりになる
- 適切な支援や配慮を受けやすくなる
- 学校での合理的配慮につながる可能性がある
- 自治体のサポートや福祉サービスを利用できる場合がある
- 自分を責めず、適切な対処法を探すきっかけになる
診断を受けた後の向き合い方
【診断名にとらわれすぎない】
診断名は特性を理解するための手がかりであり、その人自身を定義するものではありません。
一人ひとり異なる強みと弱みがあります。
【強みを見つけ、伸ばす】
発達障害のある人は、特定の分野で優れた能力を発揮することがあります。
苦手なことに注目するだけでなく、得意なことや好きなことを見つけ、それを伸ばすことが大切です。
【適切な支援を探す】
診断を受けたことで、自分に合った学習方法や支援を見つけやすくなります。
学校や家庭で必要な配慮について相談してみましょう。
【周囲の理解を得る】
必要に応じて、学校の先生や友人に自分の特性について説明することで、適切な理解と支援を得やすくなります。
【同じ特性を持つ人々とのつながり】
発達障害の特性を持つ人々の体験談や工夫を知ることで、自分にも役立つヒントが見つかるかもしれません。
診断を受けるかどうかは個人の選択です。
診断を受けなくても、自分の特性を理解し、それに合った学習方法を見つけることはできます。
大切なのは、自分自身や子どもの特性を理解し、それに合った支援や学習方法を探していくことです。
学習の遅れを取り戻すための具体的方法

発達障害の有無にかかわらず、自分に合った学習方法を見つけることは大切です。
ここでは、学習の遅れを取り戻すための具体的な方法を紹介します。
自分に合った学習スタイルの見つけ方
人によって効果的な学習方法は異なります。
自分に合った学習スタイルを見つけるためのポイントを紹介します。
自分の学習タイプを知る
先ほど紹介した3つの学習タイプ(視覚型、聴覚型、運動型)のどれに当てはまるかを考えてみましょう。
【視覚型の場合】
- 文字や図を見て学ぶ
- カラフルなマーカーや付箋を使う
- マインドマップや図解を活用する
- 学習内容を図や表にまとめる
【聴覚型の場合】
- 音読や朗読を活用する
- 学習内容を録音して聞く
- 内容を自分で説明してみる
- 音楽やリズムを使って記憶する
【運動型の場合】
- 書いて覚える
- 実際に体を動かしながら学ぶ
- ジェスチャーを交えて記憶する
- 立ったり歩いたりしながら学習する
小さな成功体験を作る
自分に合った方法で学ぶことで、「できた!」という経験を積み重ねることが大切です。
最初は簡単な課題から始めて、徐々に難しくしていきましょう。
好きなことと結びつける
興味のあることと学習内容を結びつけると、記憶に残りやすくなります。
例えば、好きなキャラクターを使って計算問題を作ったり、趣味に関連した例で理解を深めたりする方法があります。
複数の感覚を使う
視覚、聴覚、運動感覚など、複数の感覚を組み合わせて学ぶと効果的です。
例えば、教科書を読みながら(視覚)、音読し(聴覚)、重要な部分を書き写す(運動感覚)という方法が考えられます。
効果的な学習計画の立て方
学習の遅れを取り戻すためには、計画的に進めることが大切です。
現状の把握
まずは、どの科目のどの部分が理解できていないのかを明確にしましょう。
教科書や参考書の目次を見ながら、理解できている部分と理解できていない部分を分けてみましょう。
優先順位をつける
全ての科目を一度に取り組むのではなく、優先順位をつけて取り組みましょう。
特に、基礎となる部分から理解することが大切です。
小さな目標を設定する
「1週間で教科書1章分を理解する」など、具体的で達成可能な目標を設定しましょう。
小さな目標を達成することで、自信につながります。
時間割を作る
週間計画や日々の学習時間割を作成すると、計画的に学習を進めることができます。
その際、以下のポイントを意識しましょう。
- 集中力が高い時間帯を活用する
- 難しい科目は集中力が高い時間帯に取り組む
- 1回の学習時間は30分程度を目安にする
- 科目ごとに学習時間にメリハリをつける
- 休憩時間も計画に入れる
学習の記録をつける
学習した内容や時間を記録することで、進捗状況を把握でき、達成感も得られます。カレンダーやノートなどを活用しましょう。
記憶力・集中力を高めるテクニック
記憶力を高めるテクニック
- 復習のタイミングを工夫する
効果的な復習のタイミングは、学習直後、1日後、1週間後、1ヶ月後と言われています。
このタイミングで復習することで、記憶の定着率が高まります。 - 情報を小分けにして覚える
情報を小さなかたまりに分けて覚えると、記憶しやすくなります。
例えば、電話番号を「090-1234-5678」のように区切って覚えると覚えやすくなります。 - イメージ化する
覚えたい内容を具体的なイメージや絵に変換すると記憶に残りやすくなります。
例えば、歴史上の出来事を漫画のように想像するなどの方法があります。 - 関連付けて覚える
新しい情報を、すでに知っていることと関連付けて覚えると効果的です。
例えば、新しい英単語を似た日本語と結びつけるなどの方法があります。 - 説明してみる
学んだ内容を誰かに説明することで、理解度が深まり、記憶に定着します。
実際に人に説明できなくても、説明するつもりで声に出してみるだけでも効果があります。
集中力を高めるテクニック
- 短時間集中学習
25分間集中して学習し、5分間休憩するというサイクルを繰り返す方法も効果的です。
短い時間に集中することで、効率的に学習を進めることができます。 - 環境を整える
学習に適した環境を作ることも大切です。
・静かな場所を選ぶ
・適切な明るさを確保する
・温度や湿度を快適に保つ
・スマートフォンなどの気が散る要素を排除する - 体を動かす
適度な運動は脳の活性化につながります。
学習の前に軽い運動をしたり、休憩時間に体を動かしたりすることで、集中力が高まります。 - 十分な睡眠と栄養
集中力を維持するためには、十分な睡眠と栄養が欠かせません。
特に、朝食をしっかり取ることで、午前中の集中力が高まります。 - 目標と見返りを設定する
「30分間集中して勉強したら、10分間好きなことをする」などの小さな目標と見返りを設定することで、集中力を維持しやすくなります。
デジタルツールの活用法
さまざまなデジタルツールを活用することで、効果的に学習を進めることができます。
学習アプリ
英単語学習アプリ、計算ドリルアプリ、漢字学習アプリなど科目ごとに特化した学習アプリを活用するのもおすすめです。
これらのアプリは、ゲーム感覚で楽しく学習できる工夫がされ、学びやすくなっています。
デジタル教材
デジタル教科書や参考書、動画教材などを活用することで、視覚的に分かりやすく学習することができます。
特に、アニメーションや図解を用いた説明は、理解を深めるのに役立ちます。
読み上げ機能
読み書きが苦手な場合、テキストを音声に変換する読み上げ機能を活用するとよいでしょう。
多くのデバイスには読み上げ機能が標準搭載されています。
タイマーアプリ
短時間の集中学習法を実践する際に、タイマーアプリを使うと便利です。
学習時間と休憩時間を設定して、効率的に学習を進めることができます。
記録・管理アプリ
学習計画や進捗状況を記録・管理するアプリを活用することで、計画的に学習を進めることができます。
カレンダーアプリやToDoリストアプリなどがあります。
音声入力
書くことが苦手な場合、音声入力を活用することで、考えたことをテキストにすることができます。
レポートや作文などを作成する際に役立ちます。
デジタルノート
紙のノートの代わりにデジタルノートを活用することで、書いたことを編集したり、検索したりすることができます。
また、図や表を簡単に挿入することもできます。
【デジタルツールを活用する際のポイント】
- 使いやすいものを選ぶ
- 目的に合ったツールを選ぶ
- 使い方を十分に理解する
- 適切な時間管理を心がける
- デジタルツールに頼りすぎない
発達障害の有無にかかわらず、自分に合った学習方法を見つけることが大切です。
自分の特性を理解し、それに合った支援や学習方法を探していくことで、学習の遅れを取り戻し、自分のペースで成長していくことができることでしょう。
まとめ
授業についていけない理由は人それぞれ異なり、発達障害や学習スタイルの違い、基礎学力の不足、集中力やモチベーションの問題など、さまざまな要因が関係しています。
発達障害がある場合、適切な学習環境の調整や支援を受けることで、学習の困難さを軽減することができます。
また、自分に合った学習スタイルを見つけることが、授業への理解を深めるための重要なポイントとなります。
学習の遅れを取り戻すためには、短時間集中学習や視覚・聴覚・運動感覚を活かした勉強法、デジタルツールの活用など、自分に合った方法を取り入れることが大切です。
さらに、生活習慣の見直しや適切な休息をとることで、集中力を維持しやすくなります。
学習はスピードを競うものではなく、自分のペースで進めることが重要です。
授業についていくためにはさまざまな困難があるかもしれませんが、自分に合った学習方法を見つけ、少しずつでも前進することが大切です。
サポートが必要な場合は、学校や専門機関に相談しながら、学びやすい環境を整えましょう。
自分の可能性を信じて、学習を続けていくことで、できることは必ず増えていくことでしょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。






