療育を活かして勉強しやすく!発達障害のある中学生向け学習サポート

発達障害のある中学生が勉強に取り組むとき、
「どうしても集中できない」
「授業についていけない」
と悩むことがあります。
こうした困難は、学習の進め方や環境を工夫することで改善できる場合が多くありますが、どのように対策すればよいのか分からないという声もよく聞かれます。
特に、小学生のときは問題なく学べていたのに、学年が上がるにつれて学習が難しく感じるようになったというケースも少なくありません。
「療育を活かす」とは、医療や特別な指導を行うことではなく、「発達の特性に合った学習の工夫を取り入れる」という考え方です。
学校や家庭でできることも多く、「学びやすい環境を整える」「理解を助けるサポートを取り入れる」ことが、学習の負担を減らすことにつながります。
学習のしやすさを高めるためには、療育の視点を取り入れた学習環境づくりも大切です。
例えば、適度に体を動かして気持ちを切り替える、学習の流れをわかりやすく示すなど、無理なく続けられる工夫が役立ちます。
また、「何が苦手か」よりも「どんな方法なら学びやすいか」を考えることがポイントになります。
この記事では、発達障害のある中学生が学びやすくなるためのポイントや、療育の視点を活かした学習サポートの方法について紹介します。
ADHD・ASD・SLD(学習障害)などの特性ごとに、どのような学習の工夫ができるのかも詳しく解説していくので、参考にしてくださいね。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。
目次
療育を活かして学びやすく!発達障害のある中学生の学習の困りごとと対策

ここでは、発達障害のある中学生が学習でつまずきやすいポイントを整理し、それに対する基本的な対策を紹介します。
「なぜ勉強が難しく感じるのか?」を理解したうえで、具体的な学習支援の工夫を考えていきましょう。
発達障害があると勉強が難しくなる理由とは?
発達障害のある中学生が学習に苦手意識を持ちやすいのは、それぞれの特性による影響があるためです。
「授業についていけない」「ノートを取るのが難しい」などの悩みは、人によって異なります。
ADHD(注意欠如多動症)の場合
ADHDの特性があると、次のような困りごとが生じやすくなります。
- 集中力が続かない → 授業中や家庭学習で気が散りやすく、途中で集中が途切れる。
- 計画を立てるのが苦手 → 「どこから手をつければいいのか」がわからず、勉強を後回しにしがち。
- 忘れ物やミスが多い → 宿題をやったのに提出を忘れる、計算ミスが多いなど。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合
ASDの特性がある場合、以下のような点で学習が難しくなることがあります。
- 曖昧な指示が苦手 → 「適当にまとめよう」「考えを深めよう」などの表現に戸惑う。
- 予定外の変化に弱い → 急な授業変更や、想定外の課題が出ると混乱する。
- 周囲の刺激が気になる → 教室の騒音や他の生徒の動きが気になり、集中できない。
SLD(限局性学習症・学習障害)の場合
SLDがあると、特定の分野での学習が特に難しくなります。
- 読み書きが苦手 → 漢字や英単語を覚えにくく、文章を書くのに時間がかかる。
- 計算に時間がかかる → 数字を読むのに時間がかかったり、暗算が苦手だったりする。
- 板書を写すのが遅い → 先生の話を聞きながらノートを取るのが大変。
こうした特性による学習の困りごとは、適切な工夫を取り入れることで軽減できます。
学習支援に役立つ「療育を活かした学習環境づくり」
療育を活かすといっても、特別な指導が必要なわけではなく、「学習しやすい仕組みを作ること」が大切です。
例えば、学習計画を立てるのが苦手な場合、「何をいつやるのか」を明確にするだけで勉強がスムーズになることがあります。
また、授業や宿題の内容を整理しやすくするため、「色分けして視覚的に整理する」などの工夫も有効です。
「一度にたくさん覚えようとしない」「短時間で集中して学ぶ」など、小さな工夫の積み重ねが、学習の負担を減らします。
「苦手なことを無理に克服しようとする」のではなく、「学習しやすい方法を見つける」という考え方が、療育を活かした学習サポートの基本です。
学習の見通しを持たせる
勉強を進めるうえで、「何をいつやるのか」が明確でないと手が止まりやすくなります。
そのため、次のような工夫を取り入れると、スムーズに学習を進められます。
- スケジュールを作る → 「今日は国語の宿題と数学の問題集をやる」と決めておくと迷わない。
- タスクをリスト化する → 「できたらチェックを入れる」ことで、達成感を得られる。
視覚的なサポートを活用する
文字だけの情報は、理解しづらいことがあります。
そこで、次のような工夫が役立ちます。
- 図やイラストを使う → 算数の文章問題を図に描いて整理すると、内容がわかりやすくなる。
- 色分けをする → ノートに大事な部分をマーカーで目立たせると、復習しやすくなる。
短時間で区切って勉強する
長時間の学習は集中が続かず、効率が下がりやすくなります。そこで、短時間で区切る方法が有効です。
- 15分勉強し、5分休憩を繰り返す → 「この時間だけ頑張ろう」と決めると、集中しやすくなる。
- タイマーを活用する → 時間を意識すると、ダラダラせずに取り組める。
学習方法を工夫する
勉強のやり方を変えるだけで、苦手な分野も取り組みやすくなります。
- 暗記が苦手なら「書く・声に出す・聞く」を組み合わせる
- 数学が苦手なら、具体物(ブロック・数直線など)を使って理解する
- 文章問題が苦手なら、質問のポイントを色分けして整理する
成功体験を増やす
勉強に対する苦手意識を減らすには、「できた!」という感覚を増やすことが大切です。
- 簡単な問題から取り組む → 「できる!」と感じると、やる気が出やすい。
- 頑張ったことを記録する → 「毎日10分勉強できた!」と目に見える形にすると達成感が増す。
このような工夫を取り入れることで、勉強が少しずつ楽になっていきます。
発達障害のある中学生に共通する学習しやすい環境づくり
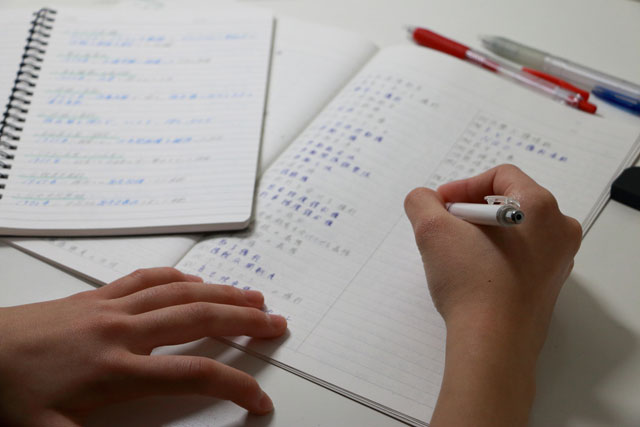
勉強をしようと思っても、学習環境が整っていないと集中しにくく、スムーズに進めることが難しくなります。
特に、発達障害のある中学生にとっては、周囲の刺激や環境の影響を受けやすいため、自分に合った学習環境を整えることが大切です。
ここでは、集中しやすく、学習の見通しが持てる環境づくりの方法を紹介します。
集中しやすい環境を整える方法
発達障害のある中学生の多くは、気が散りやすかったり、周囲の音や視覚的な刺激に影響を受けやすかったりするため、集中できる環境を作ることが重要です。
学習スペースを整理する
机の上が散らかっていると、目に入るものが気になり、集中が続きにくくなります。
そのため、勉強を始める前に机の上を整理し、「今使うものだけを置く」ようにすると、気を散らさずに学習に取り組みやすくなります。
また、教科ごとにノートや教材をまとめておくと、「あれがない、これがない」と探す時間が減り、スムーズに学習が進みます。
そのため、収納ボックスやファイルを使って、すぐに取り出せるようにするとよいでしょう。
周囲の刺激を減らす
集中できる環境を作るためには、周囲の音や視覚的な刺激を減らす工夫も有効です。
- 静かな場所で勉強する → 家庭学習では、リビングよりも自分の部屋のほうが集中しやすいことが多い。
- イヤーマフや耳栓を使う → まわりの音が気になりやすい場合は、音を遮ることで集中しやすくなる。
- 机の向きを変える → 窓の外や部屋の出入り口が見えると気が散るため、壁に向けて机を置くのも一つの方法。
このように、自分にとって気が散りにくい環境を作ることが、集中力を高めるカギになります。
勉強の見通しを持てる工夫(スケジュール・タスク管理)
「何から始めればいいかわからない」「どのくらい時間がかかるのか見当がつかない」といった状態では、勉強を始めるまでに時間がかかり、効率が悪くなります。
そのため、スケジュールやタスクを見える形にして、学習の見通しを持てるようにすることが大切です。
1日の勉強計画を立てる
勉強を始める前に、「今日は何をどれくらいやるのか」を決めておくと、スムーズに取り組みやすくなります。
- シンプルな予定表を作る → 「国語の宿題→数学の問題集→休憩→英単語10個暗記」のように、やることを順番に書く。
- 勉強時間を決める → 「〇時から〇時までは数学」「その後10分休憩」など、具体的な時間を設定するとダラダラしにくい。
無理のない計画を立て、達成できたらチェックを入れると、やる気が続きやすくなります。
タスクをリスト化して達成感を得る
やるべきことをリストにし、終わったものにチェックを入れることで、「進んでいる」という実感がわき、モチベーションが維持しやすくなります。
<例>
- 今日の宿題を終わらせる
- 明日の予習を10分だけする
- 英単語を5個覚える
このように、小さな目標に分けることで、達成感を得やすくなります。
リストを使うことで、「あとどれくらいやればいいのか」が明確になり、学習の見通しを持ちやすくなるのがメリットです。
成功体験を増やして学ぶ意欲を高めるコツ
「勉強が苦手」「やる気が出ない」と感じる中学生にとって、「できた!」という経験を増やすことが大切です。
ここでは、勉強に前向きに取り組むための工夫を紹介します。
小さな成功体験を積み重ねる
難しい問題から始めると「やっぱりできない」と落ち込みやすいため、簡単な問題からスタートするのがポイントです。
<例>
- 計算問題は最初に基本的なものを解き、少しずつ難しくする。
- 英単語を「1日5個ずつ」覚えていくことで、少しずつ語彙を増やす。
「できた!」という経験が増えると、学習に対する苦手意識が減り、勉強へのモチベーションが上がりやすくなります。
頑張ったことを記録する
学習の成果が目に見えると、やる気が続きやすくなります。
例えば、「できたことを記録するカレンダー」の作成などは、達成感を感じやすくなるのでおすすめです。
- 1日勉強できたらシールを貼る → 見た目で進捗がわかり、やる気がアップ。
- ノートに「今日の振り返り」を書く → 「今日はこれができた」「次はここを頑張る」と記録すると、次の勉強につなげやすい。
こうした学習の積み重ねを実感できる工夫を取り入れることで、意欲的に勉強を続けやすくなります。
学習環境を整えることで、「勉強しやすい」と感じる場面が増え、学習への抵抗感を減らすことができます。
特性別に考える!発達障害のある中学生向けの学習支援
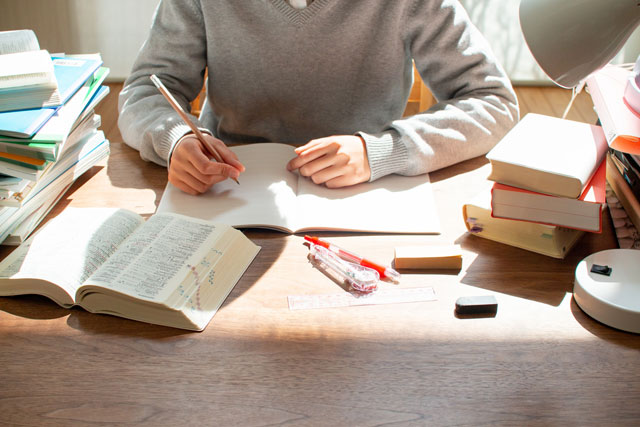
高校生になると、受験や進路についての不安も大きくなります。
そのため、中学生のうちに「どのような学習方法が自分に合っているか」を見つけておくことが、高校での学習にスムーズにつなげるポイントになります。
また、勉強が苦手だと感じる背景には、コミュニケーションの難しさが関係していることもあります。
授業中に先生へ質問するのが苦手だったり、友達に「この問題どうやるの?」と聞くことができなかったりすると、学習の遅れにつながることがあります。
そのため、先生や支援員と「どんなときに困るか」を共有し、学びやすい環境を整えることが大切です。
ここでは、ADHD・ASD・SLD(学習障害)の特性ごとに、「どのような困りごとがあるのか」「どのような工夫が役立つのか」を詳しく解説していきます。
ADHD(注意欠如多動症)の場合の学習の工夫
ADHDの特性があると、集中が続かず、学習の進め方がわからなくなることがあります。
また、計画を立てたり、ミスを防いだりするのが苦手なため、うまく勉強が進まないことが多くなります。
しかし、学習の進め方を工夫することで、こうした困りごとを減らすことができます。
ここでは、ADHDの特性に合った具体的な学習方法を紹介します。
計算ミスを減らす工夫をする
ADHDのある中学生は、計算中に途中の式を飛ばしたり、符号を見落としたりすることが多くあります。
特に、筆算で桁がずれてしまったり、暗算で簡単に済ませようとしてミスをしたりするケースがよく見られます。
そこで、次のような方法で計算ミスを減らすことができます。
- 筆算のスペースを広く取る → 計算用ノートを使い、1つの計算に十分なスペースを確保する。マス目の大きいノートを使うと、桁をそろえやすくなる。
- 途中式を書く → 特に分数の計算では、通分や約分を省略せず、1つずつ式を書いて確認する。
- 計算結果を逆算してチェックする → 例えば、「12 ÷ 3 = 4」と解いたら、「4 × 3 = 12」と逆算して確かめることで、計算ミスを防ぐ。
文章を理解しながら読む方法を身につける
長い文章を読むと、途中で何が書かれていたのかわからなくなることがあります。
特に、数学や理科の問題文は、文章が長くなりやすく、途中で集中が切れてしまうことがあります。
そのため、次のような工夫を取り入れると、文章を理解しやすくなります。
- 重要な部分にマークをつける → 問題文の中の「聞かれていること」に線を引くと、必要な情報を整理しやすくなる。
- 1文ずつ区切って読む → 長い文章は、一度に読もうとせず、文ごとに意味を確認しながら読む。
- 声に出して読む → 読みながら自分の声を聞くことで、内容が整理されやすくなる。特に、英語の長文では効果的。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合の学習の工夫
ASDの特性がある場合、指示が曖昧だと混乱しやすく、文章問題の理解が難しいことがあります。
また、決まった学習パターンがないと、どのように進めればいいのか迷いやすくなります。
こうした特性に合わせて、学習の進め方を工夫することで、問題の解き方が整理しやすくなります。
問題文を正確に理解する工夫をする
数学や理科の文章問題では、問題の意図がわからず手が止まることがあります。
そのため、文章を整理しながら読むことで、何を求められているのかを明確にすることが大切です。
- 問題の数字に丸をつける → どの数字が関係しているかを整理すると、計算しやすくなる。
- 質問の部分を言い換えてみる → 例えば、「Aさんの速さは?」と書かれていたら、「速さを求めるには、何を計算すればいい?」と考えながら進める。
- 図や表を活用する → 文章がわかりにくいときは、自分で図を描いたり、表に整理したりすると、情報が整理しやすくなる。
答えを導くための手順を決める
「どこから考えればいいのかわからない」と感じる場合は、手順を決めて解く方法を身につけると、スムーズに問題に取り組めます。
例えば、数学の問題を解くときに、
① 問題を読みながら図に描く
② 使う公式や計算方法を確認する
③ 計算をする
という流れを決めておくと、「どう考えればいいかわからない」と困ることが少なくなります。
SLD(限局性学習症・学習障害)の場合の学習の工夫
SLDの特性があると、文字を読むのが遅い、漢字や英単語が覚えにくい、計算が苦手といった困りごとが出やすくなります。
また、板書を写すのに時間がかかることもあり、授業についていくのが難しくなることがあります。
こうした学習の困りごとを軽減するための工夫を紹介します。
読みやすい工夫を取り入れる
文字を読むのが苦手な場合は、読むスピードを調整しながら進めることが大切です。
また、読んでいる途中でどこまで読んだかわからなくなることもあるため、行を飛ばさない工夫が役立ちます。
- 指でなぞりながら読む → 教科書や問題文を読むとき、指でなぞることで行を飛ばさずに読める。
- 短い文章を区切って読む → 一度に読む範囲を減らし、「1つの文を読んだら意味を確認する」ことを繰り返す。
漢字や英単語を覚える工夫をする
漢字や英単語を覚えるのが苦手な場合は、書くだけでなく、視覚や音声を活用すると覚えやすくなることがあります。
- カードに書いて、見て覚える → ひらがなとセットにして覚えると定着しやすい。
- 耳で聞いて覚える → 英単語は、音声を聞きながら口に出して読むと記憶に残りやすい。
- 漢字の意味をイメージで覚える → 「海(うみ)」なら波の形を想像するなど、イメージとセットにすると記憶しやすい。
「なぜ勉強がしづらいのか」を理解し、それぞれの特性に合った方法を取り入れることで、学びやすさが変わります。
学校や家庭でできるサポート方法

学校では授業の進め方や課題の出し方が、学習のしやすさに大きく影響を与えます。
しかし、学校の先生は生徒一人ひとりの特性をすべて把握できるわけではありません。
そのため、「どのようなことが苦手なのか」ではなく、「どのようなサポートがあれば学習がスムーズに進むのか」を考えることが大切です。
<例>
- 視覚的な情報があると理解しやすいなら、「黒板の内容をまとめたプリントをもらう」よう相談する。
- ノートを取るのが苦手なら、タブレットや写真を活用して板書を記録する。
- 学習計画を立てるのが苦手なら、「どこまで進めればいいのか」を具体的に示す。
このように、学習のしやすさを高めるためには、特性に合わせたサポートを取り入れることが重要です。
ただ、こうしたサポートを受けるためには、先生や支援者にどのように伝えるかも大切なポイントとなります。
先生に伝えておきたい学習の困りごとと配慮のポイント
小学生のうちは、保護者や先生が学習の進め方をフォローする場面が多くありますが、中学生になると「自分で学ぶ力」が求められるようになります。
この変化に対応するためには、家庭でのサポートや、学校での適切な配慮が重要になります。
また、学習だけに集中するのが難しい場合、適度な運動を取り入れることで、勉強への切り替えがしやすくなることもあります。
例えば、「勉強を始める前に軽くストレッチをする」「集中できないときは数分間歩いてリフレッシュする」などの工夫が有効です。
さらに、授業の進め方に関する調整を相談することも大切です。
板書がうまく取れない場合は、タブレットの録画・スクリーンショット機能を活用し、黒板の内容を保存できるようにすると、学習の負担が軽減されることがあります。
また、学校の先生や支援員と連携し、適切なサポートを受けられるようにすることで、勉強のしやすさが向上します。
板書や授業の進め方に関する配慮
発達障害のある中学生の中には、黒板の板書を写すのが苦手だったり、授業の進むペースについていけなかったりする子がいます。
そのため、以下のような配慮を先生にお願いすると、授業の理解がスムーズになります。
- 板書を写す時間を確保してもらう → 板書を写すのが遅い場合は、「ノートに書く時間を少し長めにとってもらう」などの調整をお願いする。
- 要点を整理して伝えてもらう → 授業中に「この部分が特に大事」と先生が強調してくれると、どこに注目すればよいのかがわかりやすくなる。
- プリントやデジタル教材を活用する → 板書の代わりにプリントを渡してもらうことで、授業の理解に集中できることもある。
課題やテストの取り組みやすさを調整する
宿題やテストの問題文が長いと、何を求められているのかがわかりにくくなることがあります。
また、時間内に解き終わるのが難しい場合もあります。
- 問題文を簡潔にしてもらう → 問題の意図がわかりにくいときは、「答えるべき内容を明確にしてもらう」と理解しやすくなる。
- 解答スペースを広めに取ってもらう → 記述問題などで、狭いスペースに書くのが苦手な場合、解答欄を広くしてもらうと書きやすい。
- 時間の延長や別室対応を相談する → 集中しにくい環境ではテストのパフォーマンスが下がるため、場合によっては配慮をお願いすることもできる。
なお、問題文が分かりにくい場合は、下記のような工夫をすることで分かりやすくなります。
| 特性 | わかりにくい問題文の特徴 | 改善例 |
|---|---|---|
| ADHD(注意欠如多動症) | 問題文が長いと最後まで読めない。どこが大事かわからず、集中が途切れる。 | 文章を短く区切り、数字を目立たせる。質問部分を強調して、注意が向きやすくする。 |
| ASD(自閉スペクトラム症) | 曖昧な表現や、「どの数字を使えばいいのか」がはっきりしないと混乱する。 | 「○○を求めなさい」のように、指示を具体的にする。不要な情報を削除し、シンプルな文にする。 |
| SLD(限局性学習症) | 読み飛ばしやすい。文字情報だけでは理解しにくい。 | 行間を空けて見やすくする。重要な語句を目立たせる。図や表を活用する。 |
家庭でできる学習サポートの工夫
家庭でのサポートは、「勉強をやらせる」ことではなく、「学習しやすい環境を整え、一緒に学ぶ姿勢を持つ」ことが大切です。
「勉強しなさい」と言うだけでは、本人のモチベーションが下がってしまうこともあるため、学習への取り組みをスムーズにする工夫が必要です。
勉強の進め方を一緒に考える
「何をやるのか」「どう進めるのか」がわからないと、勉強に手をつけられないことがあります。
そのため、学習計画を一緒に立てることがサポートの一つになります。
- 「今日やることリスト」を作る → 勉強を始める前に「国語の宿題→数学のワーク→10分休憩」と、順番を決めるとスムーズに進めやすい。
- 小さな目標を設定する → 「10分だけ問題を解く」「英単語を5個だけ覚える」など、達成しやすい目標にすると取り組みやすくなる。
- 終わったら振り返る時間を作る → 「今日はここができたね」と成果を振り返ることで、次の勉強へのモチベーションが上がりやすい。
成功体験を増やす声かけをする
「勉強をやっても意味がない」と思ってしまうと、学習意欲が低下しがちです。
そのため、「できた!」という経験を積み重ねるための声かけが重要になります。
- できた部分をほめる → 「計算ミスが少なくなったね」「今日は集中して取り組めたね」と、結果だけでなく過程を認める。
- 「次はこうしてみよう」と提案する → うまくいかなかったときも、「次はこのやり方で試してみよう」と前向きな提案をすることで、挑戦する意欲を引き出せる。
- 「一緒にやってみよう」とサポートする → 自分ひとりではやる気が出ないときは、「じゃあ、最初の1問を一緒にやってみよう」と手を動かすきっかけを作る。
中学生本人ができる学習の工夫(セルフマネジメントの考え方)
発達障害のある中学生が学習を続けるためには、「自分に合ったやり方を見つけること」が重要です。
家庭や学校のサポートを受けながらも、自分で学習をコントロールする力(セルフマネジメント)を少しずつ身につけていくことが大切です。
自分に合った学習スタイルを知る
「この勉強法が合わない」と感じることがある場合は、自分に合った学習スタイルを見つけることが必要です。
- 音読しながら勉強すると集中しやすいなら、積極的に取り入れる
- 1人で勉強すると気が散るなら、親や友達と一緒に勉強する時間を作る
- 長時間は集中できないなら、短い時間で区切って勉強する
うまくいかないときの対処法を考える
「うまくいかないときにどうすればいいか」を決めておくと、学習を続けやすくなります。
- 勉強に集中できないときは、いったん体を動かしてリフレッシュする
- 問題がわからないときは、解答を見る前に「どこでつまずいたのか」を考えてみる
- 「今日は疲れた」と感じたら、休憩を取ってから短時間だけでも取り組む
学校や家庭のサポートがあることで、発達障害のある中学生が「勉強しやすい」と感じる場面が増えます。
「自分に合った学習方法を見つける」ための考え方

発達障害のある中学生が学習を進めるうえで大切なのは、「自分にとってやりやすい方法を見つけること」です。
一般的な勉強法が合わないこともありますが、それは「勉強ができない」ということではなく、自分に合った方法を知らないだけかもしれません。
学校の授業のスタイルや塾の指導方法が合わなくても、学び方を工夫すれば、理解しやすくなったり、集中しやすくなったりします。
ここでは、「どうすれば自分に合った学習方法を見つけられるか」を考えるヒントを紹介します。
「勉強がうまくいかない理由」を見つける
「勉強がうまくいかない」と感じるとき、何が原因なのかを考えることが大切です。
「計算ミスが多い」「覚えたはずの単語をすぐ忘れる」「問題文が長いと途中でわからなくなる」など、困っていることは人それぞれ違います。
まずは、次のような視点で「どこでつまずくのか」を整理してみましょう。
どんな場面で勉強が難しくなるのか?
- 授業中、先生の話を聞いているときに理解できないのか?
→ 先生の話が速くてついていけないのか、黒板の内容がうまくノートにまとめられないのか? - 宿題やワークをやるときに困るのか?
→ 問題の意味がわからないのか、それとも解き方が思い出せないのか? - テストになるとうまく解けないのか?
→ 覚えたはずのことを忘れてしまうのか、問題を読むのに時間がかかるのか?
このように、「勉強がうまくいかない」と感じる場面を具体的に整理することで、自分に合った対策を考えやすくなります。
「やりやすい勉強方法」を試してみる
「どうすればうまく勉強できるのか」は、実際にいくつかの方法を試してみないとわかりません。
苦手な勉強を「ただ頑張る」のではなく、少しでもやりやすい方法に工夫することが大切です。
学習スタイルを工夫してみる
勉強のやり方は1つではありません。
例えば、次のような工夫を試してみることで、「自分に合う勉強法」が見つかることがあります。
- 音読して覚える → 文字を読むのが苦手なら、音声を使って学習すると記憶しやすい。
- 図やイラストで整理する → 文章だけで理解しにくいなら、ノートに図を描いて情報を整理するとよい。
- 体を動かしながら覚える → じっと座っていると集中しにくいなら、歩きながら暗記をするのも方法のひとつ。
学習環境を変えてみる
「集中しにくい」と感じるなら、勉強する場所や時間を変えるだけで、取り組みやすくなることがあります。
- 静かな場所で勉強する → 周囲の音が気になるなら、図書館や学習スペースを活用する。
- 短時間で区切って勉強する → 30分続けて勉強するのが難しいなら、15分ごとに休憩を入れる。
- 家族と一緒に勉強する → ひとりだとやる気が出ないなら、親や兄弟と一緒に学習する時間を作る。
「できること」を増やして自信をつける
勉強がうまくいかないと、「自分はダメだ」と思ってしまいがちです。
でも、少しでも「できた!」という経験を積み重ねることで、自信を持って学習に取り組めるようになります。
小さな目標を設定する
「いきなり完璧にやろう」とすると、途中で疲れてしまったり、うまくいかないと落ち込んでしまうことがあります。
そこで、最初は小さな目標を立てて、少しずつ成功体験を積み重ねることが大切です
- 「1日10分だけ勉強する」と決める → 短時間でも「やった!」という感覚が得られる。
- 「英単語を5個だけ覚える」と決める → いきなり100個覚えようとせず、少しずつ増やしていく。
- 「計算ミスを1つでも減らす」と意識する → 完璧を目指すのではなく、少しずつ改善することを目標にする。
自分に合った「ごほうび」を決める
勉強を続けるモチベーションを上げるために、「頑張ったら◯◯する」と自分でごほうびを決めるのも効果的です。
- 「宿題が終わったら好きな動画を見る」
- 「テスト勉強を頑張ったら、週末に好きなものを食べる」
- 「計算問題を10問解いたら、5分だけゲームをする」
ただし、「ごほうびがないと勉強しない」という状態にならないように、最初は小さな目標に対して短時間のリフレッシュを取り入れる程度にするとよいでしょう。
自分に合った学習方法は、いろいろなやり方を試しながら見つけていくものです。
「この勉強法は合わなかったな」と思ったら、無理に続けるのではなく、別の方法を試してみるのも大切です。
- 「どこでつまずくのか?」を考えることで、解決策が見つかる
- 学習スタイルや環境を工夫することで、勉強がやりやすくなる
- 小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけていく
「今はうまくいかなくても、やり方を変えればできるようになるかもしれない」と考えながら、自分に合った学習方法を少しずつ見つけていきましょう。
まとめ
発達障害のある中学生にとって、勉強のしづらさを克服するには、「自分に合った学習方法を見つけること」と「学びやすい環境を整えること」が重要です。
授業についていくのが難しいと感じたら、学校でのサポートを相談し、家庭では学習計画の工夫や、適度な運動を取り入れることで集中しやすい環境をつくることができます。
また、学校の先生や支援者と連携しながら、専門的なアドバイスを受けることで、学習の負担を減らしやすくなります。
実際に行動するためには、まず「どの場面で勉強が難しくなるのか」を整理し、それに合った対策を試してみることが大切です。
例えば、文章問題が苦手なら「重要な部分にマークをつける」、計算ミスが多いなら「筆算のスペースを広くする」、暗記が苦手なら「音読しながら覚える」など、具体的な方法を少しずつ取り入れてみましょう。
学習スタイルや環境を変えながら試すことで、自分にとって最適な勉強方法が見つかりやすくなります。
「勉強が苦手」と感じるのは、努力が足りないからではなく、方法が合っていないだけかもしれません。
試行錯誤しながら学びやすい方法を見つけ、無理のないペースで続けていくことが大切です。
一度でうまくいかなくても、少しずつ改善しながら進めることで、勉強へのハードルが下がり、学ぶことが楽しく感じられるようになります。
自分に合った学習方法を見つけ、できることを増やしながら、自信を持って学びを深めていきましょう。
発達障害・グレーゾーン専門の
オンライン家庭教師のソウガク
発達障害・グレーゾーンのお子様の特性を理解しながら、スモールステップで自信をつけるオンライン家庭教師のソウガク。
お子様一人ひとりに合わせた学習・サポートプログラムをご用意しています。
ソウガクでは、発達障害に関する専門機関が授業をサポートし、適正な授業運営と教材の提案提供を行い、究極の個別対応を実施しています。






