中学生が陥りやすい「間違った勉強法」と正しい学び方の違いとは?

毎日机に向かっているのに、テストの点数が思うように伸びない。
そんな悩みを抱えている中学生は少なくありません。
実は、勉強しているのに成果が出ない原因の多くは「勉強のやり方」にあります。
この記事では、中学生が陥りがちな間違った勉強法と、成績を伸ばすために実践すべき正しい学び方について詳しく解説します。
自分の勉強方法を見直すきっかけにしてくださいね。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。
目次
勉強しても成績が上がらない理由とは?中学生がやりがちな間違った勉強法
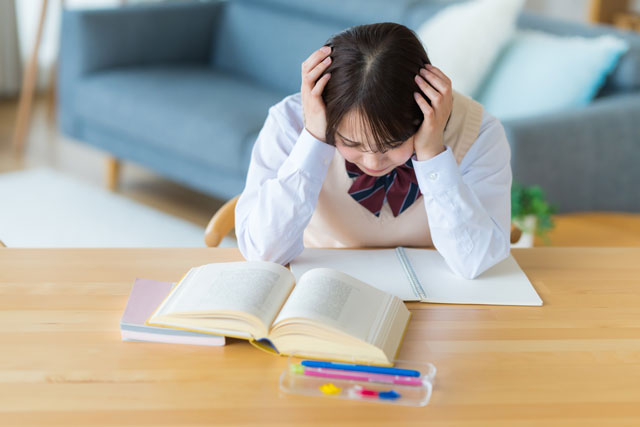
「毎日勉強しているのに成績が上がらない」と感じている中学生には、共通する勉強のやり方の問題点があります。
まずは、多くの中学生が陥りやすい間違った勉強法を5つ紹介します。
自分に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
ノートをきれいにまとめることが目的になっている
色ペンを何色も使い、定規で線を引いて、まるで美術作品のようなノートを作っている人はいませんか?
ノートを美しく仕上げることに時間をかけすぎて、肝心の内容理解がおろそかになってしまうのは本末転倒です。
ノートは「きれいに書くこと」が目的ではなく、「理解を深め、後で見返したときに思い出せること」が目的です。
見た目が整っていても、書いた内容が頭に入っていなければ、テストで点数を取ることはできません。
ノート作りに満足して勉強した気になってしまう状態は、勉強しても成績が上がらない中学生に非常に多い落とし穴です。
間違えた問題をそのまま放置している
問題集を解いて丸つけをしたとき、間違えた問題に赤ペンで正解を書き写して終わりにしていませんか?
これは非常にもったいない勉強法です。
間違えた問題こそ、あなたの弱点を教えてくれる貴重な情報源です。
なぜ間違えたのか、どこで考え方がずれたのかを確認しないまま次に進んでしまうと、同じミスを何度も繰り返すことになります。
復習不足は知識の定着を妨げる最大の原因です。
テストで「あれ、この問題見たことあるのに解けない」と感じるのは、間違えた問題をそのまま放置してきた結果かもしれません。
暗記中心で「理解」を後回しにしてしまう
教科書や参考書の内容をひたすら丸暗記しようとする勉強法も、効率が悪い方法の一つです。
確かに暗記は必要ですが、理解を伴わない暗記は、すぐに忘れてしまいます。
特に数学や理科のように、考え方や原理が大切な科目では、暗記だけに頼ると応用問題にまったく対応できなくなります。
「なぜそうなるのか」という理屈を理解せずに、公式や用語だけを覚えようとしても、問題の形式が少し変わっただけで解けなくなってしまうのです。
「長時間勉強=成果が出る」と思い込んでいる
「今日は5時間も勉強した!」と満足していても、その5時間の中身が薄ければ意味がありません。
長時間机に向かっていても、ぼんやり教科書を眺めているだけだったり、スマホをいじりながらだったりすれば、実際に集中して勉強した時間はほんのわずかです。
勉強時間の長さと成績の伸びは必ずしも比例しません。
大切なのは「どれだけ集中して、効率よく学んだか」という質の部分です。
ダラダラと長時間勉強するよりも、短時間でも集中して取り組む方が、はるかに効果的です。
スマホやテレビの誘惑で集中が続かない
勉強中にスマホの通知が気になって何度も確認してしまったり、テレビの音が聞こえてきて気が散ってしまったりすることはありませんか?
集中力が途切れるたびに、脳は再び集中状態に戻るまでに時間がかかります。
スマホやテレビなどの誘惑が多い環境で勉強していると、本来30分で終わる内容に1時間以上かかってしまうこともあります。
集中できない環境での勉強は、時間の無駄遣いになるだけでなく、勉強そのものを苦痛に感じる原因にもなります。
成績を伸ばす中学生が実践している「正しい勉強法」とは?

間違った勉強法を続けていても、成績は伸びません。では、実際に成績を伸ばしている中学生はどのような勉強法を実践しているのでしょうか?ここでは、効果的な勉強のコツを5つ紹介します。
「理解→演習→復習」の流れを意識して学ぶ
成績が伸びる中学生に共通しているのは、勉強に明確な流れがあることです。
その流れとは「理解→演習→復習」のサイクルです。
まず、教科書や授業で新しい内容を「理解」します。
次に、問題集やワークで実際に問題を解いて「演習」します。
そして、間違えた問題や理解が不十分だった箇所を「復習」して定着させます。
この3つのステップを繰り返すことで、知識が確実に身についていきます。
多くの場合、成績が伸び悩む原因は「理解」や「復習」が不足していることにあります。
演習だけをひたすら繰り返しても、土台となる理解がなければ応用力は育ちません。
正しい勉強法とは、この3つのステップをバランスよく組み合わせることなのです。
目的を明確にしてから勉強を始める
「とりあえず勉強する」という曖昧な姿勢ではなく、「今日は英単語を20個覚える」「数学の連立方程式を完璧にする」など、具体的な目標を設定してから勉強を始めましょう。
目的が明確になると、やるべきことがはっきりするため、集中力も高まります。
また、目標を達成したときに「今日はこれができた」という達成感を得られるため、勉強を続けるモチベーションにもつながります。
目標は大きすぎず、その日のうちに達成できる小さなものにするのがポイントです。
「定期テストで450点を取る」という大きな目標も大切ですが、それを実現するためには、日々の小さな目標の積み重ねが必要です。
間違いノートを活用して弱点を克服する
成績を伸ばす中学生の多くが実践しているのが「間違いノート」です。
間違いノートとは、自分が間違えた問題や理解できなかった内容をまとめたノートのことです。
間違いノートを作るときのポイントは、ただ問題と答えを写すのではなく、「なぜ間違えたのか」「正しい考え方は何か」を自分の言葉で書き込むことです。
こうすることで、同じミスを繰り返さなくなります。
テスト前には、この間違いノートを重点的に見直すことで、効率よく弱点を補強できます。
新しい問題集に手を出すよりも、自分が実際に間違えた問題を復習する方が、はるかに効果的です。
短時間集中で勉強リズムを作る
人間の集中力は、一般的に45分から90分程度が限界だと言われています。
それ以上長く続けようとすると、集中力が途切れて効率が落ちてしまいます。
おすすめの方法は、25分勉強して5分休憩するというサイクルを繰り返す方法や、45分勉強して10分休憩するというリズムです。
休憩時間には軽くストレッチをしたり、水を飲んだりして、脳をリフレッシュさせましょう。
短時間でも集中して取り組むことで、ダラダラと長時間勉強するよりも多くのことを学べます。
この「短時間集中」のリズムを習慣化することが、効率的な勉強法の基本です。
「復習のタイミング」を意識して記憶を定着させる
人間の脳は、一度覚えたことでも時間が経つと忘れてしまいます。
これを防ぐために重要なのが、適切なタイミングでの復習です。
記憶を定着させるためには、学んだ当日、翌日、1週間後、1か月後というように、間隔を空けて繰り返し復習することが効果的です。
このように計画的に復習することで、長期記憶として定着し、テスト本番でもスムーズに思い出せるようになります。
「一度覚えたから大丈夫」と安心せず、定期的に復習する習慣をつけることが、正しい勉強法の重要なポイントです。
教科別に見直そう!間違いやすい勉強のやり方と改善ポイント

勉強法は教科によっても異なります。
ここでは、主要教科ごとによくある間違いと、効果的な勉強のやり方を紹介します。
英語|単語暗記だけで終わらせない。文法と音読で理解を深めよう
英語の勉強といえば「単語を覚えること」と考えている人は多いかもしれませんね。
確かに単語は大切ですが、単語だけを覚えても英語の力は十分につきません。
英語力を伸ばすには、文法の理解と音読の練習が欠かせません。
文法を理解することで、文章の構造が見えるようになり、長文読解がスムーズになります。
また、音読を繰り返すことで、英語のリズムや語順が体に染み込み、自然と英文が読めるようになります。
効果的な英語の勉強法
- 単語は文章の中で覚える(例文と一緒に覚えると記憶に残りやすい)
- 文法は「なぜその順番になるのか」を理解する
- 教科書の本文を何度も音読する
- 間違えた問題は、正しい英文を声に出して読む
単語帳をただ眺めるのではなく、実際に声に出して読んだり、文章の中でどう使われているかを確認したりすることが、英語力向上の近道です。
数学|解き方を覚えるのではなく「考え方」を理解する
数学が苦手な中学生に多いのが、「解き方を丸暗記しようとする」という間違った勉強法です。
例題の解き方をそのまま暗記しても、問題の数字や設定が変わると対応できなくなってしまいます。
数学で大切なのは、「なぜこの解き方をするのか」という考え方を理解することです。
公式を覚えることも必要ですが、その公式がどのような場面で使えるのか、なぜその式が成り立つのかを理解しておくと、応用問題にも対応できるようになります。
効果的な数学の勉強法
- 公式は丸暗記せず、導き方を理解する
- 問題を解くときは「なぜこの方法を使うのか」を考える
- 間違えた問題は、解説を読んで考え方を理解してから解き直す
- 似たような問題を複数解いて、パターンを体で覚える
数学の勉強法は、単に答えを出すことではなく、「どう考えれば答えにたどり着けるか」というプロセスを大切にすることです。
国語|問題文をなんとなく読むだけになっていない?根拠を意識しよう
国語は「感覚で解ける」と思っている人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
国語の読解問題には、必ず本文中に答えの根拠があります。
なんとなく「これが正解っぽい」と選んでいる人は、根拠を探す習慣をつけましょう。
「なぜこの答えを選んだのか」を説明できるようになると、確実に点数が伸びます。
効果的な国語の勉強法
- 問題を解く前に、設問が何を聞いているのかを正確に把握する
- 答えを選ぶときは、必ず本文中の該当箇所に線を引く
- 「なぜその答えになるのか」を自分で説明できるようにする
- 記述問題では、本文の言葉を使いながら答えをまとめる
国語は感覚ではなく、論理的に考える科目です。
根拠を意識することで、安定して高得点を取れるようになります。
理科・社会|丸暗記ではなく、因果関係を意識して覚える
理科や社会は暗記科目と思われがちですが、ただ用語や年号を覚えるだけでは、テストで点数を取ることは難しくなっています。
最近のテストでは、「なぜそうなるのか」を問う問題が増えているからです。
理科では、実験の結果だけでなく「なぜそうなったのか」という理由を理解することが大切です。
社会では、歴史の出来事を年号で覚えるだけでなく、「なぜその出来事が起きたのか」「その結果どうなったのか」という流れを理解しましょう。
効果的な理科・社会の勉強法
- 用語を覚えるときは、意味や背景も一緒に理解する
- 理科は実験の手順だけでなく、「なぜそうするのか」を考える
- 歴史は出来事を時系列で整理し、因果関係を意識する
- 地理は地図や資料を見ながら、視覚的に理解する
丸暗記ではなく、「理解して覚える」ことを意識すると、記憶に残りやすくなり、応用問題にも対応できるようになります。
やる気が続かない中学生に多い「勉強の落とし穴」

勉強法が正しくても、やる気が続かなければ成績は伸びません。
ここでは、中学生がやる気を失ってしまう原因と、その対処法について考えてみましょう。
「完璧にやらなければ」と思いすぎて疲れてしまう
真面目な中学生ほど陥りやすいのが、「完璧主義」の罠です。
「すべての問題を完璧に解けるようにならなければ」「ノートは一字一句間違えずに書かなければ」と考えすぎると、勉強がとても苦しいものになってしまいます。
完璧を目指すあまり、少しでもミスをすると「自分はダメだ」と落ち込んでしまい、やる気を失ってしまうのです。
勉強は完璧にできなくても大丈夫です。
間違えながら少しずつ成長していくプロセスこそが、本当の学びです。
完璧主義から抜け出すために
- 「できたこと」に目を向ける習慣をつける
- 間違いは「成長のチャンス」だと考える
- 100点を目指すのではなく、「前回より1点でも上げる」ことを目標にする
完璧を求めすぎず、自分のペースで少しずつ進むことが、長く勉強を続けるコツです。
結果ばかり気にして「過程」を見直していない
「テストで何点取れたか」という結果だけを気にしていると、点数が悪かったときに大きく落ち込んでしまいます。
結果も大切ですが、それ以上に大切なのは「どのように勉強したか」という過程です。
結果が出なかったとき、「自分には才能がない」と諦めるのではなく、「勉強のやり方に問題があったのかもしれない」と考えてみましょう。
勉強の過程を見直すことで、次回に活かせる改善点が見つかります。
過程を大切にするために
- テスト後は点数だけでなく、間違えた理由を分析する
- 「今日はここまでできた」と、日々の小さな進歩を記録する
- 結果が悪くても、努力したプロセスを認めてあげる
過程を大切にすることで、たとえ結果が伴わなくても、次に向けて前向きに進むことができます。
勉強の目的が曖昧でモチベーションが続かない
「なぜ勉強するのか」が分からないまま机に向かっていても、やる気は続きません。
「親に言われたから」「テストがあるから」という受け身の理由だけでは、モチベーションを保つのは難しいでしょう。
自分なりの勉強の目的を見つけることが大切です。
「志望校に合格したい」「将来やりたい仕事のために必要」「この科目が好きだから」など、どんな理由でも構いません。自分が納得できる目的があると、勉強への意欲が自然と湧いてきます。
勉強の目的を見つけるために
- 将来の夢や興味のあることを考えてみる
- 好きな科目や得意な分野から勉強を始めてみる
- 「この勉強が将来どう役立つか」を想像してみる
目的が明確になると、勉強そのものが楽しくなり、自然と続けられるようになります。
親や先生の期待にプレッシャーを感じている
「親に期待されている」「先生に褒められたい」という気持ちは、勉強の原動力になることもあります。
しかし、それがプレッシャーになりすぎると、勉強が苦しいものになってしまいます。
周りの期待に応えることも大切ですが、一番大切なのは自分自身の成長です。
他人の期待ではなく、「自分はどうなりたいのか」を考えることが、健全なやる気を生み出します。
プレッシャーを軽くするために
- 親や先生に、自分の気持ちや悩みを正直に話してみる
- 「誰かのため」ではなく「自分のため」に勉強していることを意識する
- 完璧でなくても、努力している自分を認めてあげる
プレッシャーを感じたときは、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することも大切です。
集中力が続かない中学生必見!集中できる環境と習慣の作り方

勉強しようと思っても、なかなか集中できないという悩みを持つ中学生は多いでしょう。
集中力は才能ではなく、環境と習慣によって高めることができます。
勉強時間を区切ることで集中を維持する
長時間ずっと集中し続けることは、誰にとっても難しいことです。
集中力を維持するコツは、時間を区切って勉強することです。
例えば、「25分勉強して5分休憩」というサイクルを繰り返す方法があります。
短い時間で区切ることで、「あと25分だけ頑張ろう」と思えるため、集中しやすくなります。
タイマーを使って時間を測ると、より効果的です。
時間管理のポイント
- タイマーやスマホのアラームを活用する
- 休憩時間は本当に休む(スマホを見すぎない)
- 一つの教科を長時間続けず、教科を変えることでリフレッシュする
時間を区切ることで、メリハリのある効率的な勉強ができるようになります。
勉強する場所を決めて「勉強モード」を作る
「この場所に来たら勉強する」という習慣を作ると、自然と集中できるようになります。
自分の部屋の机、リビングの特定の席、図書館など、勉強する場所を決めましょう。
大切なのは、その場所では勉強以外のことをしないことです。
勉強する場所で遊んだりスマホをいじったりすると、脳が「ここは遊ぶ場所」と認識してしまい、集中しにくくなります。
勉強に適した環境の作り方
- 机の上は勉強に必要なものだけを置く
- スマホやゲーム機は視界に入らない場所に置く
- 適度な明るさと静かさを保つ
- 室温は少し涼しめ(20〜22度程度)に設定する
環境を整えるだけで、集中力は大きく変わります。
勉強モードに入るための自分なりの場所を見つけましょう。
スマホの通知・音を完全にオフにする
勉強中にスマホの通知が来ると、集中力が途切れてしまいます。
「ちょっとだけ」と思って見始めると、気づけば10分、20分と時間が経ってしまうこともあります。
勉強中はスマホを完全にオフにするか、別の部屋に置いておくのが理想的です。
どうしても手元に置きたい場合は、機内モードにするか、通知を完全にオフにしましょう。
スマホとの上手な付き合い方
- 勉強時間中はスマホを別の部屋に置く
- タイマーとして使う場合は、機内モードにする
- 勉強後のご褒美として、決めた時間だけスマホを使う
スマホを遠ざけることで、驚くほど集中できるようになります。
最初はつらいかもしれませんが、慣れると勉強の効率が格段に上がります。
短時間でも達成感を感じる仕組みを作る
集中力を維持するためには、達成感を感じることが重要です。
「今日はこれができた」という小さな成功体験が、次の勉強へのやる気につながります。
おすすめの方法は、勉強した内容や時間を記録することです。
ノートに「今日やったこと」を書いたり、カレンダーに勉強した日を印をつけたりすると、自分の努力が目に見える形で残り、達成感が得られます。
達成感を生む工夫
- 小さな目標を設定し、達成したらチェックマークをつける
- 勉強した内容を記録するノートを作る
- 一週間ごとに振り返り、「できたこと」を確認する
短時間でも「今日も頑張った」と思えることが、勉強を続ける力になります。
正しい勉強法を身につけると成績が変わる!中学生に伝えたい3つのポイント

ここまで、間違った勉強法と正しい勉強法について詳しく見てきました。
最後に、これだけは覚えておいてほしい大切なポイントを3つにまとめます。
勉強時間よりも「質」を重視する
何時間勉強したかよりも、どれだけ集中して効率よく学んだかの方が重要です。
ダラダラと5時間机に向かうよりも、集中して2時間勉強する方が、はるかに多くのことを吸収できます。
勉強の質を高めるためには、目的を明確にし、集中できる環境を整え、適切なタイミングで休憩を取ることが大切です。
「今日は何時間勉強した」ではなく、「今日は何を理解できた」と考えるようにしましょう。
短時間でも質の高い勉強を続けることで、確実に成績は伸びていきます。
時間の長さではなく、内容の濃さを意識することが、効率的な勉強法の基本です。
間違いを「次に活かす」姿勢が伸びる人の共通点
成績が伸びる中学生と伸び悩む中学生の最大の違いは、間違いに対する姿勢です。
間違いを「失敗」と捉えて落ち込むのではなく、「成長のチャンス」と捉えて次に活かせる人が、確実に成績を伸ばしています。
間違えた問題は、あなたの弱点を教えてくれる大切な情報です。
間違いから目を背けず、「なぜ間違えたのか」をしっかり分析し、同じミスを繰り返さないようにする。
この積み重ねが、実力を確実に伸ばします。
テストで間違えた問題こそ、あなたを成長させる最高の教材です。
間違いを恐れず、むしろ間違いから学ぶ姿勢を持ちましょう。
小さな成功体験が勉強の継続力を生む
勉強を続けるためには、「自分はできる」という自信が必要です。
その自信は、小さな成功体験の積み重ねから生まれます。
「今日は英単語を10個覚えられた」「数学の問題が前より早く解けるようになった」「テストで前回より10点上がった」など、どんなに小さなことでも構いません。
自分の成長を認めて、自分を褒めてあげることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、「もっと頑張ろう」という前向きな気持ちが生まれ、勉強を続ける力になります。
完璧を目指すのではなく、昨日の自分より少しでも成長することを目指しましょう。
まとめ
勉強しても成績が上がらない原因の多くは、勉強法そのものに問題があります。
ノートをきれいにまとめることに時間をかけすぎたり、間違えた問題を放置したり、長時間勉強すれば成果が出ると思い込んだりする間違った勉強法では、どれだけ時間をかけても効果は薄いでしょう。
正しい勉強法とは、「理解→演習→復習」の流れを意識し、目的を明確にし、間違いから学ぶ姿勢を持つことです。
勉強時間の長さではなく質を重視し、短時間でも集中して取り組むことで、効率よく成績を伸ばすことができます。
また、教科ごとに適した勉強法があることも忘れてはいけません。
英語なら音読と文法理解、数学なら考え方の理解、国語なら根拠を探す習慣、理科・社会なら因果関係を意識した学習が効果的です。
自分の勉強法を教科ごとに見直してみましょう。
やる気が続かないときや集中できないときは、完璧を求めすぎていないか、勉強の目的が明確になっているか、環境は整っているかを確認してください。
小さな目標を設定し、達成感を感じながら進むことで、勉強を続ける力が自然と育っていきます。
間違った勉強法を続けていても、成果は出ません。
しかし、正しい勉強法を身につければ、必ず成績は変わります。
今日から自分の勉強法を見直し、一つずつ改善していきましょう。
大切なのは、完璧にやることではなく、昨日の自分より少しでも成長することです。
この記事で紹介した方法を参考に、自分に合った勉強法を見つけて、着実に力をつけていってくださいね。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。






