【中学生】国語テストを完全攻略!長文読解で高得点を取るためのスキルとワザを徹底解説
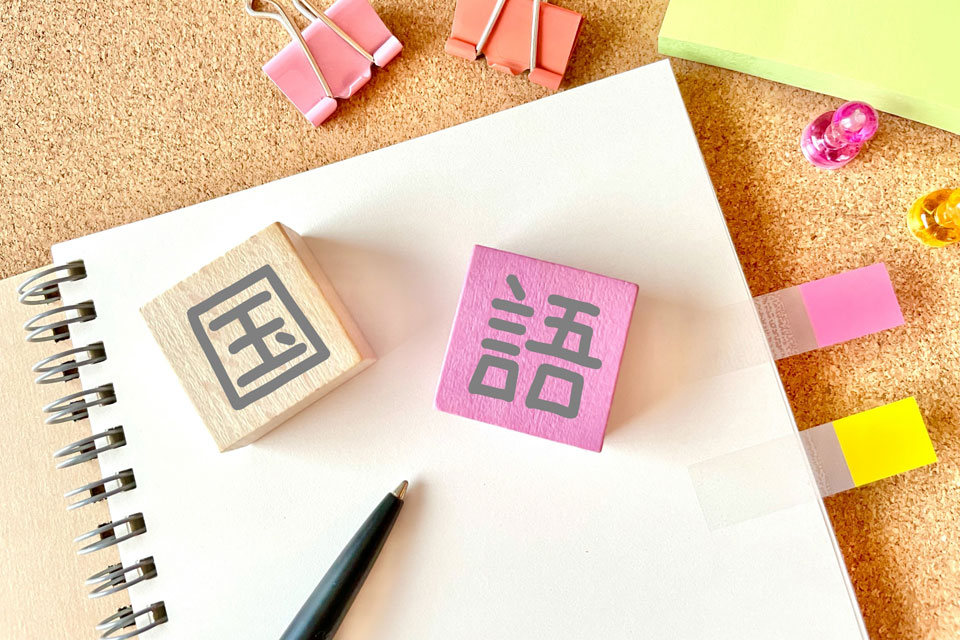
国語のテストで「読めているはずなのに点が取れない」と感じたことはありませんか?
特に長文読解では、本文をしっかり読んでも設問の意図を外してしまったり、記述問題で減点されたりと、得点に結びつかないケースが多く見られます。
国語の長文読解は、「なんとなく読めば解ける」科目ではありません。
限られた時間の中で、出題者が何を求めているのかを読み取り、その意図に沿った形で答えをまとめる「解く力」と「整える力」が必要です。
この記事では、中学生が国語の長文読解テストで確実に得点を伸ばすための具体的なスキルとワザを、今すぐ実践できる形で詳しく解説します。
「読む力」だけでなく、「設問を見抜く力」「答案を仕上げる力」を身につけることで、安定して高得点を取ることができるようになります。
保護者の方も、お子さんがどのような手順で長文問題に取り組めばよいかを理解することで、家庭でのサポートがより効果的に行えるようになることでしょう。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。
目次
はじめに|国語テストを「攻略」するために必要な発想とは?
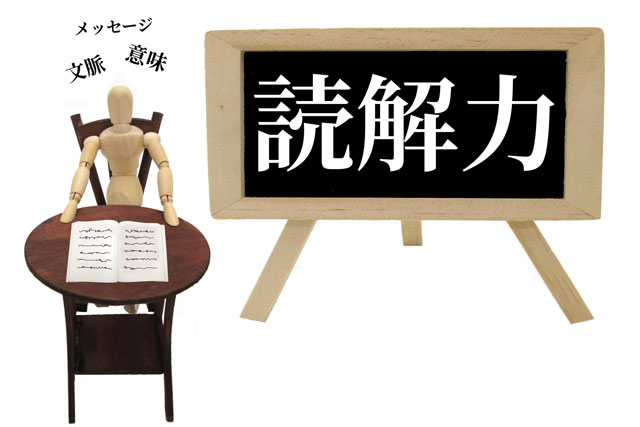
国語のテストで安定して高得点を取るには、「文章が読める」だけでは足りません。
限られた時間の中で設問の意図を正確に見抜き、減点されない答え方を身につけることが重要です。
「読む力」だけでなく「解く力」「整える力」を分けて鍛える
国語の得点力は、大きく3つの力に分けられます。
1つ目は「読む力」、本文の内容を理解し筆者の主張や登場人物の心情をつかむ力です。
2つ目は「解く力」、設問が何を求めているのかを見抜き、本文のどこに答えがあるのかを特定する力です。
そして3つ目は「整える力」、自分の言葉で答えをまとめ、減点されない形に仕上げる力です。
多くの中学生は「読む力」だけに意識が向きがちですが、実際のテストでは「解く力」と「整える力」が得点を左右します。
この3つの力を分けて意識し、それぞれに対応した練習を積むことで、国語テストの得点は確実に伸びていきます。
テストは準備で7割決まる:設問→本文→答案の順序設計
国語テストで高得点を取る生徒には、共通したパターンがあります。
それは「解く順序」が決まっているということです。
まず、問題用紙を開いたら、いきなり本文を読むのではなく、最初に設問をざっと確認します。
設問を先に読むことで、「何を聞かれるのか」という読みの目的が明確になり、本文を読む際の効率が格段に上がります。
次に本文を読みながら、設問に関係しそうな部分に印をつけていきます。
そして設問に答える段階では、本文の該当箇所を確認しながら、減点されない形で答案を仕上げます。
この「設問→本文→答案」という順序を意識するだけで、時間配分がスムーズになり、解答の精度も高まります。
今日から始める:小さな型を積み重ねる練習法
国語のテスト対策は、難しい参考書を読むことではありません。
むしろ、日々の小さな練習の積み重ねが大切です。
教科書の文章を読むときに「この段落は何を説明しているのか」を一行でメモする習慣をつける、設問を見たら「どの段落に答えがありそうか」を予測してから本文を読む、記述問題では「結論→理由」の順で書く型を毎回使う、といった具体的な行動です。
こうした小さな型を繰り返し使うことで、テスト本番でも自然に体が動くようになります。
ステップ1:読む前に勝負が決まる! 設問チェックと時間配分のワザ

国語テストの最初の1〜2分で、その後の「戦い方」が大きく変わります。
設問の並びや字数制限、記述問題の有無などを把握し、時間配分と解答順を即座に決めましょう。
設問を先に読むメリットと注意点
設問を先に読むことの最大のメリットは、本文を読む目的が明確になることです。
例えば、「筆者の主張を述べよ」という設問があれば、本文を読むときに「どこが主張なのか」を意識しながら読むことができます。
ただし、設問の内容に引きずられて、本文全体の流れをつかめなくなるケースがあります。
設問は確認するだけにとどめ、本文はていねいに読むことを忘れないようにしましょう。
設問先読みでチェックすべき4つのポイント
- 主題や要旨を問う問題があるか
- 心情や理由を説明する記述問題はあるか
- 抜き出し・選択問題の数と配点を確認
- 字数制限付きの記述問題の有無を把握
問題文を読む前にチェックすべき3つのポイント
テスト用紙を開いたら、まず設問数、配点と字数、ジャンル(説明文・文学)を確認します。
記述問題の配点が高ければ、その問題に時間をかける価値があります。
また、80字以上の記述があれば、それだけで5分以上かかることを想定しておきます。
時間を使いすぎないための「読むリズム」の作り方
50分のテストなら、本文を読むのに10〜15分、設問に答えるのに30〜35分、見直しに5分という配分が目安です。本文を読むのは12分以内と決め、段落ごとの要点を右余白にメモし、重要な接続語や対比表現に印をつけます。
記述問題は1問あたり5〜8分を目安に、選択問題や抜き出し問題はテンポよく進めます。
ステップ2:本文を読むスキル|「出題者の意図」を見抜く読み方
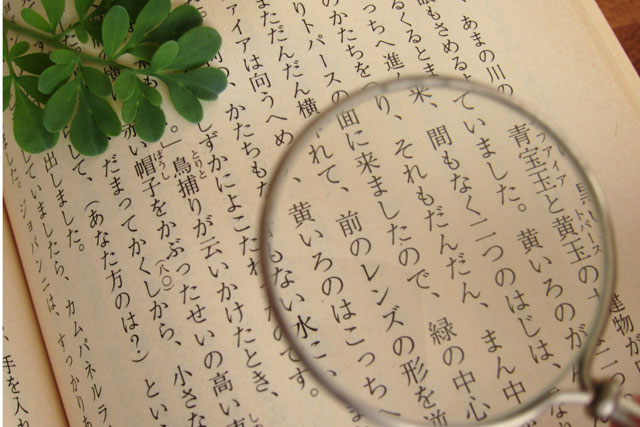
同じ文章を読んでも、読み方ひとつで正答率は大きく変わります。
段落の役割、接続語、指示語、強調表現から、設問になりやすい論点を先取りして読みましょう。
段落の役割を意識して読む
文章は、いくつかの段落が役割を分担して構成されています。
導入部分では話題やテーマが示され、展開部分では具体例や理由が説明され、対比部分では異なる立場や考え方が示され、結論部分では筆者の主張がまとめられます。
導入部分では「〜について考えてみたい」、展開部分では「例えば」「具体的には」、対比部分では「しかし」「一方で」、結論部分では「つまり」「このように」といった表現に注目します。
これらのサインを見つけながら読むと、設問に答えるときに迷いません。
接続語・指示語で文の関係をつかむ
接続語と指示語は、文と文、段落と段落をつなぐ重要な役割を果たします。
「しかし」「一方で」は対比や転換を示し、「つまり」「すなわち」は言い換えや要約を示し、「そのため」「だから」は因果関係を示します。
「これ」「その」といった指示語は、直前の内容を受けています。
これらの言葉に丸をつけたり、矢印で関係を示したりしながら読むと、答えの位置が自然と見えてきます。
筆者の主張・対比・理由の見抜き方
筆者の主張は、結論部分や「〜べきだ」「〜と考える」といった表現の近くにある場合が多くあります。
また、対比構造がある文章では、「AではなくB」「従来は〜だったが、今は〜」といった形で、筆者の立場が明確になります。
これらの部分に線を引いておくと、主題問題や選択問題で迷わずに済みます。
練習法:要点マーク&一行メモを活用しよう
本文を読むときは、右余白に一行メモを残す習慣をつけましょう。
例えば、「導入:問題提起」「対比:従来vs新しい」「結論:筆者の主張」といった短いメモです。
この一行メモは、設問に答えるときの道しるべになります。
ステップ3:設問攻略のコツ|タイプ別「得点アップの技」

設問にはパターンがあります。
タイプごとの「見る場所」「答えの型」「よくある誤答」を押さえるほど、得点は安定していきます。
主題・要旨問題の攻略法
主題・要旨問題の答えは、多くの場合、結論部分にあります。
具体的には、最後の段落や「つまり」「このように」といった接続語の後ろです。
導入部分で示された問題意識と、結論部分で示された筆者の答えを組み合わせると、より完成度の高い答えになります。
よくある誤答パターンは、具体例の内容を答えてしまうことです。
主題はあくまで「筆者の主張」であり、具体例はそれを裏付けるための材料にすぎません。
心情問題の読み取り方
心情を読み取るには、まず登場人物の行動や描写に注目します。
例えば、「うつむいた」「声が震えた」「手を握りしめた」などといった表現です。
これらの行動から、その感情を表す言葉を考えます。
心情を読み取る手がかりは、地の文、会話文、情景描写の3つに分かれています。
地の文では登場人物の内面が直接描かれ、会話文では言葉の裏にある感情を読み取り、情景描写では天気や時間帯が登場人物の心情を象徴していることがあります。
理由説明・因果関係問題の答え方
理由説明問題の答えは、「結論→理由→根拠」の順で書くと、減点されにくくなります。
例えば、「筆者が読書を勧めるのはなぜか」という設問なら、「読書を勧めるのは、読書が想像力を育てるからだ。筆者は、本を読むことで多様な視点を学べると述べている」という形です。
抜き出し問題・語句選択問題のコツ
抜き出し問題では、指定された字数や条件に合う部分を本文から探します。
前後の文とつながりがおかしくないか、文法的に正しいかを確認しましょう。
語句選択問題では、指示語の指し先を正確に特定することが重要です。
ステップ4:記述問題で差をつける! 部分点を確実に取る書き方

記述問題は配点が高く、国語テストの得点を大きく左右します。
満点を狙うより、部分点を確実に取る設計で答案を作ることが、高得点への近道です。
「理由+根拠+結論」で書く3文構成
記述問題の答えは、理由、根拠、結論の3つの要素で構成します。
下の表を参考に、字数に応じて配分をイメージしましょう。
| 記述の長さ | 結論 | 理由 | 根拠 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 60字程度 | 約20字 | 約30字 | 約10字 | 60字 |
| 80字程度 | 約25字 | 約35字 | 約20字 | 80字 |
| 100字程度 | 約30字 | 約40字 | 約30字 | 100字 |
この配分を意識すると、どの長さの記述でも構成のバランスが整い、減点を防げます。
文末表現を整えて減点を防ぐ
文末は、設問の形式に合わせて使い分けます。
理由を問う設問なら「〜からだ」「〜ためだ」、内容を説明する設問なら「〜といえる」「〜ということだ」、筆者の考えを述べる設問なら「〜と考えられる」「〜と主張している」といった形です。
文末をきちんと整えるだけで、答案の印象が大きく変わり、部分点がもらいやすくなります。
字数制限に合わせてまとめるコツ
字数が超えた場合は、装飾的な表現、重複している内容、言い換えで短くできる部分の順で削ります。
「非常に」「とても」といった副詞は、なくても意味が通る場合が多いでしょう。
逆に、字数が足りない場合は、結論、理由、根拠の順で内容を追加します。
模範解答を真似しないほうがいい理由
模範解答をそのまま真似しようとするのは、あまり効果的ではありません。
模範解答は採点者が作った「理想の答え」であり、生徒が本番で書くべき答えとは少し違います。
「結論→理由→根拠」という型を守り、自分の言葉で整合性のある答えを書くことのほうが、部分点を確実に取れます。
採点者は、模範解答と同じ表現かどうかではなく、「設問に答えているか」「本文の内容を踏まえているか」「論理的に筋が通っているか」を評価します。
ステップ5:選択問題の落とし穴を避ける! 判断力のスキル
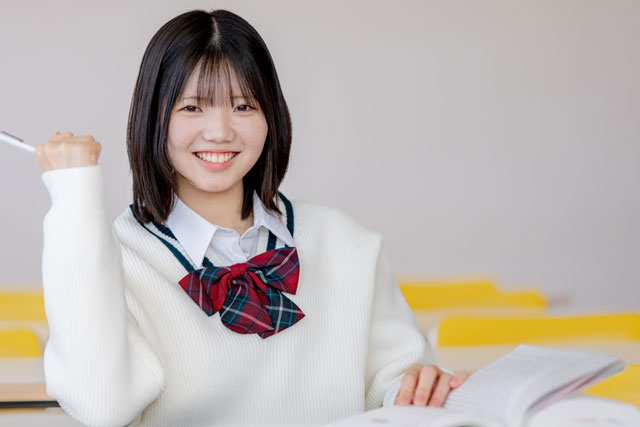
選択問題は、理解していても誤答が出やすい問題です。
その理由は、選択肢の作り方に罠があるからです。
典型的な落とし穴を先に知り、消去法を構造化することで、正答率を高めましょう。
似た選択肢の見分け方
似た選択肢の違いは、多くの場合、数語の差にあります。
「必ず」「絶対に」「すべて」といった極端な表現が入っている選択肢は、誤答であることが多いです。
また、「〜と思われる」「〜かもしれない」といった主観的な表現が入っている選択肢も注意が必要です。
本文で断定されていることが、選択肢では推測の形になっていたら、誤答の可能性があります。
「正しいけどズレている」選択肢を見抜く視点
選択問題で最も厄介なのは、「内容は正しいけれど、設問の答えとしてはズレている」選択肢です。
このタイプの誤答を避けるには、論点のズレ、時間軸のズレ、主語のズレに注意します。
設問が「筆者の主張」を問うているのに、選択肢が「具体例の内容」を述べていたら論点のズレ、設問が「現在の状況」を問うているのに、選択肢が「過去の状況」を述べていたら時間軸のズレ、設問が「筆者の考え」を問うているのに、選択肢が「一般的な意見」を述べていたら主語のズレです。
接続語・代名詞・主語一致のチェック
本文で「しかし」という逆接の接続語が使われているのに、選択肢で「そのため」という順接の接続語が使われていたら、それは誤りです。
代名詞の照応、主語と述語の一致も確認しましょう。
根拠を1文で特定する練習法
選択問題で迷ったときは、必ず本文に戻って根拠を確認します。
本文を読みながら重要な文に線を引き、設問を読んで答えがありそうな段落を予測し、予測した段落の中で設問の答えに直接関係する文を1文に絞り込みます。
その1文の内容と選択肢を照らし合わせて、最も一致するものを選びます。
ステップ6:本番で使える「高得点ワザ」まとめ

ここまで紹介した技術を、テスト本番でスムーズに使うためには、手順の固定化と見直しの型が重要です。
見直しでやるべきチェックリスト
テストの最後の5分で次のポイントをチェックすると、ケアレスミスによる減点を防げます。
国語テストの最終チェックリスト(5分で確認!)
- 記号の記入ミス:番号・記号の位置ズレを確認
- 助詞の誤り:「が/を」「に/へ」などの入れ替わりを防ぐ
- 接続詞の使い方:「しかし」「だから」など論理の流れが自然か
- 主語と述語の対応:文章全体で一貫しているか
- 字数制限:指定の範囲を超えていないか
- 禁則チェック:行頭の句読点や記号の抜けがないか
焦りを防ぐための順序決めスキル
解答順をあらかじめ決めておくと、焦りを大幅に減らせます。
例えば、抜き出し問題や語句選択問題など短時間で確実に得点できる問題から解き、次に選択問題、最後に記述問題という順序です。
この順序は、自分の得意不得意に合わせて調整できます。
大切なのは、普段から同じ順序で解く練習をして、本番でも迷わずに進められる状態を作ることです。
「わからない問題」に出会った時の対応法
わからない問題に出会ったら、無理に答えを出そうとせず、いったん保留します。
ただし、「答えがありそうな段落」だけをメモしておきます。
例えば、問題用紙の余白に「問5→第3段落」とメモしておくのです。
ほかの問題を解いているうちに、本文の理解が深まり、保留した問題の答えが見えてくることがよくあります。
まとめ
国語のテストで高得点を取るには、「読む力」だけでなく「解く力」と「整える力」をバランスよく鍛えることが大切です。
この記事で紹介した技術は、どれも明日からすぐに使えるものばかりです。
まずは、設問を先に確認して時間配分を決めること、本文を読むときに段落の役割や接続語に印をつけること、記述問題では「結論→理由→根拠」の型で書くこと――この3つから始めてみてください。
普段の問題演習で繰り返し使うことで、テスト本番でも自然に体が動くようになります。
国語テストは、才能ではなく技術で得点が伸びる科目です。
正しい手順と型を身につければ、誰でも安定して高得点を取れるようになります。
今日から一つずつ、小さな型を積み重ねていきましょう。
そして次のテストで、その成果を実感してくださいね。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。






