脱・丸暗記!中学生のための「理解が深まるノート術」と情報整理の方法
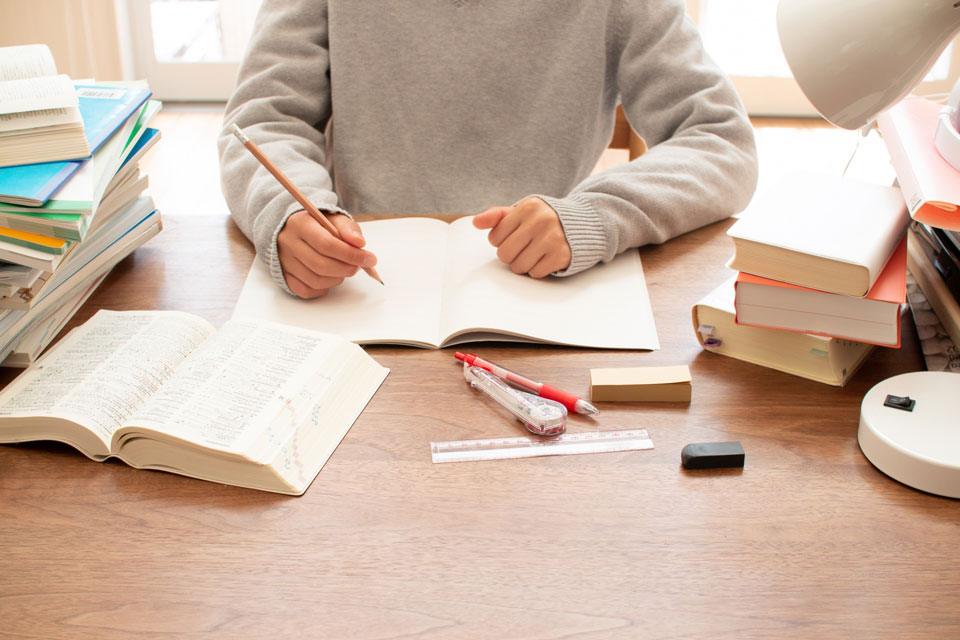
テスト前に必死に暗記して、テストが終わったら全部忘れてしまう。
そんな経験、みなさんにもあるかもしれませんね。
一夜漬けで詰め込んだ知識は、まるで砂のように指の間からこぼれ落ちていきます。
それなのに、また次のテストでも同じことを繰り返してしまうのです。
実は、この「丸暗記の落とし穴」にはまっている中学生はとても多いのです。
小学校までは暗記だけでもなんとかなったかもしれません。
でも中学校に入ると、覚える量が一気に増えるし、応用問題も出てきます。
丸暗記だけではもう太刀打ちできなくなってしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
答えは「理解すること」にあります。
そして、その理解を助けてくれる強力な味方が「ノート」なのです。
ノートは単なる板書の写しではありません。
自分の思考を整理し、記憶を定着させ、理解を深めるための道具なのです。
この記事では、丸暗記から脱却して、本当に使えるノートの取り方と情報整理法を紹介していきます。
勉強の質を変えたいと思っている人に、ぜひ読んで参考にしていただければと思います。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。
目次
丸暗記では成績が伸びない理由
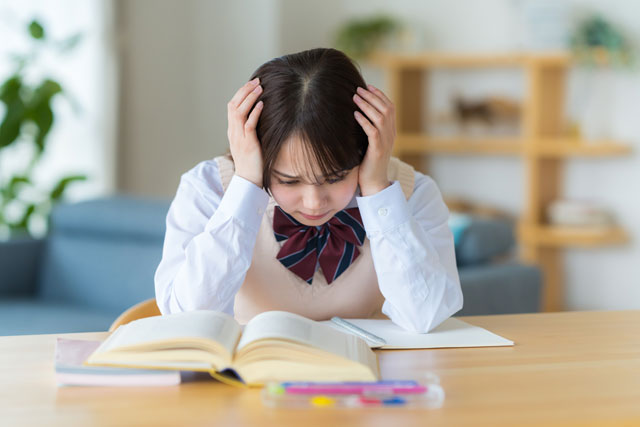
「とにかく覚えれば点数が取れる」——そう思ってひたすら暗記している人も多いでしょう。
ですが、実際にはそれだけでは成績は頭打ちになってしまいます。
なぜなのか、その理由を探ってみましょう。
覚えたつもりがテストで思い出せない原因
一生懸命覚えたはずなのに、テストになると思い出せない。
この現象には明確な理由があります。
丸暗記というのは、情報を「点」として記憶しようとする方法です。
例えば、歴史の年号を「1600年、関ヶ原の戦い」とだけ覚える。
でも、その前後の出来事や理由とのつながりがないため、記憶が孤立してしまいます。
孤立した記憶は思い出すきっかけがなく、テストのプレッシャーの中では頭から消えてしまいやすいのです。
人間の脳は、バラバラの情報よりも、つながりのある情報の方が覚えやすくできています。
「なぜそうなったのか」「その結果どうなったのか」という流れで理解していれば、一つのことを思い出せば芋づる式に他の情報も出てきます。
丸暗記ではこのつながりが作れないので、記憶が定着しにくいのです。
また、丸暗記は「短期記憶」に頼る方法でもあります。
テスト直前に詰め込んだ情報は、テストが終わればすぐに忘れてしまいます。
だから次のテストや入試のときには、また一から覚え直さなければなりません。
これでは時間も労力も無駄になってしまうのです。
入試や応用問題では「理解」が武器になる
定期テストなら、教科書の内容をそのまま問う問題も出ます。
でも入試や実力テストでは、そう簡単にはいきません。
入試問題の多くは「知識を使って考える」タイプの問題です。
例えば数学なら、公式を知っているだけでは解けません。
その公式がなぜ成り立つのか、どんな場面で使うのかを理解していないと、応用問題には対応できないのです。
社会や理科でも同じです。
単純に用語を答える問題だけでなく、「この現象が起きた理由を説明しなさい」「AとBの共通点を述べなさい」といった記述問題が増えてきます。
これらは丸暗記では対応できません。
物事のつながりや仕組みを理解していることが求められるのです。
理解していれば、初めて見る問題でも「これはあの考え方が使えそうだ」と気づくことができます。
知識と知識がつながっていて、それを自由に組み合わせられる状態——これが「理解している」ということなのです。
さらに、理解した知識は忘れにくくなります。
一度腹に落ちた内容は、たとえ細かい部分を忘れても、考えれば思い出せます。
丸暗記のように「覚えているか、忘れているか」の二択ではなく、「理解しているから再現できる」という状態になれるのです。
ノートが「理解」と「記憶」をつなぐカギになる

では、どうやって理解を深めていけばよいのでしょうか。
その答えの一つが「ノートの取り方」にあります。
ただの板書の写しでは意味がない
多くの中学生がやっているノートの取り方は、先生が黒板に書いたことをそのまま写すというものです。
でも、これでは本当にもったいノートの取り方と言えるでしょう。
板書を写すだけの作業は、言ってしまえば「コピー機」と同じです。
手を動かしてはいても、頭は働いていません。
写している間は集中しているように見えても、実際には内容を理解していないことも多いのです。
テスト前にそのノートを見返したとき、「これ、どういう意味だっけ?」となった経験はありませんか。
それは、書いたときに理解していなかったからです。
ノートに書いてあるのは先生の言葉であって、自分が理解した内容ではありません。
だから見返しても分からないのです。
もちろん、板書を写すこと自体が悪いわけではありません。
でも、それだけで終わってしまってはダメなのです。
板書を「素材」として、そこに自分の理解や気づきを加えていく。
そうすることで、ノートは初めて「使える道具」になるのです。
「思考の整理」としてのノートの役割
ノートの本当の価値は、「思考を整理する場所」であることにあります。
授業を聞いていると、さまざまな情報が頭に入ってきます。
先生の説明、黒板の図、教科書の内容、自分の疑問——これらがバラバラのまま頭の中にあると、混乱してしまいます。
ノートは、これらの情報を整理して、一つの流れにまとめる場所なのです。
例えば、理科の授業で「光合成」について学んだとします。
先生は「葉緑体」「二酸化炭素」「デンプン」といった言葉を説明します。
これらをただ書き並べるのではなく、「葉緑体の中で、二酸化炭素と水から、光のエネルギーを使ってデンプンが作られる」という流れで整理するのです。
矢印や図を使って視覚的に表現すれば、さらに理解が深まります。
つまり、ノートを取るという行為は、「情報を受け取る→理解する→自分なりに整理する」というプロセスなのです。
このプロセスを経ることで、知識が頭の中にしっかりと定着します。
また、ノートに書くことで「自分は何を理解していて、何が分かっていないのか」が見えてきます。
説明を聞いてもピンと来ない部分は、ノートにも上手く書けないはずでしょう。
そういう部分に印をつけておけば、後で重点的に復習できます。
ノートは単なる記録ではなく、「学びの過程」そのものなのです。
授業中に効果を発揮するノート術とは?
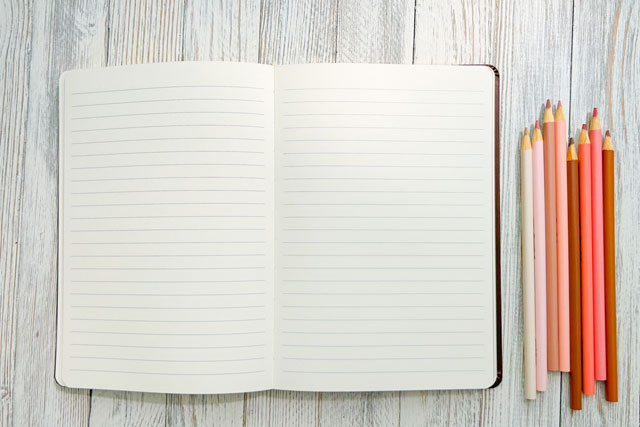
では具体的に、授業中はどのようにノートを取ればよいのでしょうか。
ここでは、すぐに実践できる方法を紹介します。
大事なキーワードは色や記号で強調
授業中、先生は大量の情報を話します。
その中で特に重要なポイントを見極めて、ノートに残すことが大切です。
まず、先生が「ここ大事だよ」「テストに出るよ」と言ったところは確実に印をつけましょう。
色ペンで囲む、アンダーラインを引く、星マークをつけるなど、後で見返したときにパッと目に入る工夫をすると効果的です。
ただし、色を使いすぎるのは逆効果です。
ノート全体が色だらけになると、どこが本当に重要なのか分からなくなってしまいます。
使う色は2〜3色に絞るのがおすすめです。
例えば、「最重要ポイント=赤」「補足情報=青」「自分の疑問=緑」といった具合にルールを決めておくとよいでしょう。
記号を活用するのも効果的です。
「!」マークで重要度を示したり、「?」マークで疑問点を記したり、「→」で因果関係を示したりする方法があります。
記号は書くのも速いですし、視覚的にも分かりやすくなります。
自分なりの記号ルールを作ってみましょう。
先生の口頭説明を「自分の言葉」で書き足す
授業では、黒板に書かれていない重要な情報も、先生が口頭で説明してくれることが多いでしょう。
これを聞き逃さずにノートに加えることが大切です。
ただし、ここで重要なのは「先生の言葉をそのまま書く」のではなく、「自分の言葉に置き換えて書く」ことです。
例えば、先生が「この公式は、つまり距離を時間で割れば速さが出るってことだね」と説明したとします。
これをそのまま書くのも悪くはありませんが、「速さ=距離÷時間。走った距離が分かれば、かかった時間で割れば速さが計算できる!」というふうに、自分なりの理解を加えて書いてみましょう。
この「自分の言葉に置き換える」作業が、実は理解を深める鍵なのです。
先生の説明を自分の言葉にするためには、内容をしっかり咀嚼して理解する必要があります。
ただ聞いて写すだけでは通らないプロセスです。
また、自分の言葉で書いておけば、後で見返したときにスッと頭に入ってきます。
先生の言葉は先生にとって分かりやすい表現でも、自分にとってベストな表現とは限りません。
自分が一番理解しやすい言葉でノートを作ることが大切です。
最初は難しいかもしれませんが、慣れてくると自然にできるようになります。
「つまりこういうことか」と考えながらノートを取る習慣をつけましょう。
科目別・効果的なノートの取り方
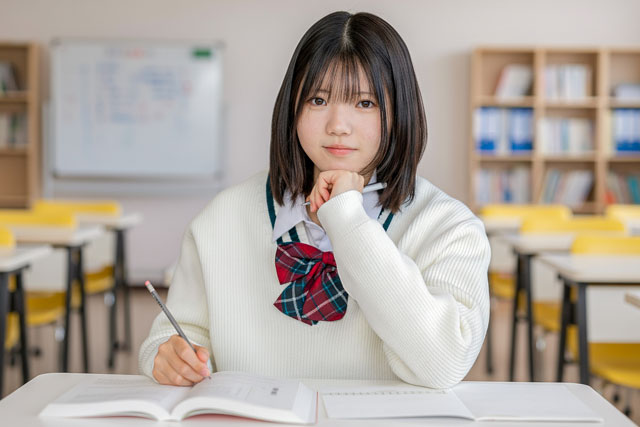
科目によっては、ノートの取り方のコツが変わってきます。
それぞれの特性に合わせた方法を見ていきましょう。
数学|途中式と「なぜそうなるか」をメモする
数学のノートで大切なのは、答えだけでなく「どうやってその答えにたどり着いたか」を残すことです。
計算問題を解くときは、途中式を省略せずに全部書くようにしましょう。
後で見返したときに、「どこでどう変形したのか」が分かるようにしておくことが大切です。
特に自分が間違えやすいところや、つまずきやすいところは、丁寧に書いておくと効果的です。
さらに有効なのが、「なぜそうなるのか」をメモすることです。
例えば、方程式を解くときに両辺を同じ数で割る操作をしたなら、「両辺を3で割る→等号が保たれる」とメモしておく。公式を使ったら、「この場面ではこの公式を使う」と書き添えておくのです。
こうすることで、ただ機械的に計算するのではなく、「この操作にはこういう意味がある」と理解しながら進められるようになります。
応用問題に直面したときも、「この状況ならあの考え方が使えそうだ」と気づけるようになるのです。
また、間違えた問題は「どこで間違えたか」「なぜ間違えたか」を赤ペンで書き込んでおきましょう。
同じ間違いを繰り返さないための貴重な記録になります。
グラフや図は大きく丁寧に
数学では図やグラフも重要な情報です。
黒板の図を小さく適当に写すのではなく、大きくはっきりと描きましょう。
座標軸の目盛りや、グラフの特徴的なポイント(頂点や切片など)もしっかり記入することが大切です。
図を描くことで、問題の状況を視覚的に理解できます。
図形の問題なら、補助線や角度、長さなどを書き込んでいくことで、解き方が見えてくることも多いのです。
英語|例文・和訳・文法ポイントをひとまとまりで書く
英語のノートは、「例文」「和訳」「文法ポイント」の3つをセットで書くのがおすすめです。
新しい文法を学んだら、まず例文を書きます。
次にその和訳を書き、最後に文法のルール(「現在完了形は have+過去分詞」など)を書きましょう。
この3つが揃って初めて、その文法が使えるようになります。
例文だけでは使い方が分かりませんし、文法ルールだけでは実際にどう使うかが分かりません。
和訳を加えることで、日本語との対応関係が理解できます。
この3点セットで覚えることで、英語の理解が深まるのです。
また、単語や熟語を書くときは、単語だけを羅列するのではなく、例文の中で覚えるようにしましょう。
「look forward to」なら、「I’m looking forward to seeing you.(君に会うのを楽しみにしています)」という例文とセットで書くのがおすすめです。
文脈の中で覚えた方が記憶に残りやすく、実際に使えるようになります。
間違えやすいポイントを色分け
自分がよく間違える文法ポイント(例えば三単現のsを忘れる、前置詞を間違えるなど)は、色ペンで目立つように書いておきましょう。
テスト前に見返すときに、「ここは要注意!」とすぐに分かるようになります。
理科・社会|表や矢印で「因果関係」を整理する
理科や社会は、「原因と結果」「条件と変化」といった因果関係を理解することが大切です。
ノートでもこの関係性を視覚的に表現するようにしましょう。
例えば、社会で「産業革命」について学んだとします。
文章を長々と書くのではなく、矢印を使って整理すると分かりやすくなります。
「蒸気機関の発明 → 工場制機械工業の発達 → 大量生産が可能に → 都市への人口集中 → 労働問題の発生」
このように、出来事の流れを矢印でつないでいくと、歴史の因果関係が一目で分かります。
理科でも同じです。
「光合成の仕組み」なら、材料(二酸化炭素、水)と条件(光、葉緑体)から、結果(デンプン、酸素)が生まれる流れを図で表しましょう。
実験の手順も、番号や矢印を使って整理すると分かりやすくなります。
表で情報を比較整理
複数の概念を比較するときは、表を使うと効果的です。
例えば「動物細胞と植物細胞の違い」を学んだときには、表を作って比較するようにしましょう。
| 項目 | 動物細胞 | 植物細胞 |
|---|---|---|
| 細胞壁 | なし | あり |
| 葉緑体 | なし | あり |
| 液胞 | 小さい | 大きい |
こうすることで、共通点と相違点が明確になり、記憶にも残りやすくなります。
社会でも「鎌倉時代と室町時代の比較」「大統領制と議院内閣制の違い」など、表を活用できる場面は多くあります。
国語|本文引用+自分の意見や要点を添える
国語のノートは、他の科目とは少し違った工夫が必要です。
説明文や論説文を学ぶときは、筆者の主張や要点をノートにまとめましょう。
その際、本文の重要な部分を短く引用しつつ、それを自分の言葉で言い換えたり、要約したりすると効果的です。
「つまり、筆者は〇〇と言いたいのだ」というふうに、自分なりの理解を書き添えてみてください。
小説や物語なら、登場人物の心情や場面の状況をメモするのがおすすめです。
「ここで主人公は悲しんでいる。なぜなら…」といったように、心情とその理由をセットで書くと理解が深まります。
また、自分の感想や疑問を書くのも効果的です。
「この表現は美しいと思った」「なぜ主人公はこんな行動を取ったのか?」など、自分の考えを記録しておきましょう。
国語は「正解」だけを覚える科目ではなく、自分なりに考える科目です。
自分の思考の跡をノートに残すことで、理解が一層深まります。
言葉の意味や背景知識も書き込む
難しい言葉が出てきたら、その意味をノートに書いておきましょう。辞書で調べた内容や、先生が説明してくれた背景知識なども記録すると役立ちます。本文を理解するための「周辺情報」も、ノートに集約していくのです。
復習に役立つノート術 :「見返しても分かるノート」にする工夫

ノートの真価は、後で見返したときに発揮されます。
ここでは、復習しやすいノート作りのコツを紹介していきましょう。
授業後に5分だけ復習メモを追加する
授業が終わったら、すぐに席を立つのではなく、5分だけノートを見返す時間を作りましょう。
その日のうちに復習することで、記憶の定着率は大きく上がります。
授業直後なら内容をまだ覚えているので、「今日学んだポイントは何だったか」をノートに簡単にまとめることができます。
例えば、ノートの最後に「今日のまとめ」欄を作り、箇条書きで3つくらいのポイントを書いておくと効果的です。
今日のまとめ:
- 連立方程式は加減法と代入法がある
- 加減法は係数を揃えてから足し引きする
- どちらの方法でも答えは同じになる
これだけでも、その日の学習内容が頭の中で整理されます。
帰宅後や数日後に見返したときも、この「まとめ」を読むことで授業の内容を思い出しやすくなります。
疑問点を空欄にしておき、後で調べて埋める
授業中、どうしても理解できなかった部分や、聞き取れなかった部分があるかもしれません。
そういうときは、無理に埋めようとせず、あえて空欄にしておきましょう。
ただし、ただの空欄ではなく、「ここが分からない」と分かるように印をつけておくことが大切です。
「?」マークをつけたり、枠で囲んだりするとよいでしょう。
そして放課後に、友達に聞いたり、先生に質問したり、教科書や参考書で調べたりして、その空欄を埋めていきます。
このプロセスこそが、深い学びにつながります。
自分で調べて解決した内容は、最初から書いてあった内容よりもずっと記憶に残ります。
「分からない → 調べる → 分かった!」という体験が、理解を確実なものにしてくれるのです。
また、疑問点を明確にすることで、自分の弱点も見えてきます。
同じような疑問が何度も出てくるなら、その分野が苦手だということです。
重点的に復習すべき場所が分かるようになります。
ノートを整理して理解を深める方法
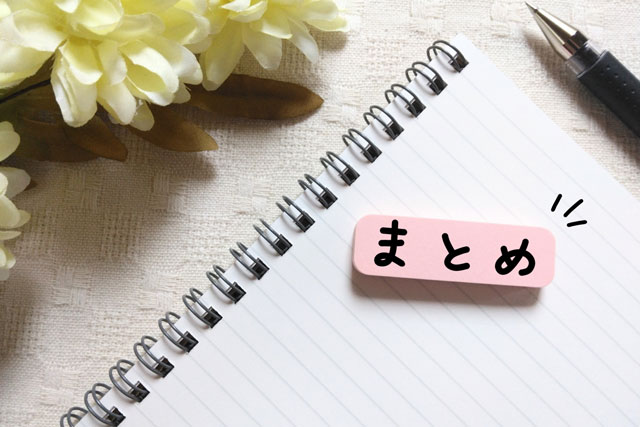
ノートの取り方をさらに工夫することで、理解をより一層深めることができます。
ここでは、いくつかの整理術を紹介していきましょう。
「まとめノート」と「授業ノート」を分けるメリット
ノートを2種類用意する方法があります。
「授業ノート」と「まとめノート」です。
授業ノートは、授業中にリアルタイムで書くノートです。
先生の説明や板書、自分の気づきなどを、その場でどんどん書き込んでいきます。
ある意味「下書き」のようなもので、多少乱雑でも構いません。
大事なのは、授業の内容を漏らさず記録することです。
一方、まとめノートは、授業後や単元が終わったときに作るノートです。
授業ノートや教科書を見ながら、重要なポイントを自分なりに整理して書き直します。
図や表を使って視覚的に分かりやすくしたり、関連する情報をまとめたりすることができます。
こちらは「清書」のイメージです。
この2段階方式のメリットは、「情報の咀嚼」が進むことです。
授業ノートに書いた内容を、まとめノートに書き直す過程で、もう一度内容を考え直すことになります。
「この情報とこの情報はつながっている」「この部分が重要だな」と気づきながら整理できるのです。
まとめノートを作る作業自体が、優れた復習になります。
ただし、まとめノートは全科目・全単元で作ると時間がかかりすぎます。
苦手な科目や、特に重要な単元に絞って作るのがおすすめです。
色分けやマークで一目でわかるようにする
ノートを見返したときに、パッと見てどこが重要なのかが分かるようにしておくと、復習の効率が上がります。
前にも触れましたが、色分けは2〜3色に絞ることが大切です。
例えば次のようなルールを作るとよいでしょう。
- 赤:最重要ポイント、テストに出る内容
- 青:補足説明、詳しい情報
- 緑:自分の疑問や気づき
このルールを守ってノートを取ると、後で見返したときに「まず赤だけ見て重要ポイントを確認 → 時間があれば青も読む → 緑は解決したかチェック」という効率的な復習ができます。
さらに、マークも活用しましょう。
- ★:超重要
- !:注意点、間違えやすいところ
- ?:疑問、未解決の問題
- ☑:理解できた、解決した
こうした記号を使うことで、ノートが「ただの記録」から「学習管理ツール」へと進化します。
定期テスト前に役立つ「要点整理ノート」の作り方
テスト前には、「要点整理ノート」を作るのが効果的です。
これは、テスト範囲の最重要ポイントだけを凝縮したノートのことです。
まず、授業ノートやまとめノート、教科書を見返して、「これだけは絶対に覚えておくべき」という内容をピックアップしましょう。
それを見開き1ページか2ページにギュッとまとめます。
例えば、歴史なら「江戸時代のまとめ」として、重要な年号、人物、出来事を年表形式で整理します。
理科なら「化学変化のまとめ」として、主な化学反応式と覚え方をリスト化します。
このノートを作る過程で、「本当に大事なのはここだ」と再確認できますし、情報が凝縮されているため、テスト直前の見直しにも最適です。
作るときのコツは、「自分にとって分かりやすい形」にすることです。
他人が見て分かるかどうかは関係ありません。
自分自身が見て「これなら覚えられる!」と思える形にしましょう。
図やイラスト、語呂合わせなど、何でも使ってかまいません。
中学生におすすめのノートの取り方3選

ノートの取り方には、さまざまな方法があります。
ここでは、中学生が実践しやすく、効果的な3つのノート術を紹介します。
これらは大学生や社会人も活用している実証済みの方法です。
初めて聞く名前かもしれませんが、仕組みはシンプルで取り入れやすいので安心してくださいね。
コーネル式ノートの特徴と中学生向けアレンジ
コーネル式ノートとは、アメリカのコーネル大学で開発されたノート術です。
ページを3つのエリアに区切って使う方法で、復習がしやすいのが特徴です。
基本の構造
ノートのページを次のように区切ります。
- 右側の大きなスペース(ノートエリア):授業中に説明や板書を書く場所。ページの3分の2くらいの幅を使う。
- 左側の細いスペース(キーワードエリア):重要な用語や質問を書く場所。ページの3分の1くらいの幅。
- 下側の横長スペース(まとめエリア):その日の授業内容を要約する場所。5〜6行分くらい。
使い方
授業中は、右側のノートエリアに普通にノートを取ります。
授業後に、左側のキーワードエリアへ右側の内容に対応する重要語句や質問を書き込みましょう。
例えば、右側に「光合成の仕組み」について書いてあるなら、左側には「光合成とは?」「必要なものは?」といった質問を書いておくのです。
最後に、下のまとめエリアに、そのページ全体の要点を2〜3文でまとめるようにしましょう。
復習での活用
復習するときは、まず左側のキーワードだけを見て、右側の内容を思い出せるか試しましょう。
「光合成とは?」という質問を見て、自分で説明できるかチェックします。
思い出せなければ、右側を見て確認します。
この方法だと、ノート自体が「問題集」のようになります。
自分で自分にクイズを出して、理解度を確認できるのです。
中学生向けアレンジ
最初から完璧に3分割するのが難しければ、簡単にアレンジしても大丈夫です。
例えば、ページの左端に定規で縦線を引いて、5センチくらいの余白を作るだけでもOKです。
そこに重要語句や「?」マークをつけた疑問を書き込んでいきましょう。
下のまとめは、余裕があるときだけ書けば十分です。
また、全科目でこの方式を使う必要はありません。
暗記が多い社会や理科など、特に復習が必要な科目に絞って使うのがおすすめです。
コーネル式の良いところは、「ノートを取る」「整理する」「復習する」という3つのステップが、一つのノートの中で完結することです。
テスト前に見返すとき、左側を隠して右側の内容を思い出す練習ができるため、効率的に記憶をチェックできます。
T字ノートの使い方と暗記科目への応用
T字ノートは、ページを縦に2つに分けて使う方法です。
文字通り、ページの真ん中に縦線を引いて「T」の字の形にします。とてもシンプルですが、さまざまな使い方ができる便利な方法です。
基本構造
ノートのページを縦に2分割し、左右それぞれのスペースに、関連する情報を対応させて書いていきます。
使い方の例
- 原因と結果:左側に「原因・理由」、右側に「結果・影響」を書く。歴史で「なぜその出来事が起きたか」と「その結果どうなったか」を対応させるのに便利。
- 問題と答え:左側に「問題・質問」、右側に「答え・解説」を書く。暗記科目で自作の問題集を作るイメージで活用したり、復習のときは、右側を隠して左側の問題に答える練習ができたりする。
- 英語と日本語:左側に「英文」、右側に「和訳」を書く。英語の勉強に最適。
- 用語と説明:左側に「専門用語」、右側に「その意味・説明」を書く。理科や社会の用語整理に使える。
暗記科目への応用
T字ノートは、特に暗記が必要な科目で威力を発揮します。
例えば、社会の歴史なら、左側に「年号・人物名」、右側に「その人がしたこと・時代背景」を書きましょう。
復習するときは、右側を折って隠し、左側の年号や人物名だけを見て内容を思い出す練習をします。
理科の用語なら、左側に「光合成」「蒸発」などの用語を書き、右側にその説明を書きます。
用語を見て説明できるか、説明を見て用語が思い出せるかを両方向から確認できるのです。
英単語なら、左側に「英語」、右側に「日本語」を書いて、自作の単語帳として使えます。
ノートを縦に折れば、片側だけを見て練習できるのでとても便利です。
メリット
T字ノートの最大のメリットは、「情報の対応関係が一目で分かる」ことです。
左と右の情報がセットになっているため、関連づけて覚えやすくなります。
また、片側を隠して練習できるので、復習にもとても使いやすい方法です。
シンプルな形式なので、ノート術に慣れていない人でもすぐに始められるという点も大きな魅力です。
シンプルで実践しやすい「見開き整理型ノート」
見開き整理型ノートは、ノートの見開き2ページを一つの単位として使う方法です。
左ページと右ページで役割を分けることで、情報を体系的に整理することができます。
基本構造
ノートを開いたとき、左右のページをそれぞれ異なる目的で使います。
- 左ページ:授業の内容、説明、例題など「インプット」の情報
- 右ページ:自分の気づき、まとめ、練習問題など「アウトプット」の情報
使い方の例
授業中は、左ページに通常通りノートを取ります。
先生の説明や板書、教科書の内容などを書き込んでいきましょう。
授業後や復習のときは、右ページを使って情報を整理します。
左ページの内容をもとに、自分なりのまとめを書いたり、図を描いたり、練習問題を解いたりすると効果的です。
例えば、数学なら左ページに例題と解き方を書き、右ページに類似問題を自分で解きます。
理科なら左ページに実験の手順と結果を書き、右ページにその考察や図解をまとめます。
メリット
この方法の良いところは、「インプットとアウトプットが同じ場所にある」ことです。
授業で学んだ内容と、自分で考えた内容が見開きで確認できるので、復習のときにとても便利です。
また、右ページを「自分の思考スペース」として自由に使えるのも魅力です。
疑問に思ったことを書いたり、関連する別の知識を書き足したり、自分なりの覚え方を工夫したりと、創造的に活用できます。
最初から完璧にやる必要はありません。
「左は授業、右は自分用」とゆるく決めておくだけでも、ノートが整理されて見やすくなります。
応用パターン
慣れてきたら、科目や目的に応じて使い分けることもできます。
- 英語:左ページに英文、右ページに和訳と文法メモ
- 社会:左ページに教科書の内容、右ページに年表や地図を自分で描く
- 国語:左ページに本文の要約、右ページに感想や意見
見開き整理型ノートは、特別な技術がいらず、どんな科目にも応用できます。
「ノートを2ページセットで考える」という意識を持つだけで、情報の整理力がぐんと高まるのです。
自分に合ったノート術を見つけるポイント
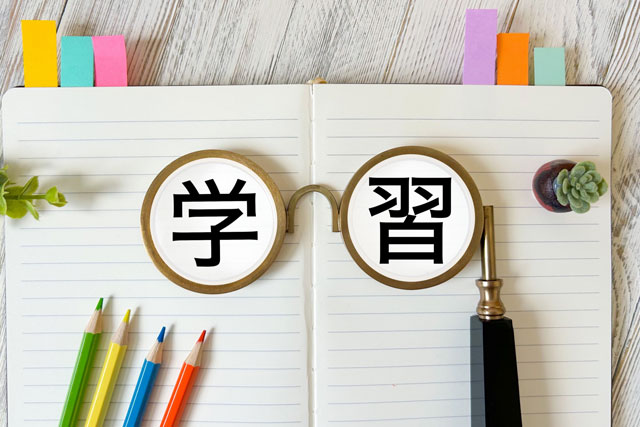
ここまでさまざまなノート術を紹介してきましたが、大切なのは「自分に合った方法を見つける」ことです。
誰かにとって完璧な方法が、みなさんにとってもぴったり合うとは限りません。
科目ごとにノートの形を変える
全ての科目で同じノートの取り方をする必要はありません。
科目の特性に合わせて、ノートの形を変えてみましょう。
例えば、数学は計算の途中式が重要なので、普通のノートに大きく書くのがおすすめです。
社会や理科は情報を整理することが大切なので、コーネル式やT字式が役立つでしょう。
英語は例文と和訳をセットで覚えたいので、見開き型が便利です。
また、同じ科目でも単元によって方法を変えても大丈夫です。
歴史の授業では年表を作って流れを整理し、地理の授業では地図を大きく描いて情報を書き込みます。
公民ではT字ノートで用語と説明を対応させます。
こんなふうに、ノートの取り方は科目ごとや単元ごとに柔軟に対応できるのです。
最初は試行錯誤が必要ですが、いろいろ試していくうちに「この科目にはこの方法が合っている」と分かってきます。
そうして、自分だけのノート術が確立していくのです。
きれいさより「使いやすさ」を重視する
ノートをきれいに書くことに夢中になって、肝心の授業を聞き逃してしまう——これはよくある失敗です。
もちろん、読みやすいノートは大切です。
でも「芸術作品のようなノート」を目指す必要はありません。
大事なのは、後で自分が見返したときに理解できるかどうかです。
文字が多少乱雑でも、内容が理解できていて重要なポイントが押さえられていれば、それは良いノートといえます。
逆に、どれだけきれいに書いても内容が理解できていなければ意味がありません。
ノートは他人に見せるためのものではなく、自分が学ぶためのものだということを忘れないようにしましょう。
ただし、最低限の読みやすさは必要です。
後で自分でも読めないほど走り書きしてしまうのは問題です。
「授業中は速さ重視で書き、復習のときに整理する」というように、2段階で考えるのも良い方法です。
また、「きれいに書き直す作業」自体が復習になることもあります。
乱雑に書いたノートを、後できれいにまとめ直すことで、内容をもう一度整理できます。
時間に余裕があるときは、試してみても良いでしょう。
大切なのは、バランス感覚です。
きれいさと効率の両方を考えながら、自分にとってベストな方法を見つけていきましょう。
ノートを活かす実践テクニック
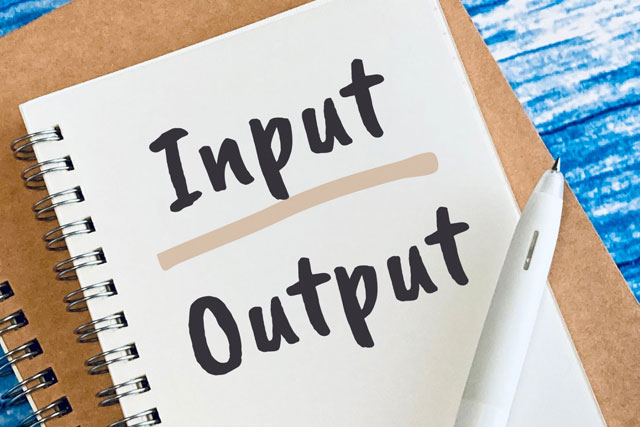
ノートを取るだけでなく、それをどう活用するかが重要です。
ここでは、ノートの価値を最大限に引き出す方法を紹介します。
テスト勉強のときは「自分への質問集」として読む
ノートを見返すとき、ただ読むだけでは効果は薄いものです。
「見たことがある」と思っても、実際にテストで答えられるかどうかは別問題だからです。
効果的な方法は、ノートを「問題集」として使うことです。
ノートの内容を見ながら、「これを自分に質問するとしたら?」と考えてみましょう。
例えば「光合成には葉緑体が必要」と書いてあったら、「光合成に必要なものは?」「葉緑体はどこにある?」「光合成で作られるものは?」といった質問を自分に投げかけてみます。
そして、ノートを見ずに答えられるか試してみましょう。
コーネル式やT字式のノートなら、最初からこの使い方がしやすい構造になっています。
でも普通のノートでも、「この部分はどういう意味?」「なぜこうなる?」と自分に問いかけながら読むことで、ただの「確認」が「テスト」に変わります。
答えられなかった部分には印をつけて、重点的に復習しましょう。
そうすることで、「何が分かっていて、何が分かっていないか」が明確になり、効率的な学習ができるのです。
間違えた問題をノートに追記して「弱点ノート」にする
テストや問題集で間違えた問題は、貴重な学習材料です。
これをノートに集めることで、自分だけの「弱点ノート」を作ることができます。
間違えた問題は、ノートの後ろのページや科目ごとの専用ページに書き写しましょう。
そのとき、ただ問題と答えを書くのではなく、「なぜ間違えたのか」「正しい考え方は何か」「次に同じ間違いをしないための注意点」も一緒に記録しておくのが大切です。
例えば、数学の問題で符号を間違えたなら「マイナスをかけるとプラスになることを忘れていた。計算するときは符号を先にチェックする!」と書きます。
英語で三単現のsをつけ忘れたなら「主語がhe/she/itのとき、動詞にsをつける。毎回主語を確認する習慣をつける!」と書きます。
こうして作った弱点ノートは、テスト前の最終確認に最適です。
新しい問題をたくさん解くよりも、自分が実際に間違えた問題を確実にできるようにするほうが、点数アップにつながることが多いのです。
また、同じような間違いが何度も出てくることに気づくはずです。
「いつも計算ミスする」「いつも単語を間違える」といった自分の傾向が見えてきます。
そうしたら、その部分を特に意識して練習することで、確実に改善できます。
弱点ノートは、自分の成長の記録でもあります。
過去に間違えた問題が、今は楽に解けるようになっている——そう実感できたとき、学力が上がっているのだと自信を持てるはずです。
ノートは「自分だけの参考書」!

ここまでさまざまなノート術を紹介してきました。
最後に、ノートに対する考え方そのものについて見ていきましょう。
「書いて終わり」から「使えるノート」へ
多くの中学生が、ノートを「書くこと」自体を目的にしてしまっています。
授業が終わってノートを書き終えると、それで満足してしまっています
ノートの本当の価値は、「書いた後」にあります。
書いたノートをどう使うかによって、学習効果は何倍にも変わってきます。
「書いて終わり」ではなく、「書いてから始まる」——この意識を持ちましょう。
授業が終わったら、その日のうちに5分でも見返す。テスト前には繰り返し読み返す。疑問が出てきたら調べて書き足す。間違えた問題を追加する。友達に説明する準備をする。
こうして何度も使い、書き足し、育てていくことで、ノートは「自分だけの参考書」になります。
市販の参考書は誰にでも同じ内容ですが、みなさんのノートには、自分が分からなかったところ、間違えたところ、気づいたことが詰まっています。
だからこそ、自分にとって一番役立つ参考書になるのです。
ノートを「生きた教材」として活用していきましょう。
一度書いたら終わりではなく、常に更新し、使い続ける。そうすることで、ノートはあなたの学力を支える強力な武器になるのです。
丸暗記から理解へ、勉強の質を高める第一歩
この記事の最初で、丸暗記の限界について触れました。
覚えてもすぐに忘れてしまう、応用が利かない、勉強が苦痛になる——丸暗記にはさまざまな問題があります。
しかし、ノート術を変えることで、勉強は「丸暗記」から「理解」へと質が変わります。
理解するというのは、知識と知識がつながることです。
バラバラの点だった情報が、線になり、面になり、やがて立体的な知識として広がっていきます。
そうなると、一つのことを思い出せば、関連する他のことも芋づる式に引き出せるようになります。
理解していれば、暗記もずっと楽になります。
意味のない文字列を覚えるのは大変ですが、意味のある物語として理解できれば、自然と頭に入ってきます。
もし一度忘れてしまっても、考えれば思い出すことができるのです。
そして何より、理解すると勉強が面白くなります。
「なるほど、そういうことか!」と分かる瞬間の喜び。知識と知識がつながって、世界の見え方が変わる体験。これは丸暗記では決して味わえない、学ぶことの本当の楽しさです。
ノート術を変えることは、単なるテクニックの話ではありません。
勉強に対する考え方、学びへの姿勢そのものを変えることにつながります。
今日から、ノートを「理解を深める道具」として使ってみましょう。
最初は慣れないかもしれませんし、時間がかかるかもしれません。
でも続けていけば、必ず効果を実感できるはずです。
みなさんのノートは、自分の成長の記録であり、思考の軌跡であり、未来への武器です。
大切に育てていきましょう。
まとめ
丸暗記に頼った勉強は、テストの点数を一時的に上げることはできても、本当の学力にはつながりません。
入試や応用問題に対応し、知識を長く定着させるためには、「理解する」ことが何より大切です。
そして、その理解を深めるための強力な道具がノートです。
ただ板書を写すのではなく、自分の言葉で整理し、図や色で視覚化し、疑問や気づきを書き込んでいきましょう。
授業ノート、まとめノート、弱点ノートなど、目的に応じて使い分けることができます。
コーネル式、T字式、見開き型など、自分に合った形を見つけることも大切です。
重要なのは、ノートを「書いて終わり」にしないことです。
何度も見返し、書き足し、活用することで、ノートはみなさんにとって最強の参考書になります。
さらに、友達に説明したり、自分に質問したりすることで、理解はより深まります。
ノート術を変えることは、勉強の質を根本から変えることにつながります。
丸暗記の苦しい勉強から、理解する喜びのある学びへ。その第一歩を、今日から踏み出してみましょう。
みなさんのノートが、自分の学びを、そして未来を変える道具になることを願っています。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。






