【北海道】高校受験の仕組みと勉強法|入試制度・内申点・志望校選びを解説

北海道の高校受験には、他の都府県とは異なる独自の制度がいくつかあります。
学区制度や全道統一の共通問題、内申点と学力検査の配点比率など、北海道ならではの特徴を理解することが、志望校合格への第一歩です。
この記事では、北海道の高校受験制度の全体像から、内申点の仕組み、効果的な勉強法まで、中学生や保護者のみなさんが知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。
目次
北海道の高校受験の基本情報

公立高校と私立高校の違い
北海道の高校は、公立高校(道立高校・市立高校)と私立高校に分かれています。
公立高校は就学支援制度の対象となっており、授業料は実質無償で通えることから、多くの受験生が第一志望とします。
道立高校は北海道が設置・運営し、市立高校は札幌市や函館市などが運営する学校です。
私立高校は、各学校法人が独自の教育方針や校風を打ち出しており、進学・部活動・国際教育など特色ある教育で人気があります。
第一志望に私立高校を選ぶ受験生も増えており、特待生制度や奨学金制度を設けている学校も多くあります。
公立高校の入試は全道で統一された制度に基づいて実施されます。
一方、私立高校は各校が独自に入試日程や選抜方法を決定しており、出願条件や選考内容も異なるため、事前の情報収集が重要です。
一般的には、公立高校を第一志望、私立高校を併願校として受験する生徒が多く見られます。
入試日程の流れと出願の注意点
北海道の高校入試は、毎年1月下旬〜3月上旬にかけて行われます。
私立高校の推薦入試は1月下旬ごろ、一般入試は2月中旬、公立高校の推薦入試は2月中旬、一般入試は3月上旬に実施されるのが通例です。
公立高校の出願では、同じ高校内に複数の学科がある場合、第1志望と第2志望を選択できる制度があります。
ただし、この制度はすべての高校で利用できるわけではなく、設定されていない高校・学科もあるため注意が必要です。
また、出願書類には調査書(内申書)などが必要となるため、早めの準備が大切です。
特に推薦入試を希望する場合は、中学校が設けている推薦基準を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
私立高校の出願では、学校ごとに出願期間・提出書類・選抜方法が異なります。
複数校を受験する場合は、試験日が重ならないように注意することが大切です。
また、入学検定料の納入方法なども学校によって異なるため、募集要項をしっかりと確認しましょう。
推薦入試と一般入試の違い
推薦入試は、中学校長の推薦を受けた生徒を対象に行われる選抜方法です。
主に面接や作文、小論文などが実施され、学力検査は行われない場合が多くなっています。
内申点に加えて、部活動や生徒会活動、ボランティアなどの取り組みが評価されるケースもあります。
また、令和5年度(2023年度)入試から推薦入試は自己推薦方式に変更され、中学校長の推薦が不要になりました。
自己推薦型では、生徒自身の志望理由や活動実績をもとに出願できるため、より柔軟な選抜方法となっています。
どちらの形式を採用しているかは高校ごとに異なるため、出願要件や選抜方法は志望校の募集要項を必ず確認しましょう。
<参考資料>北海道教育委員会 : 高等学校入学者選抜情報
推薦入試で合格した場合、一般入試を受ける必要はなく、進路が早期に決まるというメリットがあります。
ただし、推薦には各高校ごとに基準があり、内申点の水準や活動実績が求められることもあるため、希望者は中学校の先生と早めに相談しておくことが重要です。
一般入試では、5教科(国語・数学・社会・理科・英語)の学力検査と、調査書(内申点)をもとに合否が決まります。
北海道では、内申点に基づいて「A」〜「M」の13段階でランクが設定され、まずはこのランクと学力検査の得点との組み合わせによって選抜の第1段階が行われます。
ランクや点数の基準は高校によって異なるため、志望校の過去の選抜資料や進路指導の先生のアドバイスも参考にしながら、しっかりと対策を立てましょう。
推薦入試で不合格だった場合でも、同じ高校の一般入試を受験することが可能です。
当日の試験で高得点を取れれば逆転合格も十分あり得るため、実力を発揮できるような準備が求められます。
北海道独自の入試の特徴とは?

共通問題の出題形式と配点
北海道の公立高校では、全道統一の「共通問題」が導入されています。
学力検査は国語・数学・社会・理科・英語の5教科で実施され、各教科100点満点、合計500点満点で評価されます。
英語にはリスニングテストも含まれます。
出題範囲は中学校の学習指導要領に準拠しており、基本的な内容から応用まで、幅広く問われます。
記述式問題や思考力を要する問題も多く含まれ、単なる暗記では対応しきれない内容が出題される傾向にあります。
全体としては、基礎〜標準レベルを中心とした構成ですが、過去問を分析すると、教科によっては応用問題や記述力を問う問題も多く、丁寧な準備が必要です。
時間配分や記述の練習も含めた実戦的な対策が効果的です。
学区制度の仕組み(石狩学区・地方学区)
北海道では、道立高校の普通科を中心に学区制度が採用されています。
道内は大きく19の学区に分かれており、基本的には自分が住んでいる学区内の高校を受験する仕組みになっています。
札幌市全域を含む「石狩学区」は道内最大の学区で、札幌南高校・札幌北高校・札幌西高校・札幌東高校などの進学校のほか、商業・工業など専門高校も含めて選択肢が豊富です。
一方、地方学区では旭川、函館、帯広、釧路などに中心高校があり、それぞれの地域に根ざした教育が行われています。
例えば旭川東高校、函館中部高校、帯広柏葉高校などが地域の進学校として知られています。
なお、学区外からの受験も一定の条件下で可能です。
たとえば、保護者の転勤や地理的条件など、特別な事情がある場合は受験が認められるケースもあります。
詳細は中学校や教育委員会への相談が必要です。
面接・作文が課されるケース
北海道の高校入試では、推薦入試で面接が必須となっているほか、一部の公立高校の一般入試でも面接や作文を課す場合があります。
特に総合学科や専門学科では、学科の特性に応じた質問がされることもあります。
面接では、志望動機や将来の目標、中学校生活で頑張ったことなどが一般的な質問内容です。
面接時間は学校によって異なりますが、おおよそ10〜15分程度で、表情・態度・話し方などの印象面も評価対象となります。
作文については、全ての推薦入試で必須というわけではありませんが、実施される場合は600〜800字程度で与えられたテーマに対して自分の考えをまとめる形式が多く、論理的思考力や文章表現力が問われます。
時事問題や高校生活に関するテーマが出題されることもあるため、日頃から自分の意見を持つ習慣を意識することが大切です。
<参考資料>北海道教育委員会 : 令和7年度(2025年度)道立高等学校入学者選抜の手引
内申点の重要性と計算方法
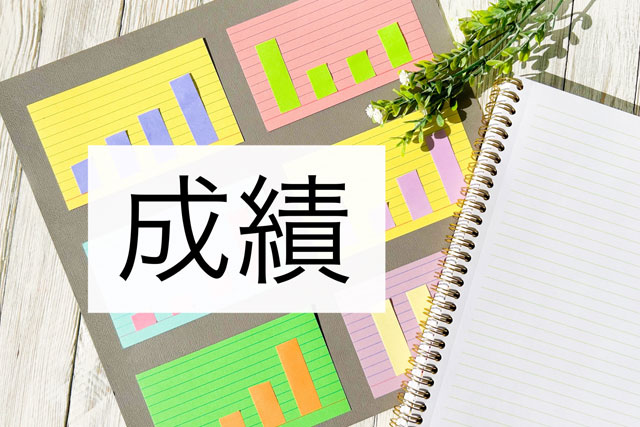
内申点の仕組みと計算方法
北海道の高校入試では、内申点(調査書点)が合否に大きく影響します。
これは中学校での成績をもとに評価されるもので、主に中学1年生から3年生までの9教科(国語・数学・社会・理科・英語・音楽・美術・保健体育・技術・家庭)が対象となります。
内申点は、各教科5段階で評価された成績を、学年ごとに重みをつけて合計することで算出されます。
【内申点の計算方法】
- 中学1年生:5段階×9教科×2倍=最大90点
- 中学2年生:5段階×9教科×2倍=最大90点
- 中学3年生:5段階×9教科×3倍=最大135点
このように、中1・中2の成績は2倍、中3の成績は3倍として扱われ、合計315点満点で計算されるのが一般的です。
内申点の配点比率や合否への影響は高校によって異なるものの、どの高校を目指す場合でも中3の成績の重みが大きいため、日々の授業態度や提出物、小テストなども含めて丁寧に取り組むことが大切です。
内申点と学力検査の比率
北海道の公立高校入試では、内申点と学力検査の点数を一定の比率で合算して総合得点を算出し、合否を判断します。
もっとも多いのは内申点:学力検査=5:5の比率で、全体の約7割の高校がこの配点を採用しています。
ただし、すべての高校が同じではなく、比率は高校や学科によって異なります。
- 進学校などでは 1:9 や 2:8 のように学力検査を重視する場合があります。
- 総合学科や専門高校では 6:4 や 7:3 など、内申点を重視する場合があります。
このように、自分の得意分野や受験スタイルに合った高校選びが重要です。
得点比率は各高校の募集要項で事前に確認できるため、必ずチェックしておきましょう。
なお、こうした比率や配点、選抜方法などの制度内容は年度によって変更されることもあるため、最新の北海道教育委員会の資料を確認するようにしましょう。
<参考資料>北海道教育委員会 : 令和7年度(2025年度)道立高等学校入学者選抜の手引
内申点が心配な場合の戦略
内申点が思うように伸びない場合でも、志望校合格を諦める必要はありません。
重要なのは、自分の強みを活かせる受験校を選ぶことです。
たとえば、学力検査の比率が高い高校を選ぶことで、当日の試験での挽回が可能になります。
学力検査で高得点を狙うためには、まずは基礎学力の徹底が最優先です。
特に数学と英語は得点差がつきやすい科目であり、計算ミスを減らす練習や文法・語彙の定着が鍵になります。
また、内申点の中でも中学3年生の成績は3倍で換算されるため、最後まで粘り強く取り組むことで点数を上げることが可能です。
特に実技4教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)は努力が反映されやすいため、積極的に取り組みましょう。
さらに、私立高校との併願を活用することで、心理的な安心材料を確保できます。
あらかじめ合格を得ておくことで、公立高校入試に集中しやすくなるというメリットがあります。
志望校の選び方と偏差値の目安

進学校と実業系高校の違い
高校選びでは、自分の将来の進路に合わせて、進学校か実業系高校かを検討する必要があります。
進学校は大学進学を前提とした教育が行われており、国語・数学・英語を中心としたカリキュラムや補習・模試が充実しています。
北海道の代表的な進学校には、札幌南・北・西・東高校や旭川東高校、帯広柏葉高校などがあります。
一方、実業系高校は就職や専門分野での進学を視野に入れた実践的な教育が特徴です。
商業科・工業科・農業科・家庭科などが設置されており、資格取得支援や企業との連携が強みです。
近年では、これらの高校から大学進学を目指す生徒も増えています。
地域別に見る主な高校と特色
石狩学区では、札幌南・北・西・東高校が進学校として広く知られており、それぞれが国公立大学への高い合格実績を誇っています。
中堅校では札幌啓成高校、札幌月寒高校、札幌新川高校なども進学希望者に人気があります。
地方学区でも、旭川東高校(旭川学区)、函館中部高校(函館学区)、帯広柏葉高校(帯広学区)、釧路湖陵高校(釧路学区)などが地域の中核進学校として位置づけられています。
実業系では、札幌商業高校、函館商業高校、旭川工業高校、帯広農業高校などがあり、それぞれの専門分野で高い就職実績や実技教育を提供しています。
※偏差値は目安であり、年度や資料によって数値にばらつきがあります。最新情報は各高校や進学情報サイトなどで確認するようにしましょう。
部活動・通学距離も大事な判断材料
高校選びでは、学力や進路だけでなく、部活動の充実度や通学環境も大切な要素です。
特に北海道のように広大で冬の気候が厳しい地域では、通学にかかる時間や交通手段の安定性も重要です。
一般的に、片道1時間以内が通いやすい目安とされます。
それ以上かかる場合は、下宿や寮を検討する家庭もあります。
部活動については、中学校の競技を続けたい場合、志望校にその部があるかどうかを確認しましょう。
また、初心者でも歓迎される部活や文化活動がある学校も多いため、学校生活全体を見渡して選ぶことが大切です。
高校受験に向けた効果的な勉強法

中1〜中3でやるべき学習の流れ
北海道の高校受験では、内申点と学力検査の両方が重視されるため、中学1年生からの計画的な学習が大きな意味を持ちます。
中1では、学習習慣の定着が最優先課題です。
小学校の内容を復習しつつ、中学校の基礎単元(正負の数、文字式、be動詞など)を確実に理解することが重要です。
定期テストで高得点を目指すことで、内申点のベースを築けます。
中2では、応用力を高める時期です。
数学の一次関数や図形の証明、英語の不定詞・動名詞など、高校入試頻出の単元に取り組みながら、過去問や問題集に触れて入試形式に慣れていきましょう。
中3では、本格的な入試対策が始まります。
9月までに中学校の学習範囲を一通り終え、10月以降は過去問演習や模試を中心に、弱点補強と実戦練習を重ねる時期です。計画的に復習と演習を繰り返すことが合格への鍵となります。
北海道の入試に強い教材と過去問の使い方
北海道の高校入試に対応した学習には、全国対応の教材と北海道向けの教材を組み合わせることが効果的です。
基礎固めには『新研究』『整理と対策』『実力メキメキ合格ノート』など、3年間の内容を網羅できる教材が役立ちます。
過去問対策では『北海道公立高校入試問題集』を活用し、少なくとも5年分以上を繰り返し解くのが理想的です。
解いた問題は「やりっぱなし」にせず、解説を読み、間違えた問題は類題で再演習することが実力アップの近道です。
教科別では、数学は『高校入試合格BON!』、英語は『システム中学英語』、理科・社会は『総整理シリーズ』なども評価が高く、自学にも適しています。
また、他県の入試問題を扱った『全国高校入試問題正解』を使って、多様な出題形式に触れるのも応用力を高めるうえで有効です。
塾や家庭教師の活用ポイント
高校受験に向けた学習をサポートしてくれる手段として、塾や家庭教師の活用は非常に有効です。
大切なのは、自分の学習スタイルや目標に合ったサポートを選ぶことです。
集団塾のメリット
集団塾では、同じ目標を持った仲間と切磋琢磨しながら学習することができます。
授業が体系的に組まれており、進学校対策コースや志望校別講座が設けられていることも多く、特に札幌圏では実績ある塾が多く存在し、競争心を刺激される環境でモチベーションを高めたいタイプの生徒に向いています。
個別指導塾のメリット
個別指導塾は、苦手科目や理解が遅れがちな単元にじっくり取り組める点が強みです。
自分のペースで質問しやすく、弱点を重点的に補強できるため、基礎力を固めたい生徒に適しています。
学力に応じた柔軟なカリキュラムが組まれるため、内申点対策にも有効です。
家庭教師のメリット
家庭教師は、生徒一人ひとりに完全に合わせたマンツーマン指導が受けられる点が最大の特長です。
学校や塾ではカバーしきれないニーズに対応できるため、学習習慣が身についていない生徒や、人前で質問しにくいタイプの生徒にとって心強い存在となります。
特に地方では塾の選択肢が少ないこともあるため、家庭教師の方が柔軟に対応できる場合もあります。
近年はオンライン家庭教師の選択肢も増えており、時間や地域に制限されずに質の高い指導を受けられる環境も整いつつあります。
塾や家庭教師を利用する際は、学校の授業や部活動との両立が可能かどうかを十分に考慮し、無理のない学習スケジュールを立てましょう。
定期的に学習の成果を振り返り、必要に応じて指導内容を見直すことも大切です。
学校の授業・部活動とのバランスを崩さないよう、無理のない学習計画を立てることが大切です。
まとめ
北海道の高校受験は、全道統一の共通問題、19学区による学区制度、内申点と学力検査の比率など、独自の制度が数多く存在します。
これらを正しく理解し、自分の状況に合った志望校や対策法を選ぶことで、合格に大きく近づくことができます。
受験対策は中学3年生になってからではなく、中学1年生からの積み重ねが結果を左右すると言っても過言ではありません。
学習習慣を早期に身につけ、内申点を意識しながら、計画的に力を伸ばしていきましょう。
また、偏差値や進学実績だけでなく、学校の雰囲気や通学のしやすさ、部活動の環境も含めて、自分に合った学校を見つけることが、高校生活をより充実したものにします。
不安を感じることもあるかもしれませんが、正しい情報と積み重ねた努力が、きっと自信につながっていくことでしょう。
この記事が、これから受験に向かう皆さんの道しるべとなれば幸いです。
心から応援しています。
北海道で家庭教師をお探しなら、ソウガクにお任せください!
北海道の中・高・大学の受験対策や、在校中の学校のテスト対策ならお任せください。
北海道で長年家庭教師業を営んでいるソウガクには、地域の教育事情・受験ノウハウが蓄積されています。






